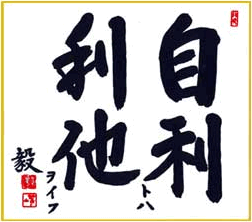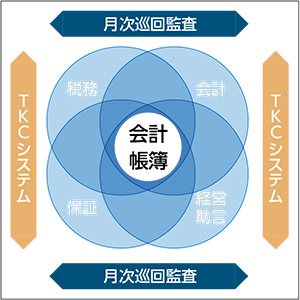News&Topics
雑所得(所得税)
| No.1500 雑所得
[令和3年9月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得をいい、例えば、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。 所得の計算方法 雑所得の金額は、次の(1)から(3)の合計額です。 (1) 公的年金等 収入金額 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得 (注)公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。 (2)業務に係るもの 総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得 (注1)業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。 (注2)令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。 なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。 また、業務に係る雑所得を有しており、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合には、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になります。 (3)(1)、(2)以外のもの 総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得 税額の計算方法 雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。 なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税(詳細は、コード1522を参照してください。)が適用されます。 所得税の源泉徴収 公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。 なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315パーセント(所得税および復興特別所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。 (注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。 注意事項 雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。 根拠法令等 所法35、67、69、120、203の2、204、232、所令196の2、196の3、197、所規40、102、所基通35-1〜2、措法41の10、41の14、復興財確法28 |

2022年8月15日更新
Web3.0時代

平将明衆議院議員東京4区公式サイト ➢ NFTホワイトペーパー(案) NFTホワイトペーパー(案)Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略(概要版)2022年3月 ➢ Web3.0時代を見据えたわが国のNFT戦略 
DXレポート 〜ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開〜➢ DXレポート 〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜(サマリー)(PDF形式:1,301KB)➢ DXレポート 〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜(本文) (PDF形式:4,895KB) ➢ DXレポート 〜ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜(簡易版) (PDF形式:2,693KB) ➢ 経済産業省DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート中間とりまとめ(サマリー)令和2年12月28日 |
MENU
|
1.月次支援金(経産省)(2021年3月1日)一時支援金:令和3年5月31日終了/月次支援金:令和4年1月7日終了 2.弁護士等の報酬 3.税務署窓口における押印の取扱いについて 4. コロナ特例FQA |
中小企業・個人事業者のための支援金

緊急事態宣言の影響緩和 制 度 の 概 要 2021年3月1日(月)より事務局ホームページを開設しました。 月次支援金事務局ホームページはこちら外部リンク <支援金>申請受付は令和4年1月7日終了 |
弁護士・税理士等の報酬料金
 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金[令和3年9月1日現在法令等]国税庁 弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 1 源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれるもの ・弁護士や税理士などの業務に関する報酬・料金は、源泉徴収の対象となります。 ・謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。 ・ただし、支払者が直接、交通機関やホテル等に支払う交通費、宿泊費等で、その金額が通常必要な範囲内のものであるときは、源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。 ・なお、弁護士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収をする必要はありません。 ・また、報酬・料金の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下、「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において、報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。 2 源泉徴収の方法 ・源泉徴収すべき所得税額及び復興特別所得税の額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
(例)150万円の弁護士報酬を支払う場合 (150万円-100万円)×20.42%+102,100円=204,200円 ・源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は204,200円になります。 3 源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納める期限 ・弁護士や税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。 ・ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合には、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限は7月10日、7月から12月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の納付期限は翌年1月20日となります。 (所法204、205、216、所基通204-2、204-4、204‐11、平元直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31) ➢ No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|国税庁 (nta.go.jp) |
税務署窓口における押印の取扱いについて

令和2年12月21日(令和3年4月1日最終更新)
1 国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。 (1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(具体的には別紙1(PDF/150KB)をご覧ください。)
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(具体的には別紙2(PDF/154KB)をご覧ください。)
2 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。 ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となりますので、御留意ください。 3 令和3年4月1日以降の手続に際しては、以下の点に御留意いただきますようお願い申し上げます。 (1) 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています。 押印欄のある様式についても、引き続き印刷して御使用いただけますが、この場合も、上記1、2で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は不要です(以下(2)(3)においても同じ)。 (2) 税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しておりますので、御了承ください。 (3) ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただくことは差し支えありません。 (4) 押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。 (5) 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしています(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です。)。 ➢ 税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp) ※複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法 押印せずに相続税の申告書を提出する場合 ➢ 0020012-133.pdf (nta.go.jp)
※相続税申告の作成・提出についてよくある質問 ➢ 相続税の修正申告書をe-Taxにより提出(送信)することはできますか。 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)  相続税の修正申告書はe-Taxにより提出(送信)することができます。 相続税の修正申告書はe-Taxにより提出(送信)することができます。なお、修正申告書については、令和元年分の申告(2019年1月1日以降に相続等により財産を取得した人の申告)からe-Taxの対象となります。 ※徴収猶予等の電子申請について ➢ 【2021/04/01更新】徴収の猶予等の電子申請について | eLTAX 地方税ポータルシステム 【2021/04/01更新】徴収の猶予等の電子申請について ・4月1日より、徴収の猶予等の申請は「その他申請書」による受付を開始しました。 ・これまで、「税務代理権限証書」で行っていた「徴収の猶予」の申請手続きは、「その他申請書」で行ってください。 ・「その他申請書」に係る特設ページをトップページの「トピックス」に開設し、本お知らせに掲載していた内容は特設ページに移動しましたので、ご参照ください。 
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリ
 ➢ oVoce ➢ oVoceビジネスメタバースでテレワークの課題を解決、離れたメンバーの状況も一目でわかる、テレワーク中のコミュニケーションコストを削減 |