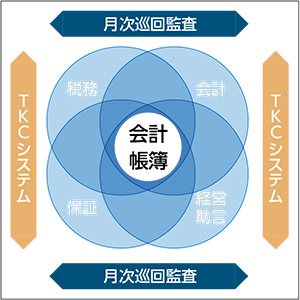�����ōX�������������������

�T�@���_ �@����25�N2��28���A���������ٔ��������i�ȉ��u�O�������v�Ƃ����B�j�����������ƎāA���Œ��͕]���ʒB189�i2�j�ɂ�����A���Ђ̊����ۗL�����ɂ�銔���ۗL�����Ђ̔������u25���ȏ�v����u50���ȏ�v�ɉ������A����25�N5��27���Ȍ�ɑ������ɂ��擾�������Y��]������ꍇ�ɓK�p���邱�ƂƂ��ꂽ�B ����25�N5��27���Ȍ�ɑ����œ��̐\��������҂��A�����O�ɑ������ɂ��擾�������Y��]������ꍇ�ɂ��K�p���邱�Ƃ��ł��A���̗v���ɊY������Αk���čX���̐������ł���Ƃ����B�������@��\����������5�N�i���^�ł̏ꍇ��6�N�j���o�߂��Ă��鑊���œ��ɂ��ẮA�@�ߏ�A�{�����ɌW�������̕]���ʒB��K�p�ł��Ȃ��Ƃ����B �u�O�������v�̌������܂ޖ{�������l��͍X�������̖@��̐������Ԃ��o�߂��Ă������Ƃ���A�]���ʒB�����ɔ����X���̐��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���̌�A�������܂ޑ����l��̖������ł������������Y���ɂ��āA����26�N1��16�������ƒ�ٔ����ɂ����Ē���ɂ���Y��������i�ȉ��u�{������v�Ƃ����B�j���������A�����͖{���e������7����6���擾�����B����ɔ����X���̐����ɂ����āA�u�O�������v�ŔF�肳�ꂽ�]���z�Ɋ�Â��X���̐��������ł��邩�ۂ�������ꂽ�B1 (��)1 �uJUSTAX��303���i����30�N10��10�����j�v�����ŗ���f�[�^�ʐM�����g���E�L�i2018�N�j�A�M�҈ꕔ���B �i���A�ō��ق܂ő����A�u�O�������ŏ��i�v�����ɂ�������炸�A�[�Ŏ҂̐Ŋz���������Ȃ������ߎS�Ȏ���ł���B�j �U�@�O���̊T���i�n�فE���فE�ō��فj
�i��v�ȑO���j �@�@�����́A����25�N3��15���u�O�������v�̊m���A����26�N1��16���u�{������v�����������B �A�@�����́A����26�N5��16���A�]�����Ŗ������ɑ��A�u�{������v�̐����𗝗R�ɁA�����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��u�X���̐����v�i�{���X�������j�������B �@�@�����͖{���e�����̉��z���u�O�������ŔF�肳�ꂽ�z�Ɠ��z�v�ł��邱�Ƃ�O��ɍX���̐����������B �B�@�]�����Ŗ������́A����26�N11��12���A�����ɑ��{���e�����̉��z�́u�����Ő\���ɂ�����z�Ɠ��z�v�Ƃ��ׂ��ł���Ƃ��A �@�u�X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����v�i�{���ʒm�����j������ƂƂ��ɁA �C�@�����ɑ��A�����A�����Ŗ@35��3���Ɋ�Â��u���z�X�������v�i�{���X�������j�������B �D�@�����́A�u�{���ʒm�����v�y�сu�{���X�������v�ɂ�����{���e�����̉��z��s���Ƃ��āA���̈ꕔ�̎���������߂��B ➢�_�_�����\ |
|
(��)�S�@�k�����l�A���{�����Y�A�w��Y����������̑����łɌW��X���̐����Ǝ�������̍S���͈͂̔�~�����n�ٕ���30�N1��24������~�xPwC Legal Japan News, June 2019�A4�ŁA�M�҈ꕔ���B �T�@�d�K�A�w�����Ŗ@�ɂ������Y����������̍X���̐����Ǝ�������̍S���́x�i�V�E������Watch���d�Ŗ@No.148�jTKC���[���C�u�����[�A�y�����ԍ��zz18817009-00-131481651�A�M�҈ꕔ���B �U�@LEX�^DB�y�����ԍ��z28111239�A�y���Ă̊T�v�zA�̑����l�ł���T�i�l�y�ёI��҂炪�A�������Y�łȂ����Y������đ������Y�Ƃ��đ����ł̐\���������Ƃ��āA��Y�������c��������ɑ����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��X���̐����������̂ɑ��āA��T�i�l�鎭�Ŗ������������������Œʑ��@23��1�����Ɋ�Â����̂ł���Ƃ��Ċ��ԓk�߂𗝗R�ɍX�����ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm���������Ƃ͈�@�ł���Ƃ��āA��T�i�l�鎭�Ŗ������ɑ��āA�s�������i�ז@3��2���Ɋ�Â��ʒm�����̎�����ƁA�X�������̋`���t�������߁A��T�i�l���ɑ��āA�s�������ԊҐ������Ɋ�Â��A�ߕ��Ɏx�����������ő����z�̕Ԋғ������߂����Ăɂ����āA���R���T�i�l�̐��������p�������߁A�T�i�l���A���������l�̈�l��������ȏ�A�{�����Y�����O���������ł̐\�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������ȂǂƎ咣���čT�i�����Ƃ���A���������l�Ԃň�Y�͈̔͂ɂ�����������ꍇ�ɂ́A�e�����l���e�l�̔F���ɂ��������Čʂɐ\�����邱�Ƃ��\�ł���ȂǂƂ��āA�T�i�����p���ꂽ����B �V�@LEX�^DB�y�����ԍ��z28111259�A�y���Ă̊T�v�z�����炪�A�������Y�ł͂Ȃ����Y�ɂ�����đ����Ő\�������Ƃ��āA��Y�������c������ɍX���̐����������̂ɑ��āA�퍐�i�鎭�Ŗ������j���A���ԓk�߂𗝗R�ɍX�����ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm���������Ƃ͈�@�ł���Ǝ咣���āA�퍐�ɑ��A�ʒm�����̎�����ƍX�������̋`���t�������߁A�I��I�ɁA�퍐�i���j�ɑ��s�������ԊҐ��������߂�Ȃǂ������Ăɂ����āA�����̐\���ɑ��݂���Ƃ����ߌ�̐��������߂邽�߂ɑ����Ŗ@32���Ɋ�Â��X���̐��������邱�Ƃ͖@�̗\�肷��Ƃ���ł͂Ȃ��A������̍X���̐����́A�X���̊�����k�߂����s�K�@�Ȃ��̂ł���A��L�ʒm�������͓K�@�ł���ȂǂƂ��āA���������p��������B �W�@LEX�^DB�y�����ԍ��z28042338�A�y���Ă̊T�v�z�푊���l�̋��������l��1�l�ł��錴�����A���Y�����ɌW�鑊���ł̖@��\��������ɐ���������Y��������ɂ���Č������擾�������Y�ɌW��ېʼn��i�����@�̋K��ɂ�鑊�����̊����ɂ���Čv�Z����Ă����ېʼn��i�ƈقȂ邱�ƂɂȂ������Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�퍐�i�����Ŗ������j�ɑ��āA�X���̐����������Ƃ���A�퍐�������̏�L�X���̗��R���Ȃ��|�̏������������߁A���̎���������߂����Ăɂ����āA��������������ԂŎ擾������Y�́A�{������ŕ����ɂ�菊���������Y�ɌW��ېʼn��i�͈͓̔��ƂȂ�A�ېʼn��i�y�ё����Ŋz�̂�������ߑ�ƂȂ��Ă��Ȃ��ȂǂƂ��A��L�X�������͕s�K�@�ł���A��L�����͓K�@�ł���Ƃ��āA�����̐��������p��������B �X�@�O�f��4�A�M�҈ꕔ���B 10�@���q�G���ҁu�ŐV�d�Ŋ�{����70�v208���A298�ŁA�M�҈ꕔ���B 11�@�O�f��4�A�M�҈ꕔ���B 12�@�O�f��5�A�M�҈ꕔ���B 13�@�O�f��10�A298�Ł|299�ŁA�M�҈ꕔ���B �X�@�����̌��� �@�X���������̐������@�Ɗ��Ԃɂ����̖@�I������������邱�Ƃɍ�����������B�������d�Ŗ@����`�̊ϓ_����́A�[�ŋ`���҂�������]���̓K�p��r������B��̐����̋@��ł���X���̐����̔r�����̍d���I�^�p�ɂ��ẮA������_��I�^�p�ɉ��߂�ׂ��ł���B�O�������́u���Œʑ��@23��2��3���ɋK��̓��@�{�s��6��1��5���̎��R�v�ɊY�����邪�A �@�����łɊւ���e���ẮA���ꂼ�ꂪ�ʓI�ł���B���Ԍ���A���v���ɂ�����A���邢�͍ŋ߂ł͍ЊQ���ɂ�鏔���x���lj����肳��Ă���B�@�߂̌����Ƃ��Ċ�{�I���x�����ɂ����Ă͏ڍׂȋK��������X���ɂ���B���������āA����̌����͂܂��܂��d�v�Ȃ��̂ƂȂ�B�@�߂ɋK�肳��Ă��Ȃ������̋�̓I�]���ɂ��ẮA�s�����@��`�̗l����悵�Ă���B�{���ł͓Ɛ�֎~�@�̉����ɔ������Y�\���̕]���̕ω��A���邢�͂��̑��̏ω����N���Ƃ��鑈���A�܂��́A�@�߂��z�肵�Ă��Ȃ����Ăɂ�����V���Ȕ��ᓙ�̊m��ɂ��A�@�ߖ��͒ʒB�������������Ȃ���B ���Y�]���ɂ��ẮA���Y�]���ʒB�ɑ傫���ˑ����邱�ƂƂȂ�B������A�Z���Ԃɍ����I�ɂ�������Y��]�����邽�߂̊�͍��̂Ƃ�����Y�]���ʒB�݂̂ł���B�Ӓ�]����Ǝ��]���Ƃ�����i�����邪�A���̃��X�N���A�ʓr��p�E���ԓ���v����B�܂��A���ʂȎ������ꍇ�������A���œ��ǂ͓Ǝ��̊Ӓ�]���ɂ��ẮA�����ېł𗝗R�ɍD�܂������̂Ƃ͍l���Ă��Ȃ� �B14�@����ɂ����Ă��A�]���ʒB�̒�߂�]�����@�ɂ���Ă͓K���Ȏ�����K�ɎZ�肷�邱�Ƃ̂ł��Ȃ����ʂ̎������Ƃ͔F�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�Ӓ�]���z�̍�������ے肵�Ă��鎖�Ⴊ���� �B15 �����ł̊�b�T���z������������ꑊ���ł̐\���������������A�ߔN�́A�����l���̌����ӎ������܂�A�l�b�g��ŁA���₷�������Ɋւ���@��������肷�邱�Ƃ��ł��A��Y�����������ł̖@��\�������܂łɐ������Ȃ�����͑����X���ɂ���B���̏ꍇ�A��Y������ɍX���̐����E�C���\�������\�肳��邱�ƂƂȂ�B �{�������͂��̂悤�Ȏ���Ɏ�����̎�����^������̂ƂȂ�B�T�i�R�̍s�������ڂ���� �B16 (��)14 LEX�^DB�y�����ԍ��z66015299�A���ŕs���R�����ٌ��y�ٌ��v�|�z�����Ŗ@22���́A�����A�②���͑��^�ɂ��擾�������Y�̉��z�́A���ʂ̒�߂�������̂������A���Y���Y�̎擾�̎��ɂ����鎞���ɂ��|�K�肵�Ă��邪�A�S�Ă̍��Y�̎����i�q�ϓI�������l���������z�j�͕K��������`�I�Ɋm�肳�����̂ł͂Ȃ����߁A�ېŎ�����A���Y�]���̈�ʓI������Y�]����{�ʒB�ɒ�߁A����ɒ�߂�ꂽ�]�����@�����I�ɓK�p���Č`���I�ȕ������т����Ƃɂ��A�������Ď����I�ȑd�ŕ��S�̕��������Q���邱�Ƃ����炩�ł���Ƃ��������ʂ̎������ꍇ�������A���Y�]����{�ʒB�ɒ�߂��]�����@�ɂ���č��Y��]�����邱�ƂƂ��Ă���B 15 LEX�^DB�y�����ԍ��z25449987�A�����n���ٔ��������A�Ȃ� 16 �O�f��4�A6�ŁA�M�҈ꕔ���B �Y�@��������i�O�������j�̍S���� �@�s�������́A�ʏ�̖��������Ƃ͈قȂ����Ȏ戵��K�v�Ƃ��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ����߁A�u�s�������i�ז@�v�����肳��Ă���A�s�������̍ٔ��́A�����i�ז@�̂ق��A�u�s�������i�ז@�v�̒�߂�Ƃ���ɏ]���čs���邱�ƂƂ���Ă���B�d�ői�ׂ��A�s�������̈��Ƃ��āA�d�Ŗ@�߂̒��ɕʒi�̒�߂�����ꍇ�̑��́A���R���̖@���̓K�p���邱�ƂɂȂ�B17 18 �@�s�������i�ז@33��1���́u�������ٌ͍��������������́A���̎����ɂ��āA�������ٌ͍��������s�������̑��̊W�s�������S������B�v�ƋK�肵�Ă���B19 �@���̂�����u�S���́v�͈���ōs�����ɔ����̎�|�ɏ]���ĐϋɓI�ɍs�����邱�Ƃ��`���Â���i�ϋɓI�`���s�ׂ̋`���Â��j�Ӗ������Ƃ����B�ȏォ�炷��ƁA�S���͂��y�Ԃ̂́A����������A�O�i�ɂ����ĐR�����f���ꂽ���R�Ɍ����邱�ƂɂȂ�B20 �@���́A�O�������ɍS�������Ƃ��Ă��A����́u�����Ŗ@32��1���̎��R�v�ɓ����炸�A�u���Œʑ��@23��1���̎��R�v�ɊY��������ɂ����Ȃ��Ǝ咣�����B����ɑ��Ė{�������ł́u���_�ƂȂ����X�̍��Y�̕]�����@�Ȃ������z�ɌW��F��E���f���тɂ�������b�Ƃ��ĎZ�肳���ېʼn��i�y�ё����Ŋz�ɌW��F��E���f�ɁC�����啶�������o�����̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�Ƃ��āC�s�������i�ז@33��1������̍S���͂������Ă���Ƃ������Ƃ��ł���v�Ɣ��������B�M�҂͂��̔����͍����I�Ȃ��̂ł���ƍl����B �@��������̍S���͂́A�u���̎����v�ɂ��ċy�Ԃ��̂ƋK�肳��Ă���B����āA�����͂��̍S���͂������Ă��邩��u��̑����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��X���̐������͓��@35��3���Ɋ�Â��X�������ɌW�鎖���ɂ��Ă��C����̔푊���l���瑊���ɂ��擾�������Y�ɌW�鑊���ł̉ېʼn��i�y�ё����Ŋz�Ɋւ��鎖���ł��邱�Ƃɕς�肪�Ȃ��ȏ�C�s�������i�ז@33��1���ɂ������̎����Ƃ��āC��L�̍S���͂��y�Ԃ��̂Ɖ�����̂������ł����āC�]�O�̍X�������ɂ��āC���_�ƂȂ�C���̕]�����@�Ȃ������z�������ɂ���ĕύX�����Ɏ������X�̍��Y�ɂ��ẮC�ېŒ��ɂ����āC�������ɂ�����]�����@�Ȃ������z����b�Ƃ��ĉېʼn��i���Z�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���v�ƌ��_�Â����B�{���́A�{���\�����瑊�����Ԃ��o�߂��Ă�����̂́A�����E����A�O�������̊m��Ȃǂ́A��������u����̑������Y�v�Ɋւ�����̂ł���u���̎����v���ʂɕ������邱�Ƃɂ͍��������Ȃ��B�{�������ōٔ����̎������u���̎����v�ɌW�锻�f�͍����I�ł���Ɣ��f����B21 �@�{���ł́A�O�������́A�����̕]���ɂ��Ĉ��̕]�����@�������I�ł���ƔF�肵�A����Ɋ�Â����i��F�肵�����炱���X����������������ƍl�����邽�߁A�O�������̗��R���A�����̕]�����@�Ƃ��ėގ��Ǝ�䏀������p����ׂ��Ƃ��Ă���_�ɂẮA�����啶�����߂ɕK�v�Ȏ����F��ł���ƍl�����A����͖T�_��Ԑڎ����ł͂Ȃ��B22�@��������̍S���͂��y�Ԕ͈͂́A�������R���̔��f�̂����A�u���̍S���͂́A�����啶�������o�����̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�ɂ킽����̂ł���v�B23 (��)17 ���Œʑ��@�i�s�������i�ז@�Ƃ̊W�j ��114���@���łɊւ���@���Ɋ�Â������Ɋւ���i�ׂɂ��ẮA���̐ߋy�ё��̍��łɊւ���@���ɕʒi�̒�߂�������̂������A�s�������i�ז@�i���a37�N�@����139���j���̑��̈�ʂ̍s�������i�ׂɊւ���@���̒�߂�Ƃ���ɂ��B 18 ���q�G�u�d�Ŗ@�v�i��23�Łj�A1071�ŁA�i2019�N�j�A�O�����A�M�҈ꕔ���B 19 �O�f��4�A4�ŁA�M�҈ꕔ���B �i��������i�O�������j�̍S���́j�@ �E�u���Y�K��́A��������̍S���͂ɂ��ċK�肵�����̂ƌ����Ă��܂����i����G�w�s���@�U�x�i��5�Ł@����Łj(�L��t)186�Łj�B�ʐ��I�����ł́A���̍S���͂ɂ��āA�����͂Ƃ͈قȂ����i�ׂɂ������������ɗ^����ꂽ����Ȍ��͂ł���A�s�����ɔ����̎�|�ɏ]���čs����������̖@��̋`�������������̂Ɖ�����Ă��܂��B�i����E�s���@�U�@188�Łj�B���̓_�A��������ɂ��s����������������A���Y��������@�ł��邱�Ƃ��m�肵�Ă��A����݂̂ł͌����̋~�ς��\���ɍs��ꂸ�A�s�����ɔ����̎�|�ɏ]�����s�����`���t���邱�Ƃɂ���Ă͂��߂ċ~�ς̎��������ۏႳ���ꍇ�����Ȃ��Ȃ����߁A�S���͂���ʂɖ@�肵���Ɛ�������Ă��܂��B�v�i�F�ꍎ��w�s���@�T���U�x�i��5�Łj�i�L��t�j�i280�Łj�B �E�O�f��5�A3�ŁA�M�҈ꕔ���B �i��������̍S���́j �u�s�i�@33��1���́u�������ٌ͍��������������́A���̎����ɂ��āA�������ٌ͍��������s�������̑��̊W�s�������S������B�v�Ƃ��Ď�������̍S���͂̒�߂������Ă���B���̍S���͂�������̂́A�����̎啶�Ɋ܂܂�锻�f�����߂ɕs���ȗ��R���̔��f�ł���A�@�I���f�݂̂Ȃ炸�����F��ɋy�Ԃ��A�����̌��_�ƒ��ڊW���Ȃ��T�_��v��������F�肷��ߒ��ɂ�����Ԑڎ����ɂ��Ă̔F��ɂ͍S���͂͐����Ȃ��Ƃ����(�F�ꍎ��w�s���@�T���U�x�i�L��t�A2006�N�j238�Łj�B �@�{�������́A�O�i�Łu���_�ƂȂ����X�̍��Y�̕]�����@�Ȃ������i�ɌW��F��E���f���тɂ�������b�Ƃ��ĎZ�肳���ېʼn��i�y�ё����Ŋz�ɌW��F��E���f�v�ɍS���͂������Ă���Ɣ������Ă���B�����ł̐Ŋz�̔���ɍS���͂������邩�ɂ��Ă͋^��Ƃ���c�_�����邪�A�O�i�ł̍X�������̎�������߂ɕs���̗��R���̔��f�ƂȂ����u�X�̍��Y�̕]�����@�ɌW��F��E���f�v�ɂ��čS���͂������邱�Ƃɂ͋^���̂Ȃ��Ƃ���ł��낤�B���̔F�肪��b�ƂȂ��Ă��Ȃ���A�O�i�ɂ����āA���z�X�������̂��������\���Ŋz���镔�������ׂĎ��������Ƃ͓������Ȃ����̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B�Ȃ��A���̂悤�ȕ]�����@�ɌW��F��E���f�́A�萫�I�Ȃ��̂ł����āA���z�I�ɉ��Ȃ��̂ł͂Ȃ�����A���z�X�������̂��������\���Ŋz���镔������������ߕK�v�Ȕ͈͂ł̂ݍS���͂�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͍l�����Ȃ��B�Ⴆ�Ηގ��Ǝ�䏀��������1��100�~��S1�{S2��������1��300�~�Ƃ����Ƃ��ɁA���z�X�������̂��������\���Ŋz���镔������������߂ɂ�1��200�~�ȉ��ł��邱�Ƃ�������Ώ\��������Ƃ����āA�ގ��Ǝ�䏀�������������]�����@�ł���Ƃ������f�̂���1��200�~�ȉ��ɑ������镔�������ɂ��čS���͂�������Ƃ������Ƃ͍l����ꂸ�A�ގ��Ǝ�䏀�������������]�����@�ł���Ƃ������f���̂ɍS���͂������邱�ƂɂȂ�B �@���̍S���͂ɂ��A�ېŒ��́A�O�i�����ŔF�肳��A�Њ��̑����ŕ]���ɂ��ėގ��Ǝ�䏀�����ƈقȂ���@����b�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�s�i�@33��1�����u���̎����v�ɂ��čS������ƋK�肷�邱�Ƃ���A�O�i�����̍S���͂́A��������Y�̏�Ԃł̍��Y�]���Ɍ��肳�����̂ł���A������̍X���̐�����X�������ɂ͊W���Ȃ��Ƃ��锽�_���l������B���̓_�ɂ��ẮA������ɂ�����i�K�ł̉ېŒ��ɂ����Y�]���ɂ��ẮA�u����̔푊���l���瑊���ɂ��擾�����������Y�ɌW�鑊���ł̉ېʼn��i�y�ё����Ŋz�Ɋւ��鎖���ł��邱�Ƃɕς�肪�Ȃ��v���Ƃ���A����ɑO�i�����̍S���͂��y�ԂƂ���{�������̔��f�͑Ó��Ȃ��̂ł���B����̔푊���l����̑����ɌW�铯��̑����Ŏ��Ăł���ɂ�������炸�A��������Y�i�K�ł̑������Y�̕]�����@���������������e������Ƃ����āA������̒i�K�ɂȂ�ΉېŒ��͖������Ă悢�Ƃ������Ƃɂ͓��R�Ȃ肦�Ȃ��B�v 20 ����T�́u����i�ׂɂ�����R���͈̔͂Ɣ����̍S���́|�R��������i�ׂ���̎����|�v�m�I���Y�@����w���� Vol.10�i2006�N�j�A148�Ł|149�ŁA�M�҈ꕔ���B 21 �O�f��4�A5�ŁA�M�҈ꕔ���B �i�u���̎����v�͈̔́j �E�u���́u���̎����v�̈Ӌ`�ɂ��ẮA���Y�i�����Ɍ���Ƃ�������������܂����A�S���͂������̍s�����̊������S��������̂ł��邱�Ƃ���A���Y�i�����Ɍ��炸�A���Y��������ɌW��s�������̑Ώۂ���@���W�Ƃ����Ӗ��ɉ����錩�����L�͂ł��i�w���� �s�������i�ז@�x�i��4�Łj�i�O�����j691�A692�ŁA������v�ҁw�����s�������i�ז@�x�i�L��t�j430�Łj�B ���̓_�ɂ��A��Y������̍X���ɂ����ẮA��Y�����O�ɂ����Ċm�肷�ׂ��Ŋz�ɌW��O���̑i�ׂƂ͓����������\�����Ȃ��Ƃ��A�����O��Ƃ��āA�{���́A�S���͂���u���̎����v�Y�����Ȃ��Ƃ��錩�����l�����܂��B �������Ȃ���A�{�������ł́A�u���̎����v�͈̔͂ɂ��āA�u��̑����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��X���̐������͓��@35��3���Ɋ�Â��X�������ɌW�鎖���ɂ��Ă��A����̔푊���l����̑����ɂ��擾�������Y�ɌW�鑊���ł̉ېʼn��i�y�ё����Ŋz�Ɋւ��鎖���ł��邱�Ƃɕς�肪�Ȃ��ȏ�A�s�������i�ז@33��1���ɂ����w���̎����x�Ƃ��āv��舵����|�������Ă���A��Y�����O����܂߂Ĉ�́u���̎����v�ƂƂ炦�Ă�����̂ƍl�����܂��B���̔��f�́u���̎����v�͈̔͂��A���Y�i�����Ɍ���̂ł͂Ȃ��A����̖@���W�܂ŋy�ԂƂ����L�̗L�͂Ȍ����Ɠ��l�̗�����̂��Ă���悤�Ɏv���܂��B ���̓_�ɂ��ẮA�O�q�̒ʐ��I�����̂悤�ɁA�s�������i�ז@33���̎�|���A����������������ꍇ�ɂ́A�s�����ɓ��Y�����̎�|�ɏ]�����s�����`���t���~�ς̎�������ۏႷ��_�ɂ���Ƒ�����̂ł���A���Ȃ��Ƃ��A���Y�i�����Ɍ���ƍl����̂͋�������悤�Ɏv���܂��B�ނ���A�����Ŗ@�́A��Y�����O����Y�����������̑����Ɋ�Â��ېłł��邩�炱���A55����32���̂悤�ȋK���݂��āA�ʂ̐\���ł͂Ȃ��A��Y������̉ېł��X�����Ƃ��Ĉ����Ă���̂ł���A���̂悤�ɓ��@����Y�����O�ƈ�Y�������̑����Ɋ�Â���̉ېŊW�Ƃ��đ������Ă��邱�Ƃ�����A�{�������ōٔ����̎������u���̎����v�ɌW�锻�f�͍����I�ł���ƍl�����܂��B�v 22 �O�f��4�A5�ŁA�M�҈ꕔ���B �i�S���͂��锻�f�͈̔́j �E�u�܂��A��������̍S���͂��y�Ԕ͈͂́A�������R���̔��f�̂����A�u�����啶�������o�����̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�ɂ킽��v���̂Ƃ���Ă��܂��i�Ŕ�����4�N4��28������^ 784-178�j�B�܂�A�啶�Ɋ܂܂�锻�f�����߂ɕs���ȗ��R���̔��f�ł���A�@�I���f�݂̂Ȃ炸�A�����F��܂ŋy�Ԃ��̂́A�����̌��_�ƒ��ڊW���Ȃ��T�_��v��������F�肷��ߒ��ɂ�����Ԑڎ����ɂ��Ă̔F��ɂ͍S���͂͐����Ȃ����̂Ƃ���Ă��܂��i�F��E�s���@�T���U�@280�ŁA�w���� �s�������i�ז@�x691�Łj�v �E�u�s�������i�@33��1���Ɋ�Â��S���͂��锻�f�͈̔͂ɂ��ẮA�ېŏ����̎�������ɂ����āA��@�̗��R�Ƃ��ċ��z��������Ă��A���̋��z���s�������S������킯�ł͂Ȃ��Ƃ���c�_������܂��B�i�씎���ҁw���ߍs���i�ז@�x(�L��t)310�Łj�B�������Ȃ���A�����R�ٔ���ɂ����ẮA�����ł̔F��Ɋւ���ېŏ����̎���i�ׂ́A�����z�̔F����@���̂��̂𑈂����Ƃ����Ƃ���̂ł��邱�Ƃ���A�����͍����I�ȔF����@���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩���m�肵�A�ېŒ�������ɍS������ď����z�����炽�߂ĎZ�肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�|����������́i�����n�ُ��a38�N10��30���s����������W�@14-10-1766�j��A�y�n�ېő䒠�̓o�^���i�Ɋւ���Œ莑�Y�]���R���ψ���̌���̑S��������������̗��R���ŁA�K���Ȏ������F�肳��Ă���Ƃ��́A���ψ���́A���̔����̔F��ɍS������|����������̂�����܂��i������������13�N12��26�����^1094-130�j�B�v �E�u�{�������́A�O�����������āu�]�O�̍X�������ɂ��āA���_�ƂȂ�A���̔F�肳�ꂽ�����̕]�����@�y�щ��z�������ɂ��ύX�����Ɏ������X�̍��Y�ɂ��ẮA�ېŒ��ɂ����āA�������ɂ�����]�����@�Ȃ������z����b�Ƃ��ĉېʼn��i���Z�肵�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��āA�O�������ɂ����ĔF�肳�ꂽ���Y�̕]�����@�y�щ��z�ɂ��Ă̍S���͂�F�߂Ă��܂��B���̂悤�Ȕ��f�́A�S���͈͂̔͂Ɋւ���O�L�����R����̔��f�Ƃ�����������̂ł���A���̊ϓ_����������̕]�����@�Ƃ��ėގ��Ǝ�䏀�@��p����ׂ��Ƃ���Ă���_�́A�S���͂�L����ƍl���邱�Ƃ͍����I�ƍl�����܂��B�v �E�u�s�������i�ז@33��1���̋K��ɂ��A�s���@�ւɑ��A�ގ��Ǝ�䏀������p���Ă̊����̕]���������ď������s���S���͂�������ƍl�����A�X���̐������\���Ɋ�Â������ɏ]���ĕ]�����邱�Ƃ��s�������i�ז@33��1���ɔ�����Ƃ��邱�Ƃɂ͍����I�ł���ƍl�����܂��B�v �E�uB�Њ����ɂ��ẮA�O�������ł�1��31,189�~�ƔF�肳��Ă��܂������A�X���̐����ɂ����Ă�19,132�~�ƔF�肳��Ă��܂��B���̓_�A�{�������́AA�Њ����̕]�����@�Ȃ������z�ɌW�������O��ɐ������v�Z����A19,132�~�Ƃ����ׂ����̂ł���A�O�������F��̉��z�́A�����Ɍv�Z�ԈႢ�A��L�����������ꍇ�Ɋւ��閯���i�ז@257���̍X������̑ΏۂƂȂ肤��Ǝw�E���Ă��܂��B���̊ϓ_����A�u�S���͂́A��L�̌v�Z�Ⴂ�ɂ����z�ɂ��Ăł͂Ȃ��A��L�̐����ɂ�����]�����@�Ɋ�Â����������v�Z�ɂ����z�ɂ��Đ�����v�Ɣ������āA�X���̐����ɂ����Ď����ꂽ1��19,132�~�𐳂������z�ƔF�肵�Ă��܂��B�v 23�@LEX�^DB�y�����ԍ��z27811171�A�ō��ٕ���4�N4��28�������B |
| �Z�@���� �@�d�Ŗ@����`�̋@�\�͑d�ł̔[�t�����߂��鍑�����A���̌o�ϐ����ɂ����āu�@�I���萫�v�Ɓu�\���\���v���m�ۂ��邱�Ƃł���B24�@�@�߂����m�ɉېł��邱�Ƃ��K�肵�Ă��Ȃ����̂ɂ��ẮA�ېł���Ȃ����Ƃ������ł���B�ߑ�Ȑŕ��S�����炩�ȏꍇ�ɂ́A����͐��������ׂ��ł���B�@�̒�߂����@�ȊO�ɂ��̐����������Ȃ��Ȃ�A�[�ŋ`���҂̗��v�����Q����ƔF�߂�����i�̎������ꍇ�ɂ́A�d�Ŗ@�̒�߂�ȊO�̐������@�̑��݂�F�߂�ׂ��ł���B25 �@���v���ɊY������@��\��������ɂ������Y�����m��ɂ��u�z��҂̐Ŋz�y���v�A�u���K�͑�n���̉ېʼn��i�̓���v�̍X���̐����͈��v���ɊY������ꍇ�ɔF�߂���B�{���ɂ����Ă͍��Œʑ��@�{�s�ߑ�6���1����5���̎��R�ɊY������u���Œʑ��@��23���2����3���̍X���̐����v�Ɓu�����Ŗ@32��1���̍X���̐����v�̊֘A�ɂ����ĉ��炩�̌���������K�v�����������̂Ǝv����B ���Œʑ��@71���i���ł̍X���A���蓙�̊��Ԑ����̓���j�̋K�肪����A���͈��v���̂��ƁA�X������5�N�̊��Ԑ�����ɂ����Ă��A���Y�ٌ�����������������6���ԂɌ���A�X�����蓙���ł��邱�ƂɂȂ��Ă���B �@�{�������ɂ����Ĕ��f�������ꂽ�u�����Ŗ@32��1���̍X���̐����v�Ɓu�s�������i�ז@33��1���̍S���́v�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�u�X���̐����ɂ����Ď咣�����鎖�R�v�������I�Ɋg�傷�錋�ʂɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����_�����ƂȂ肦��B���Œʑ��@23��1���i����24�N�����O�j�́A�����\���ɂ�����ېŕW����Ŋz�v�Z�Ɍ�肪�������ꍇ�ɂ��āA1�N�ԁi���s�@��5�N�ԁj�̊��Ԑ�����݂��čX���̐�����F�߂Ă���Ƃ���A�{�������́A�����I�ɂ��̗�O�I�Ȏ�舵�������e���邱�ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ̎w�E�����l������B26�@�������A���Œʑ��@114���ɁA���łɊւ���@���Ɋ�Â������Ɋւ���i�ׂɂ����ẮA���̏ꍇ�������u�s�������i�ז@�v���ɏ]���ƋK�肳��A���@33��1���ŁA�������ٌ͍��������������́A�u���̎����v�ɂ��āA�������ٌ͍��������s�������̑��̊W�s�������u�S������v�̂ł��邩��A�u�Y�@��������i�O�������j�̍S���́v�ɂ����Č����������R�Ɋ�Â��A�ٔ����́u�O�������v�m��Ȍ�́A�u�X���̐����̔r�����v27�@�z���āA���Y�S���͂��y�Ԃ��̂Ƃ��āA�����̎咣���e�ł� ��ʖ@�ł���s�������i�ז@�ɂ�荑�Œʑ��@�A�����Ŗ@�����C�����邱�Ƃɕs�����͂Ȃ��B�{�����́A�����Ŗ@32��1���y�ѓ��@35��3�����z�肵�Ă��Ȃ��������Ăɂ��āA�s�������i�ז@33��1���ɂ����u�S���́v���y�ԂƂ��������ɂ��A�ɉ������_��Ȗ@���߂������Ȃ��A�����I�Ȍ��_�����Ӌ`�[�������ł���B28 (��)25 �O�f��5�A3�ŁA�M�҈ꕔ���B �i�S���͂ƍX���̐����̔r�����j �E�u�{���̖�������Y�ɂ��Ă̑����ł̓����\�����番����̍X���̐����E�X�������Ɏ���ߒ������āA�@32��1���ł͂Ȃ��A���Œʑ��@�i�ȉ��A���ʖ@�j23���ɂ��X���̐����ɂ���ē����\���z�̉ېʼn��i�ƐŊz�����z������\���ɂ��A�@32��1���ɂ��X���̐����Ŏ咣�ł��鎖�R������Ȃ�����������K�v������B �@�������ɁA�����\���ɑ��đ��z�X�������Ȃ����O�ɍ��ʖ@23��1���i����24�N�����O�j�ɂ��X���̐����i�����O�F�@��[��������1�N�j�������đO�i�������F�肵���]�����@����b�Ɍ��z�X�����������߂邱�Ƃ͗��_�I�ɂ͉\�ł��邪�A�����̔���E��������Y�]���ʒB189�i����25�N�����O�j�̑��݂Ƃ���������A�����I�����Ȃ��������Ƃ͖�������ʂ��Ƃł���A�܂������I�����Ȃ��������Ƃ�������̖{���̌����ɉe����^���邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�����܂ł��Ȃ��d�Ŗ@����`�̂��ƂŁA�@�̒�߂�ȏ�̉ߑ�Ȑŕ��S�����߂邱�Ƃ͋����ꂸ�A�ߑ�Ȑŕ��S���������Ă���ꍇ�ɂ́A����͐�������Ȃ���Ȃ炢�B�������A�Ŏ��̈���I�ő��₩�Ȋm�ۂƂ����������ƐŖ��s���̑�ʐ��Ƃ��������̉��ŁA���̐����̕��@�Ɗ��Ԃɂ����̖@���x�I������������邱�Ƃɂ�������������B�������A�d�Ŗ@����`�̊ϓ_����́A�����������ł���A�����̐���͗�O�ł���B�ߑ�Ȑŕ��S�ɂ��đd�Ŗ@�̒�߂鐥�����@�ɂ��A�u�@�̒�߂����@�ȊO�ɂ��̐����������Ȃ��Ȃ�A�[�ŋ`���҂̗��v�����Q����ƔF�߂�����i�̎������v�ꍇ�ɂ́A�d�Ŗ@�̒�߂�ȊO�̐������@�̑��݂�F�߂�ׂ��Ƃ���Ŕ���39.10.22�i���W18��8��1762�Łj�ɂ́A�X���̐����̔r�����̍d���I�^�p�����߂�ƂƂ��ɁA�X���̐����̉^�p�ɂ��Ă������Ɛ����ɂ����錴���Ɨ�O�̋t�]�I�^�p�ƂȂ�悤�Ȏ��Ԃ̔��������߂��|��ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B�{���ɂ����č��ʖ@23��1���ɂ��X���̐����́A�@��[��������1�N�̊ԗ��_�I�ɂ͂ł����ɂ��Ă��A�ȏ�̂悤�Ȏ����A���ꂪX�̎咣���e�ł̖@32��1���̓K�p��r��������̂ł͂Ȃ��B�v 26 �O�f��4�A6�ŁA�M�҈ꕔ���B �i���̑��̖��_�j �E�u���̓_�ɂ��ẮA�{�������Ŏ������戵���́A�s���i�ׂɂ�鏈���̎���ɂ��~�ς������̂�����̂Ƃ��ׂ��s�������i�ז@33��1������߂�ꂽ���Ƃ̔��˓I�Ȍ��ʂł����āA�K�������s�����Ƃ͍l�����Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B�܂��A�Ŗ��i�ׂ��s���i�ׂ̈�ł���ȏ�A���ʖ@�Ƃ��Ă̑d�Ŗ@�K�ɁA���i�A�s�������i�ז@33��1���̌��͂�}�����ׂ��������Ȃ�����́A��ʖ@�ł���s�������i�ז@�ɂ��C�������ʂ������邱�Ƃ͕s�����ł͂Ȃ��ƍl�����܂��B�v 27 ���q�G�u�d�Ŗ@�v��23�ŁA932�ŁA946�ŁA�i2019�N�A�O�����j�M�҈ꕔ���B �E�u�ߑ�Ȑ\���������ꍇ�ɂ��ẮA�X���̐����̎葱��ʂ��Ė����������ׂ����ƂƂ���Ă���i�X���̐����̌����I�r�����j����A���낪�d��ł����āA�X���̐����ȊO�ɂ��̐����������Ȃ��Ȃ�Δ[�ŋ`���҂̗��v�����Q����ƔF�߂�����i�̎������ꍇ�������ẮA���@95���̓K�p�͔r�������Ɖ����ׂ��ł��낤�B�v �E�u�@���킴�킴�X���̐����̎葱����݂�����|�ɂ��݂�ƁA�\�����ߑ�ł���ꍇ�ɂ́A�����Ƃ��āA���̋~�ώ�i�ɂ�邱�Ƃ͋����ꂸ�A�X���̐����̎葱���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɖ����ׂ��ł��낤�B�i�����j������u�X���̐����̌����I�r�����v�ƌĂԂ��Ƃ��ł���B�v�i�M�Ғ��A�u�����I�r�����v�ɂ́A��O��F�߂�]�n�����邱�Ƃ��������Ă���B�j 28 ���{�_�j�u�����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��X���̐����y�ѓ��@35��3���Ɋ�Â��X�������̍ۂ̌v�Z�ɂ����Ċ�b�Ƃ��ׂ����z�����ƂȂ�������v�Ōo�ʐM�A�i2018.09�j�A156�ŁA�M�҈ꕔ���B
|
|||||||
|
�ʓY1 �������̂Ȃ��������̕]���i���Ђ̊����ۗL�����ɂ�銔���ۗL�����Ђ̔����j ���������ٔ�������25�N2��28�����������������Ƃ��A�����̏���Ђ̊������ۗ̕L���Ɋ�Â��A�]���ʒB189(2)�ɂ�������Ђ̊����ۗL�����ɂ�銔���ۗL�����Ђ̔������u25���ȏ�v����u50���ȏ�v�ɉ��������B�i�]���ʒB189�A�����ʒB�������j �P �]���̎戵�� �������̂Ȃ������̔��s��Ђ̒��ɂ́A�ގ��Ǝ�䏀�����ɂ�����W�{��Ђł������Ђɔ�ׂāA���Y�\�����������������ɕ�����Ђ�������B���̂悤�ȉ�Ђ̊����ɂ��ẮA��ʂ̕]����ЂɓK�p�����ގ��Ǝ�䏀�����ɂ��K���Ȋ����̎Z����s�����Ƃ���������̂ƍl�����邱�Ƃ���A�]���ʒB189((����̕]����Ђ̊���))(2)�ł́A�����ۗL�����i�]����Ђ̗L����e���Y�̉��z�̍��v�z�̂����ɐ�߂銔�����̉��z�̍��v�z�̊����j��25���ȏ�ł�����Ђ������ۗL�����ЂƂ��A���̊����̉��z��ގ��Ǝ�䏀�����ł͂Ȃ��A�����Ƃ��ď����Y���z�����ŕ]�����邱�ƂƂ��Ă����i�]���ʒB189�|3((�����ۗL�����Ђ̊����̕]��))�j�B �Q �ʒB�����̊T�v�� (1) ���������ٔ��������̊T�v ���������ٔ�������25�N2��28�������i�ȉ��u���ٔ����v�Ƃ����B�j�ɂ����āA���̊����ۗL�����Ђ̊����̉��z�������Ƃ��ď����Y���z�����ɂ��]�����邱�Ǝ��͍̂����I�ł���ƔF�߂�����̂́A����9�N�̓Ɛ�֎~�@�̉����ɔ����ĉ�Ђ̊����ۗL�Ɋւ�����A�����ۗL�����ЂɌW��]���ʒB�̒�߂��u���ꂽ����2�N�̕]���ʒB����������傫���ω����Ă��邱�ƂȂǂ���A�����ۗL����25���Ƃ������l�́A���͂⎑�Y�\�����������������ɕ��Ă���Ƃ܂ł͕]���ł��Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ��킴��Ȃ��Ɣ��f���ꂽ�B �i���j���ٔ����ɂ����ẮA�����ۗL�����ɉ����āA���̊�ƂƂ��Ă̋K�͂⎖�Ƃ̎��ԓ��𑍍��l�����Ĕ��f����Ƃ��Ă��邪�A����́A�����O�̕]���ʒB189(2)�ɂ�������Ђ̊����ۗL�����ɂ�銔���ۗL�����Ђ̔����i�ȉ��u���Ђ̔����v�Ƃ����B�j�i25���ȏ�j����������L���Ă������̂Ƃ͂����Ȃ����Ƃ�O��Ƃ��Ă��邽�߂ł���A�u���Ђ̔����v����������L������̂ł���A��ƂƂ��Ă̋K�͂⎖�Ƃ̎��ԓ��𑍍��l�����邱�Ƃ܂ł����߂���̂ł͂Ȃ��Ɖ������B (2) �ʒB�����̊T�v ���Y���ٔ������A�����̏���Ђ̊������ۗ̕L���A���Ȃ킿�A�L���،�������W�v��������Ђ̊����ۗL�������m�F�������ʁA�命���̏���Ђ̊����ۗL������50�������ł��邱�ƂȂǂ���A���Ђ̔������u25���ȏ�v����u50���ȏ�v�ɉ������邱�ƂƂ����B (3) �����ʒB�̉��� �{�����ɔ����A�����ʒB�́u��2�\ ����̕]����Ђ̔���̖����v�ɂ�����u2. �����ۗL�����Ёv�́u����v�f�v�A�u�����v�y�сu����v���ɂ��ĉ��������B (4) �K�p������ �{�����ɌW�������̕]���ʒB�i���Ђ̔����j�́A����25�N5��27���Ȍ�ɑ����A�②���͑��^�i�ȉ��u�������v�Ƃ����B�j�ɂ��擾�������Y��]������ꍇ�ɓK�p����ق��A�{�����������ɔ������̂ł���A�ߋ��̑����œ��ɂ��Ă��A�ʑ��@��23���2����3���̋K��Ɋ�Â��X���̐��������邱�Ƃ��ł���i���j���Ƃ܂��A����25�N5��27���Ȍ�ɑ����œ��̐\��������҂��A����25�N5��27���O�ɑ������ɂ��擾�������Y��]������ꍇ�ɂ��K�p���邱�Ƃ��ł���B �i���j�{�����͔����ɔ������̂ł��邽�߁A�ʑ��@�{�s�ߑ�6���1����5���ɋK�肷��X���̐����̎��R�ɊY�����A�ߋ��ɑk���ĉ�����̕]���ʒB��K�p���邱�Ƃɂ��A�ߋ��̑����œ��̐\���̓��e�Ɉٓ������������œ����[�߂����ɂȂ�ꍇ�ɂ́A�ʑ��@��23���2����3���̋K��Ɋ�Â��A�{������m�������̗�������2���ȓ��ɏ����̐Ŗ����ɍX���̐��������邱�Ƃ��ł���B �Ȃ��A�@��\���������������5�N�i���^�ł̏ꍇ��6�N�j���o�߂��Ă��鑊���œ��ɂ��ẮA�@�ߏ�A���z�ł��Ȃ��i�{�����ɌW�������̕]���ʒB��K�p�ł��Ȃ��j���Ƃɗ��ӂ���B �i���jhttps://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/130528/pdf/01.pdf�i2019/11/18�j �i�ʎ��j��ȊW�@�߂̒�߁@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@LEX/DB�y�����ԍ��z25550456 �����Œʑ��@�i����16�N�@����14���ɂ������O�̂��́j �i�X���̐����j ��23���@�[�Ő\�������o�����҂́A���̊e���̈�ɊY������ꍇ�ɂ́A���Y�\�����ɌW�鍑�ł̖@��\����������1�N�ȓ��Ɍ���㊟�A�Ŗ������ɑ��A���̐\�����ɌW��ېŕW�������͐Ŋz���i���Y�ېŕW�������͐Ŋz���Ɋւ����͑�26���i�čX���j�̋K��ɂ��X���i�ȉ����̏��ɂ����āu�X���v�Ƃ����B�j���������ꍇ�ɂ́A���Y�X����̉ېŕW�����͐Ŋz���j�ɂ��X�������ׂ��|�̐��������邱�Ƃ��ł���B ��@���Y�\�����ɋL�ڂ����ېŕW�����Ⴕ���͐Ŋz���̌v�Z�����łɊւ���@���ɏ]���Ă��Ȃ��������Ɩ��͓��Y�v�Z�Ɍ�肪���������Ƃɂ��A���Y�\�����̒�o�ɂ��[�t���ׂ��Ŋz�i���Y�Ŋz�Ɋւ��X�����������ꍇ�ɂ́A���Y�X����̐Ŋz�j���ߑ�ł���Ƃ��B �i㊟�@������A�@��\����������5�N�i��2���@�l�ł̏ꍇ��9�N�j�j ��E�O�i���j 2�`7�i���j�@�@�@ �������Ŗ@�i����16�N�@����84���ɂ������O�̂��́j �i�X���̐����̓����j ��32���@�����Ŗ��͑��^�łɂ��Đ\�������o�����Җ��͌�������҂́A���̊e���̂����ꂩ�ɊY�����鎖�R�ɂ�蓖�Y�\�����͌���ɌW��ېʼn��i�y�ё����Ŋz�܂��͑��^�Ŋz�i���Y�\�������o�����㖔�͓��Y���������C���\�����̒�o���͍X�����������ꍇ�ɂ́A���Y�C���\�����͍X���ɌW��ېʼn��i�y�ё����Ŋz���͑��^�Ŋz���ߑ�ƂȂ����Ƃ��́A���Y�e���ɋK�肷�鎖�R�����������Ƃ�m�������ɗ�������4���ȓ��Ɍ���A�[�Œn�̏����Ŗ������ɑ��A���̉ېʼn��i�y�ё����Ŋz���͑��^�Ŋz�ɂ����Œʑ��@��23���1���i�X���̐����j�̋K��ɂ��X���̐��������邱�Ƃ��ł���B ��@��55���̋K��ɂ�蕪������Ă��Ȃ����Y�ɂ��Ė��@�i��904����2�i��^���j�������B�j�̋K��ɂ�鑊�������͕�②�̊����ɏ]���ĉېʼn��i���v�Z����Ă����ꍇ�ɂ����āA���̌㓖�Y���Y�̕������s���A���������l���͕���҂����Y�����ɂ��擾�������Y�ɌW��ېʼn��i�����Y���������͕�②�̊����ɏ]���Čv�Z���ꂽ�ېʼn��i�ƈقȂ邱�ƂƂȂ������ƁB ��`���i���j �i�X���y�ь���̓����j ��35���i���j 2�i���j 3�@�Ŗ������́A��32���1�������5���܂ł̋K��ɂ��X���̐����Ɋ�Â��X���������ꍇ�ɂ����āA���Y�����������҂̔푊���l����̑����܂��͈②�ɍ��Y���擾�����ҁi���j�ɂ����̎��R������Ƃ��́A���Y���R�Ɋ�Â��A���̎҂ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�̍X�����͌��������B�i�����������j ��@���Y���̎҂���27���Ⴕ���͑�29���̋K��ɂ��\�����i�����̐\�����ɌW�������\�����y�яC���\�����j���o���A���͑����łɂ��Č�������҂ł���ꍇ�ɂ����āA���Y�\�����͌���ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�i���Y�\�����͌��肪��������C���\�����̒�o���͍X�����������ꍇ�ɂ́A���Y�C���\�����͍X���ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�j�����Y�����Ɋ�Â��X���̋N���ƂȂ�����������b�Ƃ��Čv�Z�����ꍇ�����邻�̎҂ɌW��ېʼnۉ��i���͑����Ŋz�ƈقȂ邱���ƂȂ邱�ƁB ��@���Y���̎҂��O���ɋK�肷��҈ȊO�̎҂ł���ꍇ�ɂ����āA���̎҂������ɋK�肷�鎖������b�Ƃ��Ă��̉ېʼnۉ��i�y�ё����Ŋz���v�Z���邱�Ƃɂ��A���̎҂��V���ɑ����ł�[�t���ׂ����ƂƂȂ邱�ƁB 4�i���j �i��������Y�ɑ���ېŁj ��55���@�����Ⴕ���͕�②�ɂ��擾�������Y�ɌW�鑊���łɂ��Đ\�������o����ꍇ���͓��Y���Y�ɌW�鑊���łɂ��čX���Ⴕ���͌��������ꍇ�ɂ����āA���Y�������͕�②�ɂ��擾�������Y�̑S�����͈ꕔ�����������l���͕���҂ɂ���Ă܂���������Ă��Ȃ��Ƃ��́A���̕�������Ă��Ȃ����Y�ɂ��ẮA�e���������l���͕���҂����@�i��904����2�i��^���j�������B�j�̋K��ɂ�鑊�������͕�②�̊����ɏ]���ē��Y���Y���擾�������̂Ƃ��Ă��̉ېʼn��i���v�Z������̂Ƃ���B�������A���̌�ɓ��Y���Y�̕���������A���Y���������l���͕���҂����Y�����ɂ��擾�������Y�ɌW��ېʼn��i�����Y���������͕�②�̊����ɏ]���Čv�Z���ꂽ�ېʼn��i�ƈقȂ邱�ƂƂȂ����ꍇ�ɂ����ẮA���Y�����ɂ��擾�������Y�ɌW��ېʼn��i����b�Ƃ��āA�[�ŋ`���҂ɂ����Đ\�������o���A�Ⴕ���͑�32���̍X���̐��������A���͐Ŗ������ɂ����čX���Ⴕ���͌�������邱�Ƃ�W���Ȃ��B ���s�������i�ז@ �i�R���i�ׁj ��3���@���̖@���ɂ����āu�R���i�ׁv�Ƃ́A�s�����̌����͂̍s�g�Ɋւ���s���̑i�ׂ������B 2�@���̖@���ɂ����āu�����̎�����̑i���v�Ƃ́A�s�����̏������̑������͂̍s�g�ɓ�����s�ׁi�����ɋK�肷��ٌ��A���肻�̑��̍s�ׂ������B�ȉ��P�Ɂu�����v�Ƃ����B�j�̎���������߂�i�ׂ������B 3�@�i�ȉ����j �i����������̌��́j ��33���@�������ٌ͍��������������́A���̎����ɂ��āA�������ٌ͍��������s�������̑��̊W�s�������S������B 2�`4�i���j �����Œʑ��@ �i�s�������i�ז@�Ƃ̊W�j ��114���@���łɊւ���@���Ɋ�Â������Ɋւ���i�ׂɂ��ẮA���̐ߋy�ё��̍��łɊւ���@���ɕʒi�̒�߂�������̂������A�s�������i�ז@�i���a37�N�@����139���j���̑��̈�ʂ̍s�������i�ׂɊւ���@���̒�߂�Ƃ���ɂ��B �����Œʑ��@ �i�X���̐����j ��23���@�P(��) 2�@�[�Ő\�������o�����Җ��͑�25���i����j�̋K��ɂ�錈��i�ȉ����̍��ɂ����āu����v�Ƃ����B�j�����҂́A���̊e���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�i�[�Ő\�������o�����҂ɂ��ẮA���Y�e���ɒ�߂���Ԃ̖�����������O���ɋK�肷����Ԃ̖����������ɓ�������ꍇ�Ɍ���B�j�ɂ́A�����̋K��ɂ�����炸�A���Y�e���ɒ�߂���Ԃɂ����āA���̊Y�����邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��ē����̋K��ɂ��X���̐����i�ȉ��u�X���̐����v�Ƃ����B�j�����邱�Ƃ��ł���B ��@�`�@��i���j �O�@���̑����Y���ł̖@��\��������ɐ������O�ɗނ��鐭�߂Œ�߂��ނȂ����R������Ƃ��@���Y���R�����������̗�������N�Z����2���ȓ� 3�@(��) �����Œʑ��@�{�s�� �i�X���̐����j ��6���@�@��23���2����3���i�X���̐����j�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂��ނȂ����R�́A���Ɍf���闝�R�Ƃ���B ��@�`�@�l�i���j �܁@���̐\���A�X�����͌���ɌW��ېŕW�������͐Ŋz���̌v�Z�̊�b�ƂȂ������ɌW�鍑�Œ��������������ʒB�Ɏ�����Ă���@�߂̉��߂��̑��̍��Œ������̖@�߂̉��߂��A�X�����͌���ɌW��R�������Ⴕ���͑i���ɂ��Ăٌ̍��Ⴕ���͔����ɔ��ĕύX����A�ύX��̉��߂����Œ������ɂ����\���ꂽ���Ƃɂ��A���Y�ېŕW�������͐Ŋz�����قȂ邱�ƂƂȂ�戵�����邱�ƂƂȂ����Ƃ�m�����ƁB 2�@�i�ȉ����j �������Ŗ@ �i�z�ɑ��鑊���Ŋz�̌y���j ��19����2 1�@�i���j 2�@�O���̑������͈②�ɌW���27���̋K��ɂ��\�����̒�o�����i�ȉ����̍��ɂ����āu�\�������v�Ƃ����B�j�܂łɁA���Y�������͈②�ɂ��擾�������Y�̑S�����͈ꕔ�����������l���͕���҂ɂ�Ă܂���������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ�����O���̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���̕�������Ă��Ȃ����Y�́A������2�����̉ېʼn��i�̌v�Z�̊�b�Ƃ������Y�Ɋ܂܂�Ȃ����̂Ƃ���B�������A���̕�������Ă��Ȃ����Y���\����������3�N�ȓ��i���Y���Ԃ��o�߂���܂ł̊Ԃɓ��Y���Y����������Ȃ������Ƃɂ��A���Y�������͈②�Ɋւ��i���̒�N�����ꂽ���Ƃ��̑��̐��߂Œ�߂��ނȂ��������ꍇ�ɂ����āA���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��[�Œn�̏����Ŗ������̏��F�����Ƃ��́A���Y���Y�̕������ł��邱�ƂƂȂ����Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̗�������4���ȓ��j�ɕ������ꂽ�ꍇ�ɂ́A���̕������ꂽ���Y�ɂ��ẮA���̌���łȂ��B �������Ŗ@�{�s�� �i�z��҂ɑ��鑊���Ŋz�̌y���̏ꍇ�̍��Y�����̓���j ��4����2�@�@��19����2��2���ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂��ނȂ��������ꍇ�́A���̊e���Ɍf����ꍇ�Ƃ��A�����ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂���́A�����̏ꍇ�̋敪�ɉ������Y�e���ɒ�߂���Ƃ���B ��@���Y�������͈②�ɌW��@��19����2��2���ɋK�肷��\�������i�ȉ������܂łɂ����āu�\�������v�Ƃ����B�j�̗�������3�N���o�߂�����ɂ����āA���Y�������͈②�Ɋւ���i���̒�N������Ă���ꍇ�i���Y�������͈②�Ɋւ���a�͒���̐\���Ă�����Ă���ꍇ�ɂ����āA�����̐\���Ă̎��ɑi���̒�N�����ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ����܂ށB�j �����̊m�薔�͑i���̎扺���̓����̑����Y�i�ׂ̊����̓� ��@���Y�������͈②�ɌW��\�������̗�������3�N���o�߂�����ɂ����āA���Y�������͈②�Ɋւ���a���A���▔�͐R���̐\���Ă�����Ă���ꍇ�i�O�����͑�l���Ɍf����ꍇ�ɊY�����邱�ƂƂȂ��ꍇ�������B�j�@�a���Ⴕ���͒���̐����A�R���̊m�薔�͂����̐\���Ă̎扺���̓����̑������̐\���ĂɌW�鎖���̏I���̓� �O�@���Y�������͈②�ɌW��\�������̗�������3�N���o�߂�����ɂ����āA���Y�������͈②�Ɋւ��A���@�i����29�N�@����89���j��907���3���i��Y�̕����̋��c���͐R�����j�Ⴕ���͑�908���i��Y�̕����̕��@�̎w��y�ш�Y�̕����̋֎~�j�̋K��ɂ���Y�̕������֎~����A���͓��@��915���1�����������i�����̏��F���͕��������ׂ����ԁj�̋K��ɂ�葊���̏��F�Ⴕ���͕����̊��Ԃ��L������Ă���ꍇ�i���Y�������͈②�Ɋւ��钲�▔�͐R���̐\���Ă�����Ă���ꍇ�ɂ����āA���Y�����̋֎~������|�̒��₪�������A���͓��Y�����̋֎~�Ⴕ���͓��Y���Ԃ̐L��������|�̐R���Ⴕ���͂���ɑ���ٔ����m�肵���Ƃ����܂ށB�j�@���Y�����̋֎~������Ă�����Ԗ��͓��Y�L��������Ă�����Ԃ��o�߂����� �l�@�O3���Ɍf����ꍇ�̂ق��A�������͈②�ɌW����Y�����Y�������͈②�ɌW��\�������̗�������3�N���o�߂�����܂łɕ�������Ȃ������Ƌy�ѓ��Y���Y�̕������x���������Ƃɂ��Ŗ������ɂ����Ă�ނȂ��������ƔF�߂�ꍇ�@���̎���̏��ł̓� ���d�œ��ʑ[�u�@ �i���K�͑�n���ɂ��Ă̑����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�̓���j ��69����4 1�`3�� 4�@��1���̋K��́A�����̑������͈②�ɌW�鑊���Ŗ@��27���̋K��ɂ��\�����̒�o�����i�ȉ����̍��ɂ����āu�\�������v�Ƃ����B�j�܂łɋ��������l���͕���҂ɂ�ĕ�������Ă��Ȃ�����Ώۑ�n���ɂ��ẮA�K�p���Ȃ��B�������A���̕�������Ă��Ȃ�����Ώۑ�n�����\����������3�N�ȓ��i���Y���Ԃ��o�߂���܂ł̊Ԃɓ��Y����Ώۑ�n������������Ȃ������Ƃɂ��A���Y�������͈②�Ɋւ��i���̒�N�����ꂽ���Ƃ��̑��̐��߂Œ�߂��ނȂ��������ꍇ�ɂ����āA���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��[�Œn�̏����Ŗ������̏��F�����Ƃ��́A���Y����Ώۑ�n���̕������ł��邱�ƂƂȂ����Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̗�������4���ȓ��j�ɕ������ꂽ�ꍇ�i���Y�������͈②�ɂ����Y���擾�����҂������1���̋K��̓K�p���Ă���ꍇ�������B�j�ɂ́A���̕������ꂽ���Y����Ώۑ�n���ɂ��ẮA���̌���łȂ��B �i�ȉ����j �i���j���߂͑����Ŗ@4����2���p |
|
�����i�ʕ\���j �i�ʕ\1�j �{���e�����̉��i��
�i�M�Ғ��j�E�����n�فA����24�N3��2�������u3�@�O���v��蔲�� �E�ԍ�1�@�������A�H�Ə��͏��a23�N�ɐݗ����ꂽ���������y�ы������ɂ��e��E�L���b�v�E��×p��E��O�i���̐�������є̔�����ړI�Ƃ��鎑�{���̊z��4��3200���~�̊�����Ђł���B�{�������̊J�n�̓��̒��O�����ł��镽��15�N5��31���̎��_�ɂ����铯�Ђ̑����Y���z�i���뉿�i�j��2120��7668��0565�~�A�]�ƈ�����5291���ł���A���Y���O�����ȑO1�N�Ԃł��镽��14�N6��1�����畽��15�N5��31���܂ł̎��ƔN�x�ɂ����铯�Ђ̎�����z��1882��0001��0637�~�ł����āA���Ђ͑��Ђɓ�����B �@ �E�ԍ�2�@B������Ђ́A���a41�N�ɐݗ����ꂽ�s���Y�̎擾�y�ъǗ�����ړI�Ƃ��鎑�{���̊z��9��9000���~�̊�����Ђł���B�{�������̊J�n�̓��̒��O�����ł��镽��15�N2��28���̎��_�ɂ����铯�Ђ̑����Y���z�i���뉿�i�j��98��2222��8821�~�A�]�ƈ�����5���ȉ��ł���A���Y���O�����ȑO1�N�Ԃł��镽��14�N3��1�����畽��15�N2��28���܂ł̎��ƔN�x�ɂ����铯�Ђ̎�����z��3��6845��2448�~�ł����āA���Ђ͒���Ђɓ�����B �E�{�������̊J�n�̎��_�i����16�N2��28���j�ɂ����āA�������A�H�Ə��́AB������Ђ̔��s�ϊ�������198�����̂���165��9240���i���s�ϊ���������83.8���j��L���Ă���A�܂��AB������Ђ́A�������A�H�Ə��̔��s�ϊ�������864�����̂���645��3400���i���s�ϊ��������̖�74.7���j��L���Ă������̂ł���B�Ȃ��A�������A�H�Ə��̊����i�ȉ��uA�Њ����v�Ƃ����B�j�y��B������Ђ̊����i�ȉ��uB�Њ����v�Ƃ����AA�Њ����ƕ����āu�{���e��Њ����v�Ƃ����B�j�́A��������������̂Ȃ������ɓ�����Ƃ���A�{�������̊J�n�̎��_�ɂ�����A�Њ����̉��z����Ђɂ��Ă̌����I�]�������ł���ގ��Ǝ�䏀������p���ĕ]������ƁA1��������4553�~�i��L�u�ʕ\1�v�ł�4653�~�j�ƂȂ�B �E�{���������Y�ɂ́AA�Њ���64��5400���y��B�Њ���17��8200�����܂܂�Ă���B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(�}) 29
(���j29 LEX�^DB�y�����ԍ��z26012243�i����20�N7��16���ٌ��j�A�i�}2�j�A�M�҈ꕔ�� �i�ʕ\2�j �ېł̌o���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�i�P�ʁF�~�j
�i��������A�ًc����ɂ��ꕔ�������ꂽ��̂��́j���������B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �y�{���O���z �i1�je�i�ȉ��u�{���푊���l�v�Ƃ����B�j������16�N2��28���Ɏ��S�������Ƃɂ��J�n�����{�������ɌW�鑊���l�ł��錴���i�{���푊���l�̒��j�j�A�{���푊���l�̒����A�O���C�l���y�ѓ�j�i�ȉ��u������v�Ƃ����B�j���тɖ{���푊���l�̓y�ь��i�ȉ��u��v�Ƃ����A�����A������A��̌v7�����āu�{�������l��v�Ƃ����B�j�́A�{�������ɌW�鑊���łɂ��āA���N12��27���A��Y�������������Ă��Ȃ����Ƃ��瑊���Ŗ@55���Ɋ�Â����@�̋K��ɂ�鑊�����̊����i�e7����1�j�ɏ]���č��Y���擾�������̂Ƃ��āA�]�����Ŗ������ɑ��\���i�{���\���j�������B ���̍ہA�����́A�ʕ\2�̏���1���L�ڂ̂Ƃ���A�ېʼn��i��22��6374��4000�~�A�[�t���ׂ��Ŋz��10��7095���~�Ƃ���\�������Ă���A�{���e�����̉��z�ɂ��Ă͕ʕ\�P�̖{���\�����L�ڂ̂Ƃ���Ƃ��Ă����B �i2�j�]�����Ŗ������́A����19�N2��13���A�����ɑ��A�{���e�����̈ꕔ�̉��z���ߏ��ł���Ƃ��āA�ʕ\2�̏���2���L�ڂ̂Ƃ���A�ېʼn��i��41��2068���~�A�[�t���ׂ��Ŋz��19��9989��9200�~�Ƃ���X�������������B �i3�j�����́A����19�N4��12���A��L�i2�j�̍X�������̎���������߂āA�������ŋǒ��ɑ���ًc�\���Ă������Ƃ���A���ǒ��́C���N6��27���A�ʕ\2�̏���4���L�ڂ̂Ƃ���A�ېʼn��i��41��2059��2000�~�A�[�t���ׂ��Ŋz��19��9985��4900�~�Ƃ��āA��L�i2�j�̍X�������̈ꕔ���������|�ً̈c����������B �i4�j�����́C����19�N8��1���A��L�i3�j�ً̈c����ɂ�肻�̈ꕔ���������ꂽ��̍X�������̎���������߂āA���ŕs���R�������ɑ���R�������������Ƃ���A�������́A����20�N7��16���A�����̐R�����������p����|�ٌ̍��������B�iLEX�^DB�y�����ԍ��z26012243�Q�Ɓj �i5�j�����́A����21�N1��21���A�퍐��ɁA�ʕ\2�̏���7���L�ڂ̂Ƃ���A��L�i4�j�̍X�������̎���������߂�i���𓌋��n���ٔ����ɒ�N�����i�O���i�ׁj�B�Ȃ��A�����̂ق��A��������A���ꂼ��\����Ɏ��X�������ɂ��A�ًc�\���ċy�ѐR���������o�āA����������߂�i�����N���A�O���i�ׂ̋��������ƂȂ��Ă����B �i6�j�]�����Ŗ������́A����23�N2��28���A�����ɑ��A�ʕ\2�̏���8���L�ڂ̂Ƃ���A�ېʼn��i��40��6089���~�A�[�t���ׂ��Ŋz��19��7000��9300�~�Ƃ��āA�O�L�i4�j�̍X�������̈ꕔ�����������z�X�������������B �i7�j�����n���ٔ����́A����24�N3��2���A��L�i6�j�̌��z�X�������ɂ�肻�̈ꕔ���������ꂽ��̍X�������i�O���X�������j�̂����A�{���\���ɌW��[�t���ׂ��Ŋz10��7095���~���镔�����������|�̔����i�O����1�R�����j�������n�����B �퍐�́A��L������s���Ƃ��čT�i�������A���������ٔ����́A����25�N2��28���A�퍐�̍T�i�����p����|�̔����i�O���T�i�R�����j�������n���A�����̔����i�O�������j�́A���N3��15���Ɋm�肵���B �O�������̔�������A�{���e�����̉��z�͕ʕ\1�̑O���������L�ڂ̂Ƃ���ƋL�ڂ���Ă����B �i8�j�O���i�ׂł́i�Ȃ��C��1�R�y�эT�i�R��ʂ��A�ȉ��̑��_�y�є��f�̗v�|�ɕύX�͂Ȃ��B�j�A�{���e�����̂����A�������A�H�Ə��i�ʕ\1�̔ԍ�1�j�y��B������Ёi���ԍ�2�j�̊e�����̕]�����@�Ȃ������z�������A�k1�l�������A�H�Ə��̊����ɂ��ẮA���������������̂Ȃ������ɓ�����A���Ђ����Y�]����{�ʒB�i�ȉ��u�]���ʒB�v�Ƃ����B�j�ɂ������ЂɊY�����邱�Ƃ�O��ɁA���Ђ������ۗL�����Ђł���Ƃ��ĕ]���ʒB����̏����Y���z�����ɂ���Ă��̉��z��]�����ׂ����ۂ����A�k2�lB������Ђ̊����ɂ��ẮA���������������̂Ȃ������ɓ�����A���Ђ������ۗL�����Ђł���A�����Y���z�����ɂ���Ă��̉��z��]�����ׂ��ł��邱�Ƃ�O��ɁA���Ђ��������A�H�Ə��̊�����ۗL���Ă��邱�Ƃ܂��āAB������Ђ̊����̉��z��������ƕ]�����ׂ���������ꂽ�B ���̓_�A�]���ʒB�ł́A�������̂Ȃ������̔��s��Ђ̒��ɂ́A�]���ʒB����̗ގ��Ǝ�䏀�����ɂ���Ċ����̉��z��]������ꍇ�ɂ�����W�{��Ђł������Ђɔ�ׂāA���Y�\�����������������ɕ�����Ђ�������Ƃ���A���̂悤�ȉ�Ђ̊����ɂ��ẮA��ʂ̕]����ЂɓK�p�����ގ��Ǝ�䏀�����ɂ��K���Ȋ����̕]�����s�����Ƃ���������̂ƍl�����邱�Ƃ���A���Ђɂ��ẮA�����ۗL�����i�]����Ђ̗L����e���Y�̉��z�̍��v�z�̂����ɐ�߂銔�����̉��z�̍��v�z�̊����j��25���ȏ�ł���]����Ђ������ۗL�����ЂƂ��C���̊����̉��z��ގ��Ǝ�䏀�����ł͂Ȃ��A�����Ƃ��ď����Y���z�����ŕ]�����邱�ƂƂ��Ă����B �O�������́A���̗��R���ŁA�����ۗL�����Ђ̊����̉��z�������Ƃ��ď����Y���z�����ɂ��]�����邱�Ǝ��͍̂����I�ł���ƔF�߂����ŁA����9�N�̓Ɛ�֎~�@�̉����ɔ����ĉ�Ђ̊����ۗL�Ɋւ���������ۗL�����ЂɌW��]���ʒB�̒�߂��u���ꂽ����2�N�̕]���ʒB����������傫���ω����Ă��邱�ƂȂǂ���A���Ђɂ��Ă̊����ۗL����25���ȏ�Ƃ�����́A���͂⎑�Y�\�����������������ɕ��Ă���Ƃ܂ł͕]���ł��Ȃ��Ȃ��Ă����Ɣ��f������ŁA�������A�H�Ə��̊����ۗL��������25.9�����ł��邱�Ɠ��܂�����ŁA���Ђ������ۗL�����ЂɊY�������A�����Y���z�����ɂ���Ă��̊����̉��z��]�����ׂ��ł͂Ȃ��A�ގ��Ǝ�䏀�����ɂ���ĕ]�����ׂ��ł���Ƃ̔��f�����A���Ђ̊����̉��z��ʕ\1�̑O���������L�ڂ̂Ƃ���ƔF�肵���B �܂��A�O�������ɌW�锻������AB������Ђ̊����ɂ��ẮA�ȏ�̐�����O��Ƃ�����ŁA�ʕ\1�̑O���������L�ڂ̂Ƃ���̊z�ƔF�肷��|���L�ڂ���Ă����B�������A���Ђ̊����̉��z�ɂ��ẮA�������A�H�Ə��ɌW���L�̐�����O��ɁA�]���ʒB����̏����Y���z�����ɂ���Đ������v�Z������A�ʕ\1�̖{���X���������L�ڂ̂Ƃ���̊z�ƔF�肳���ׂ����̂ł������B �����ŁC�{���e�����̂����C��L�e�ЈȊO�̕ʕ\1�ԍ�3�Ȃ���7�̊e�Ђ̊����ɂ��ẮA�O���X�������ɂ����鉿�z�ł���ʕ\1�̑O���X���������L�ڂ̂Ƃ���̊z�Ƃ��邱�Ƃɂ��ē����ҊԂɑ������Ȃ��A�O�������ɂ����Ă����̉��z�������Čv�Z������Ă���B ���̏�ŁA�O�������́A��L�̊e���z������b�Ƃ��āA�{�������ɌW�錴���̉ېʼn��i�i�擾���z�j��18��8786��1000�~�A�[�t���ׂ������Ŋz�� 8��7873��3800�~�ƔF�肵�A���Y�����Ŋz�͖{���\���ɌW����z�͈͓̔��ł��邩��A�O���X�������͖{���\���ɌW��[�t���ׂ��Ŋz���邻�̑S������@�Ȃ��̂ł���Ɣ��������B �i9�j���Œ������́A�O���������āA�����̏���Ђ̊������ۗ̕L���Ɋ�Â��A�]���ʒB�ɂ�������Ђ̊����ۗL�����ɂ�銔���ۗL�����Ђ̔�����25���ȏォ��50���ȏ�ɉ������A����25�N5���A��������\�����B �Ȃ��A�������܂ޖ{�������l��́A�X�������̖@��̐������Ԃ��o�߂��Ă������Ƃ���A��L�̕]���ʒB�����ɔ����X���̐��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B �i10�j�{���e�������܂ޖ{���푊���l�̈�Y�ɌW���Y�����\�������ɂ��āA����26�N1��16���A�����ƒ�ٔ����ɂ����Ĉ�Y��������i�ȉ��u�{������v�Ƃ����B�j�����������B �Ȃ��A�{������̐����ɂ��A�����͖{���e������7����6���擾����Ɏ������B �i11�j��́A����26�N2��21���A�]�����Ŗ������ɑ��A�{������̐����𗝗R�Ƃ��āC�����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��X���̐����������B �i12�j�����́A�@����26�N5��16���A�]�����Ŗ������ɑ��A�{������̐����𗝗R�Ƃ��āA�ʕ\2�̏���10���L�ڂ̂Ƃ���A�ېʼn��i��9��6080��5000�~�A�[�t���ׂ��Ŋz��4��4199��0400�~�Ƃ��āA�����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��X���̐����i�{���X�������j�������B ���̍ہA�����́A�{���e�����̉��z��ʕ\1�̖{���X���������L�ڂ̂Ƃ���AB������Ђ������e�Ђ̊e�����ɂ��ẮA�O�������ŔF�肳�ꂽ�z�Ɠ��z�AB������Ђ̊����̉��z�ɂ��ẮA�O�L�i8�j�̂Ƃ���O�������̐�����O��ɐ������v�Z�����ꍇ�̉��z�Ƃ��Ă����B �i13�j�]�����Ŗ������́C����26�N 6��20���A�O�L�i11�j�̍X���̐����Ɋ�Â��A��ɑ����z�X�������������B �i14�j�]�����Ŗ������́C����26�N11��12���A�����ɑ��A�{���X�������ɂ��A�{���e�����̉��z�ɌW�镔���ɂ��ẮA�{���\���ɂ����銔���̕]���̌��ɌW�鐥�������߂���̂ŁA�����Ŗ@32��1���Ɋ�Â��X���̐����ɂ���Ă͐��������Ȃ����ƂȂǂ𗝗R�Ƃ��āA�X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����i�{���ʒm�����j�������B �܂��A�]�����Ŗ������́A�O�L�i13�j�̓�ɑ��錸�z�X�������ɔ����A����26�N11��12���A�����ɑ��A�ʕ\2�̏���12���L�ڂ̂Ƃ���A �ېʼn��i��49��0410��9000�~�A�[�t���ׂ��Ŋz��23��2567��1800�~�Ƃ��āA�����Ŗ@35��3���Ɋ�Â����z�X�������i�{���X�������j�������B �{���X���������ɂ����āA�]�����Ŗ������́A�{���e�����̉��z��ʕ\1�̖{���X�����������L�ڂ̂Ƃ���A�{���\���ɂ����鉿�z�Ɠ��z�Ƃ��Ă����B �i15�j�����́A����26�N12��12���A�]�����Ŗ������ɑ��A�{���X����������s���Ƃ��Ĉًc�\���Ă������Ƃ���A���Ŗ������́A����27�N2��12���A�����ً̈c�\���Ă����p����|�ً̈c����������B ����ɁA�����́A����27�N3��13���A�{���X����������s���Ƃ��ĐR�������������Ƃ���A���ŕs���R�������́C����28�N2��12���A�����̐R�����������p����|�ٌ̍��������B �i16�j�����́A����28�N7��29���A�{���i�����N�����B �i�M�Ғ��j����9 �E�i�T�i�R�j�����^���������ٔ����A����25�N2��28���iLEX�^DB�y�����ԍ��z25500443�j�A�T�i�l�̍T�i�����p�B �E�i���R�j�����^�����n���ٔ����A����24�N3�� 2���iLEX�^DB�y�����ԍ��z25481239�j�A�X���y�щ��Z�ŕ��ی��������������A������̐����F�e�B �y���Ă̊T�v�z �����炪�A�{�������ɌW�鑊���ł̐\���������Ƃ���A�j�Ŗ���������e�����łɌW��X����������ъe�ߏ��\�����Z�ŕ��ی��菈���������Ƃɂ��A�{���e�X�������́A�{�������Ɋ|���鑊�����Y���̊������A�Ћy��B�Ђ̊e�����̉��z�̕]���z������Ă��ꂽ���̂ł���A�����Ŗ@22���Ɉᔽ������̂ł��铙�Ƃ��āA�{���e�����̎���������߂����Ăɂ����āA�{�������̊J�n����A�Ђɂ��ẮA���̊����̉��z�̕]���ɂ����ėގ��Ǝ�䏀������p����ׂ��O������������ۗL�����ЂɊY��������̂Ƃ͔F�߂�ɑ���Ȃ��ȂǂƂ��āA�{�������ɌW�錴����̔[�t���ׂ��Ŋz�́A��������{���\���ɂ����Č����炪�\�������[�t���ׂ��Ŋz�͈͓̔��ł��邩��A�{���e�X�������́A�{���\���ɌW��e�[�t���ׂ��Ŋz���邻�̑S������@�Ȃ��̂ł���A�܂��A�{���e���ی��菈�����܂��A���̑S������@�Ȃ��̂ł���Ƃ��āA������̐�����F�e��������B �E�ʓY1�Q�ƁA�u�������̂Ȃ������̕]���ɂ�������Ђ̊����ۗL�����ɂ�銔���ۗL�����Ђ̔��f��ɂ��āA���������ٔ�������25�N2��28���������A����Ђ̊����ۗ̕L���Ɋ�Â��u25���ȏ�v����u50���ȏ�v�ɉ��������B�v�A�i��25.5.25�ە]2�|20�j�B |
�X���E����y�ѕ��ی���̂ł�����Ԉꗗ�\
1�@�ړ]���i�Ő��ɌW��@�l�ł̍X���E���蓙�y�ё��^�ł̍X���E���蓙�ɂ��Ă�6�N�i�[66��4㉑�A��36�@�j�B �܂��A���O�]�o���̓���i��60��2�A60��3�j�̓K�p������ꍇ�̏����łɂ��čX�����蓙�ɂ��ẮA�����Ƃ���7�N�i��70�C�j�B����ɁA�X���̏��ˊ��ԏI����6���ȓ��ɂȂ��ꂽ�X���̐����ɌW��X�����͂��̍X���ɔ����čs������Z�ł̕��ی���ɂ��ẮA���Y�X���̐�����������������6�����o�߂�����܂łɂ��邱�Ƃ��ł���i��70�B�j�B 2�@�@�l�łɌW�鏃�������̋��z�ɂ��Ă̍X���́A����30�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ����Đ�������̂ɂ��Ă�10�N�A�����O�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ��Ă�9�N�Ƃ���Ă���B �i���Ԑ����̎�|�j �@���ł̖@���W�ɂ����āA���̍s�g�����錠�������܂ł��������ɔF�߂Ă��ẮA�[�Ŏ҂̖@�I���肪�����Ȃ�����łȂ��A���ł̉��I���s��������Ȃ�̂ŁA����ɑΏ����邽�߁A���ی��y�ђ������ȂǂɊւ�����Ԑ������݂����Ă���B���̓��e�́A��ʂ������I�ɍs���鍑�ł̕��ۋy�ђ��������I�����₩�ɏ�������K�v�����邱�Ƌy�э��̍��̏��Ŏ����������Ƃ���5�N�ł��邱�Ɓi��v�@30�j���l�����āA���ō��Ɋւ�����Ԑ����ی��ɂ��Ă͌���5�N�i��70�j�A�������ɂ��Ă�5�N�i��72�@�j�ƒ�߂��Ă���B�܂��A�[�Ŏ҂��[�߉߂����ŋ��ɂ��Ă̍��ɑ���ҕt���������A�������Ɠ��l��5�N�̊��Ԑ������߂Ă���i��74�@�j�B �ihttps://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/06.pdf�j�A88�ł���91�Łi2019.12.6�j�A�M�҈ꕔ���B �����Œʑ��@ �i���ł̍X���A���蓙�̊��Ԑ����j ��70���@���̊e���Ɍf����X�����蓙�́A���Y�e���ɒ�߂�������͓�����5�N�i��2���ɋK�肷��ېŕW���\�����̒�o��v���鍑�łœ��Y�\�����̒�o���������̂ɌW�镊�ی���i�[�t���ׂ��Ŋz��������������̂������B�j�ɂ��ẮA3�N�j���o�߂������Ȍ�ɂ����ẮA���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B ��@�X�����͌���@���̍X�����͌���ɌW�鍑�ł̖@��\�������i�ҕt�����\�����ɌW��X���ɂ��Ă͓��Y�\�������o�������Ƃ��A�ҕt�����\�����̒�o���Ȃ��ꍇ�ɂ��錈�薔�͂��̌����ɂ���X���ɂ��Ă͐��߂Œ�߂���Ƃ���B�j ��@�ېŕW���\�����̒�o��v���鍑�łɌW�镊�ی���@���Y�\�����̒�o���� �O�@�ېŕW���\�����̒�o��v���Ȃ����ۉېŕ����ɂ�鍑�łɌW�镊�ی���@���̔[�ŋ`���̐����̓� 2�@�@�l�łɌW�鏃�������̋��z�œ��Y�ېŊ��Ԃɂ����Đ��������̂������A�Ⴕ���͌���������X�����͓��Y���z��������̂Ƃ���X���́A�O���̋K��ɂ�����炸�A������1���ɒ�߂��������10�N���o�߂�����܂ŁA���邱�Ƃ��ł���B 3�@�O2���̋K��ɂ��X�������邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂȂ���O6���ȓ��ɂ��ꂽ�X���̐����ɌW��X�����͓��Y�X���ɔ��čs���邱�ƂƂȂ���Z�łɂ��Ă��镊�ی���́A�O2���̋K��ɂ�����炸�A���Y�X���̐���������������6�����o�߂�����܂ŁA���邱�Ƃ��ł���B 4�@���̊e���Ɍf����X�����蓙�́A��1�����͑O���̋K��ɂ�����炸�A��1���e���Ɍf����X�����蓙�̋敪�ɉ����A�����e���ɒ�߂�������͓�����7�N���o�߂�����܂ŁA���邱�Ƃ��ł���B ��@�U�肻�̑��s���̍s�ׂɂ�肻�̑S���Ⴕ���͈ꕔ�̐Ŋz��Ƃ�A���͂��̑S���Ⴕ���͈ꕔ�̐Ŋz�̊ҕt�������Łi���Y���łɌW����Z�ŋy�щߑӐł��܂ށB�j�ɂ��Ă̍X�����蓙 ��@�U�肻�̑��s���̍s�ׂɂ�蓖�Y�ېŊ��Ԃɂ����Đ��������������̋��z���ߑ�ɂ�����̂Ƃ���[�Ő\�������o���Ă����ꍇ�ɂ����铖�Y�\�����ɋL�ڂ��ꂽ���Y���������̋��z�i���Y���z�Ɋւ��X���������ꍇ�ɂ́A���Y�X����̋��z�j�ɂ��Ă̍X���i�O2���̋K��̓K�p����@�l�łɌW�鏃�������̋��z�ɌW����̂������B�j �O�@�����Ŗ@��60����2��1�������3���܂Łi���O�]�o������ꍇ�̏��n�������̓���j���͑�60����3��1�������3���܂Łi���^���ɂ��Z�҂Ɏ��Y���ړ]�����ꍇ�̏��n�������̓���j�̋K��̓K�p������ꍇ�i��117���2���i�[�ŊǗ��l�j�̋K��ɂ��[�ŊǗ��l�̓͏o�y�ѐŗ��m�@�i���a26�N�@����237���j��30���i�Ŗ��㗝�̌����̖����j�i���@��48����16�i�ŗ��m�̌����y�ы`�����Ɋւ���K��̏��p�j�ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j�̋K��ɂ�鏑�ʂ̒�o������ꍇ���̑��̐��߂Œ�߂�ꍇ�������B�j�̏����Łi���Y�����łɌW����Z�ł��܂ށB��73���3���i�����̒��f�y�ђ�~�j�ɂ����āu���O�]�o������̓K�p������ꍇ�̏����Łv�Ƃ����B�j�ɂ��Ă̍X�����蓙 �i���ł̍X���A���蓙�̊��Ԑ����̓���j ��71���@�X�����蓙�Ŏ��̊e���Ɍf������̂́A���Y�e���ɒ�߂���Ԃ̖�����������O���̋K��ɂ��X�����蓙�����邱�Ƃ��ł�����Ԃ̖����������ɓ�������ꍇ�ɂ́A�O���̋K��ɂ�����炸�A���Y�e���ɒ�߂���Ԃɂ����Ă��A���邱�Ƃ��ł���B ��@�X�����蓙�ɌW��s���\���ĎႵ���͑i���ɂ��Ăٌ̍��A����Ⴕ���͔����i�ȉ����̍��ɂ����āu�ٌ����v�Ƃ����B�j�ɂ�錴�����̈ٓ����͍X���̐����Ɋ�Â��X���ɔ��ĉېŕW�������͐Ŋz���Ɉٓ����ׂ����Łi���Y�ٌ������͍X���ɌW�鍑�ł̑�����Ŗڂɑ�������̂Ɍ���B�j�œ��Y�ٌ������͍X�������҂ɌW����̂ɂ��Ă̍X�����蓙�@���Y�ٌ������͍X��������������6���� ��@�i�ȉ����j ��Y����������̍X���̐����Ǝ�������̍S����
�����l�W�}�i����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���i���S�j���@��i�푊���l�j�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���\�\�\���\�\���\���\���\�\���\�\�\���\�\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �b�@�@�@�b�@�@�b�@ �@�b�@�@�b�@�@�@�b�@�@�b �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j�@�@�����E�O���E �l���E���j�@�@�����E�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����j�@�i������j�@�@�@�@�@�@�@�@�i������j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@↓�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@↓ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�������@�@6/7�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 1/7�@�@�@�@�@�@�@�@�@→�i�㏞�����j |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�����ٔ����� �Q�@���������ٔ����@�����R�O�N�i�s�R�j��S�U�� �@�@�����ōX����������������T�i�����A�����эT�i���� �@�@�ߘa�P�N�P�Q���S�������i�ꕔ����A�ꕔ�ύX�j�i�㍐�\���āj �@�@�k�d�w�^�c�a�@�Q�T�T�X�O�Q�O�Q �y���������z (1) �X���̐����ɑ��闝�R���Ȃ��|�̒ʒm�����Ƒ��z�X�������Ƃ��Ȃ��ꂽ�ꍇ�ɂ����āA���z�X�������̂ݎ���i�ׂ̑ΏۂƂ���Α����Ƃ������Ƃ͂ł����A�ʒm�����̎�������߂�i���̗��v������Ƃ�������B (2) �����Ŗ@�R�Q���P���Ɋ�Â��X���̐����ɂ����ẮA�����Ƃ��āA��Y�����ɂ���č��Y�̎擾���ω��������ƈȊO�̎��R���咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������B (3) �����Ŗ@�R�T���R���Ɋ�Â��X�������ɂ�����ېʼn��i�̎Z��̊�b�ƂȂ�X�̍��Y�̉��z�́A�܂��͐\���ɂ����鉿�z�Ƃ��A���̌�ɍX���������������ꍇ�ŁA�\���ɂ����鉿�z�̂������Y�X�������ɂ���ĕύX���ꂽ���z������Ƃ��ɂ́A���̉��z����b�ɂ��ׂ��ł���Ƃ�������B (4) �����Ŗ@�R�T���R���ɂ�葊���œ��L�̌㔭�I���R�i��Y�����j�𗝗R�ɂȂ��ꂽ���z�X���̎���i�ׂɂ����āA�㔭�I���R�������Ƃ��Ȃ��������@�̗��R�Ƃ��Ď咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������B (5) �\����̈�Y�����ɌW��X�������₻��ɑ��闝�R�Ȃ������̎�������ɂ����āA���Y�̎擾�̕ω��ȊO�̎��R���咣�ł���Ɖ�����͍̂���Ƃ�������B (6) �\���ɂ��m�肷��͔̂[�t���ׂ��Ŋz����ېŕW�����ł����āA��Y�̕]���͊m�肵�Ȃ��|�̔�T�i�l�i���R�����j�̎咣��r�˂�������B (7) �s�������i�ז@�R�R���P���ɂ����u���̎����v�Ƃ́A��������ɌW��s�������̑Ώۂł���@���W�Ɖ�����̂������Ƃ�������B (8) �{���X���������́A�O�������Ƃ̊W�ōs�������i�ז@�R�R���P���ɂ����u���̎����v�ɊY������Ƃ�������B (9) ��������̍S���́B (10)�O���X���������K�@���ǂ����ɓ������đO���i�ׂ̔����啶�Ŏ����ꂽ�����̕]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f�ɂ͍S���͂�������Ƃ�������B (11)�ېŒ��͑O�������Ŏ����ꂽ�X�̍��Y�̕]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f���тɂ�������b�Ƃ��ĎZ�肳���ېʼn��i�y�ё����Ŋz�̔��f�ɍS�������Ƃ�������B (12)�{���X�������̎���i�ׂɂ����āA���ɔ����ɂ���Ď������ꂽ�O���X���������s�������i�ז@33���P���ł����u���̎����v�ɊY�����邱�Ƃ�ے肵���Ȃ��Ƃ�������B (13)�ېŒ��ɂ͑O�������ɂ�����{���e�����̕]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f����ɖ{���e������������E����̌������`�����Ȃ��|�̍T�i�l�i���R�퍐�j�̎咣�́A��s�������i�ׂ̎��������m�ۂ��čs���̓K����}�낤�Ƃ���S���͂̎�|�ɔ�����Ƃ�������B (14)�O�i�����ɌW��]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f�ɍS���͂�������Ɖ����邱�Ƃ́A�P�Ƒ������Ɣ�r���Ă�������������|�̍T�i�l�i���R�퍐�j�̎咣��r�˂�������B �y�����v�|�z (1) �����łɂ��āA�����l�́A��Y�����I���O�ł����Ă�����̐\�������܂łɖ@�葊�����ɏ]���ĉېʼn��i���v�Z���Đ\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A�\����̈�Y�����ɂ��擾������Y�ɌW��ېʼn��i����L�v�Z�ɂ��ېʼn��i�ƈقȂ�ꍇ�A�����l�́A��Y�����̓��e�ɏ]���ĉېʼn��i�̌v�Z���������A����Ɋ�Â��čX���̐����i�����Ŗ@�R�Q���P���j�����邱�Ƃ��ł��A�����āA�X�����ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����i�{���ʒm�����j�́A�w�i��T�i�l�E���R�����j���[�Ŋz�̌��z�����߂�|�̍X���̐����ɑ��A�ېŒ��ɂ����āA�����҂w�ɌW��ېŕW�������͐Ŋz����S�̓I�Ɍ���������ŁA�X�������ɂ͗��R���Ȃ��i���z�X�������ׂ��łȂ��j�Ƃ��čX�����������ۂ���|�̔��f�����������̂ł���A���ɏ�L�������ɂ��Z�o�����Ŋz���\���z��葽�z�ɂȂ�Ƃ��Ă��A�ʒm���������ꂽ�����ł́A��L�̎Z�o�����z���[�t���ׂ��Ŋz�Ƃ��Ċm�肳�����̂ł͂Ȃ��A�[�t���ׂ��Ŋz�͐\���ɂ��m�肵���z�̂܂܂ł����āA�����A�ېŒ��́A�����P���Ȃ����T���ɂ��X���̐����Ɋ�Â��X���������ꍇ�A���Y�����ɌW�鑼�̑����l�ɂ����@�R�T���R���e���̎��R������Ƃ��́A�@��̊��ԓ��ɁA���̎҂ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�̍X����������Ƃ���A�{���X�������́A�ېŒ����A��ɑ��錸�z�X�������ɔ����A�����Ɋ�Â��čs�������̂ł���A�{���X�������i���z�X�������j�́A�ېŕW����Ŋz���z�ύX���鏈���ł����āA����ɂ��[�t���ׂ��Ŋz���m�肷����ʂ�L����Ƃ���A���̂悤�ɁA�ʒm�����Ƒ��z�X�������Ƃ́A���e����ʂ��قȂ���̂ł���A�X�����������ېŒ����[�t���ׂ��Ŋz�͐\���z��葽�z�ł���Ɣ��f�����ꍇ�A�ېŒ��͂��̊z��[�t���ׂ��Ŋz�Ƃ��Ċm�肷�鑝�z�X�������݂̂���悢�Ƃ���Ă���킯�ł͂Ȃ����A�ʒm��������̑��z�X�������ɋz�������|���߂��K����Ȃ��A���������āA���z�X�������̎���������߂�i���ɂ����āA�\���Ŋz���镔���̎�����݂̂Ȃ炸�\���Ŋz�ƍX���̐����ɌW��Ŋz�Ƃ̍��z�����ɂ��Ă�����������߂邱�Ƃ��ł���Ɖ����邱�Ƃ͍���ł���A������\�Ƃ���悤�ȋK����������炸�A�ȏ�ɂ��A�{���ɂ����ẮA�{���X�������̂ݎ���i�ׂ̑ΏۂƂ���Α����Ƃ������Ƃ͂ł����A�{���ʒm������������ɌW��i���ɂ��đi���̗��v���F�߂���Ƃ����ׂ��ł���B (2) �����Ŗ@�R�Q���P���Ɋ�Â��X���̐����ɂ����ẮA�����Ƃ��āA��Y�����ɂ���č��Y�̎擾���ω��������ƈȊO�̎��R�A���Ȃ킿�A�\�����͏]�O�̍X�������ɂ�����X�̍��Y�̉��z�̕]���Ɍ�肪���������Ɠ����咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ɖ�����A���̌��ʂƂ��āA�����Ɋ�Â��X���̐�����A�ېʼn��i�̎Z��̊�b�ƂȂ�X�̍��Y�̉��z�́A�܂��͐\���ɂ����鉿�z�Ƃ��A���̌�ɍX���������������ꍇ�ŁA�\���ɂ����鉿�z�̂������Y�X�������ɂ���ĕύX���ꂽ���z������Ƃ��ɂ́A���̉��z����b�ɂ��ׂ��ł���Ɖ������B (3) �����Ŗ@�R�T���R���́A�X���̓����Ƃ��āA�����łɂ��āA�ꕔ�̑����l����̓��@�R�Q���P���̍X���̐����Ɋ�Â����z�X�����������ꂽ�ꍇ�ɂ����āA���̗]�̑����l�ɂ��āA���Y���z�X�������́u����ƂȂ�����������b�Ƃ��Čv�Z�v�����ېʼn��i�y�ё����Ŋz���\�����͏]�O�̍X�������ɂ�������z�ƈقȂ邱�ƂƂȂ����Ƃ��ɂ́A���Y�����l�ɑ��čX������������|���߂Ă���A���̋K��U�肩�炷��A�����Ɋ�Â��X�������ɂ�����ېʼn��i�̎Z��̊�b�ƂȂ�X�̍��Y�̉��z���܂���L�Ɠ��l�ɁA�܂��͐\���ɂ����鉿�z�Ƃ��A���̌�ɍX���������������ꍇ�ŁA�\���ɂ����鉿�z�̂������Y�X�������ɂ���ĕύX���ꂽ���z������Ƃ��ɂ́A���̉��z����b�ɂ��ׂ��ł���A��������ƁA�{���̂悤�Ȑ\����ɍX�������̎���i�ׂɂ����Ĉ�Y�̕]�������߂�ꂽ�Ƃ�������́A�{���A�\�����ɓ��݂��Ă�������ł����āA�����ŌŗL�̌㔭�I����Ƃ͂������A�����Ŗ@�R�Q���e���ɂ���ɓ�����悤�Ȏ��R�͋K�肳��Ă��炸�A���������āA�{���e�����̕]�����@�y�щ��z�ɌW��O�������̔��f�𗝗R�ɁA�����P���Ɋ�Â��čX�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B (4) �{���X�������̍����ł��鑊���Ŗ@�R�T���R���������œ��L�̌㔭�I���R�i��Y�����j�𗝗R�ɑ��z�X�����邱�Ƃ�F�߂����̂Ɖ�����邩��A�����ɂ�鑝�z�X����������@�ł���Ǝ咣���Ă��̎���������߂�ꍇ���A���@�R�Q���P���Ɋ�Â��X�������ɂ��ĂƓ��l�A�����ɌŗL�̌㔭�I���R�������Ƃ��Ȃ��������@�̗��R�Ƃ��Ď咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ������B (5) ���{�̑����łɂ��ẮA��Y�擾�ېŕ�������{�Ƃ��A���p�����i�����ł̑��z��@�葊���l�̐��Ɩ@�葊�����ɂ���ĎZ�o���A�e�l�̎擾���Y�z�ɉ����ĉېł�������j�Ƃ���Ă��邪�A�����Ŗ@�R�Q���P���ɂ��X�������⓯�@�R�T���R���Ɋ�Â��X�������̎�������ɂ����āA�X�̍��Y�]���̌�蓙���咣�ł��邩�ǂ����́A�����łɂ��A�����Ȃ鎖�R�Ɋ�Â��čX���������F�߂��邩�ɌW����ł��邩��A��Y�擾�ېŕ�������{�ł��邱�Ƃ��炽�����ɏ�L�X���������������ɂ����Ĉ�Y�����ɂ����Y�̎擾�̕ω��ȊO�̎��R���咣�ł���Ɖ�����͍̂���ł���B (6) �w�i��T�i�l�E���R�����j�́A�\���ɂ��m�肷��͔̂[�t���ׂ��Ŋz����ېŕW�����ł����āA��Y�̕]���͊m�肵�Ȃ��|�咣���邪�A��Y�̕]�����ς��Δ[�t���ׂ��Ŋz�����ς�蓾��̂ł����āA�w�̏�L�咣�́A�\���ɂ��[�t���ׂ��Ŋz������U�m�肵�Ă��邱�Ƃ�ے肷��ɓ������A�̗p���邱�Ƃ͂ł����A����ɁA�w�́A���Y�̉��i�͑����J�n���̉��i�ɂ��ׂ��Ƃ̍l�����͂w�Ɉ�Y�̖{���̉��z�ɔ䂵�ĉߑ�ȕ��S���ۂ����ƂɂȂ�s�����ł���Ǝ咣���邪�A���S��������Ƃ��Ă����̓_�́A���Œʑ��@�y�ё����Ŗ@�ɂ����āA�X������������Ԃ⎖�R����߂��Ă��邱�Ƃɂ����̂ł���A��ނȂ��Ƃ����ׂ��ł���B (7) �s�������������������́A�u���̎����v�ɂ��āA�����҂���s�������̑��̊W�s�������S������Ƃ���i�s�������i�ז@�R�R���P���j�A�����ɂ��S���͂́A��������̎��������m�ۂ��邽�߂ɕt�^���ꂽ���̂ŁA�s�����ɁA�������ٌ͍�����@�Ƃ��������̔��f���e�d���A�u���̎����v�ɂ��Ĕ����̎�|�ɏ]���čs�����A����Ɩ������鏈����������ꍇ�ɂ́A�K�ȑ[�u���Ƃ�ׂ����Ƃ��`���t������͂ł��邩��A�i�ׂɂ�����i�ו��ɌW��ٔ����̔��f�ɂ��Đ���������͂ƈقȂ�A�啶�������o�����̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�i���R���̔��f�j�ɂ��Đ�������̂Ɖ�����i�ō��ُ��a�U�R�N�i�s�c�j��P�O�������S�N�S���Q�W����O���@�씻���E���W�S�U���S���Q�S�T�ŎQ�Ɓj�A���̂悤�ȍS���͂̋�̓I���e�Ɋӂ݂�A�����ɂ����u���̎����v�Ƃ́A��������ɌW��s�������̑Ώۂł���@���W�Ɖ�����̂������ł���B (8) �O�������i�ɌW��O���X�������j�Ɩ{���X���������́A��������{���푊���l�̈�Y�ɌW��w�i��T�i�l�E���R�����j���[�t���ׂ������ł̉ېłƂ�������̖@���W�ɌW����̂ł��邩��A�{���X���������́A�O�������Ƃ̊W�ōs�������i�ז@�R�R���P���ɂ����u���̎����v�ɊY������ƔF�߂�̂������ł���B (9) ��������̍S���͂́A�啶���̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�i���R���̔��f�j�ɂ��Đ�������̂ł���Ƃ���A����i�ׂ̑i�ו��́A�s�������̈�@��ʂł���Ɖ�����Ă��邩��A���Y����i�ׂ̑Ώۂł��鏈���ɂ��āA���̍����@�K����߂�e�K�@�v���ɂ��Ă̊Y�����A���Ȃ킿���Y�������e�K�@�v�����[�����Ă���Ƃ������Ƃ́A�i�ו��Ɋ܂܂�A�e�K�@�v���Y�����ɌW�锻�f���̂ɕK�v�ȗ��R���̎����F��y�і@�����f�ɂ��čS���͂�������Ƃ����ׂ��ł���B (10)�O���i�ׂ́A�w�i��T�i�l�E���R�����j�y�ё��̋��������l�̈ꕔ���A�O���X�������ɂ��A�O���i���Ăł���A��ȑ��_�́A�`�������ۗL�����ЂɊY�����邩�ǂ������тɂ����O��Ƃ���`�y�тa�̊e�����̎����̕]�������y�щ��z�ł����āA�O�������́A�`�͊����ۗL�����ЂɊY��������̂Ƃ������A�����I�]�������ł���ގ��Ǝ�䏀�����ɂ���ĕ]������̂������ł����āA��������Ƃ`�����͂P��������S�U�T�R�~�ł���A�a�����́A���̎��Y�ł���`�����̕]������L�̂Ƃ���ł��邱�Ƃ���ɏ���̌v�Z������ƁA�P��������R���P�P�W�X�~�ƂȂ�Ƃ��A�����̕]���i���̑��̊����ɂ��Ă͑O���X�������ɂ����鉿�z�Ɠ��z�j��p���Ċe�����l���[�t���ׂ������Ŋz���v�Z���A���ꂪ�{���\���ɂ����Đ\�������[�t���ׂ��Ŋz�͈͓̔��ł��邩��A�O���X�������́A�{���\���ɌW��e�[�t���ׂ��Ŋz���镔������@�ł���Ɣ��f�������̂ł���A���Ȃ킿�A�O�������́A��Y�ł���{���e�����̕]�����@�ɂ��Ĕ��f���A�����p���ĎZ�o���鉿�z�i�������A�a�����ɂ��Ă͍X������̑ΏۂƂȂ蓾�閾�炩�Ȉ�Z������B�j�Ɋ�Â��A�[�t���ׂ��Ŋz���Z�o���āA��L���f�������̂ł���A��������ƁA�O�������ɂ����āA�O���X���������K�@���ǂ����ɌW��啶�̔��f�́A�d�Ŗ@�K�ɏ]���ċq�ϓI�ɎZ�肵���ېʼn��i�y�ё����Ŋz�������炩�ɂ�邪�A����͓K�@�v���� �Y�����邩�ǂ����̖��ł���A���̓K�@�v���ɊY�����邩�ǂ����ɂ��Ă̌��_���̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�́A�܂��͐Ŋz�̌v�Z�̊�b�ƂȂ�����Y�̉��z�ɂ��Ă������̂ł���Ƃ���A���z�͕]�����@�ɉ����Čv�Z����ΐ��������l���Z�o�������̂ł���A�t�Ɍv�Z�����ΐ��������l���Z�o����Ȃ����Ƃ��炷��A�]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f�ɍS���͂�������Ɖ�����̂������ł���B (11)�O�������̔��f�̂����A���_�ƂȂ����X�̍��Y�̕]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f���тɂ�������b�Ƃ��ĎZ�肳���ېʼn��i�y�ё����Ŋz�ɌW�锻�f�ɍS���͂������A�ېŒ��ɂ����āA�O�������ɂ�����]�����@�Ȃ������z����b�Ƃ��ĉېʼn��i���Z�肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���A�����Ŗ@�R�Q���P���́u���������l���͕���҂����Y�����ɂ��擾�������Y�ɌW��ېʼn��i�v�ɂ��ẮA�X�̍��Y�̉��z�ɂ��A�\���ɂ����鉿�z�ɁA�]�O�̍X�������ɂ��ύX�ɉ����A�X�ɏ�L�̔����ɂ��ύX����������ł̉��z����b�Ƃ��āA���Y��Y������̉ېʼn��i���v�Z���ׂ��ł���A���̌��ʁA�����́u���Y���������͕�②�̊����ɏ]���Čv�Z���ꂽ�ېʼn��i�v�y�ѓ��𒌏����́u�X���ɌW��ېʼn��i�y�ё����Ŋz�v�ɑ��������L�̔����ɂ��ꕔ�������̏]�O�̍X�������ɌW��ېʼn��i�y�ё����Ŋz���ߑ�ƂȂ����Ƃ��́A�ېŒ��ɂ����āA���Y��Y������̉ېʼn��i�y�ё����Ŋz�Ɋ�Â��āA�����̍X���̐����ɑ��錸�z�X�����������ׂ����ƂɂȂ�Ɖ�����A�܂��A���@�R�T���R���Ɋ�Â��X�������ɂ����Ă��A���@�R�Q���P���̍X���̐����Ɋ�Â����z�X�������́u����ƂȂ�����������b�Ƃ��Čv�Z�v����ȏ�A���l�ɏ�L�e�ύX��̌X�̍��Y�̉��z����b�Ƃ��āu���̎҂ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz�v���v�Z���A���̌��ʂƂ��āA�u�X���ɌW��ېʼn��i���͑��� �Ŋz�v�A���Ȃ킿�A��L�̔����ɂ��ꕔ�������̏]�O�̍X�������ɌW��ېʼn��i���͑����Ŋz������ƈقȂ邱�ƂƂȂ�ꍇ�ɁA����ɉ������X���������\�ɂȂ���̂Ɖ������B (12)�x�i�T�i�l�E���R�퍐�j�́A�{���X���������������ꂽ�����Ƃ͈قȂ�Ǝ��̔��f�v�f���܂ޏꍇ�́A�s�������i�ז@�R�R���P���ł����u���̎����v�ɓ�����Ȃ��Ǝ咣���邪�A�{���X���������ɂ����đO�������̑Ώۂł���O���X�������ƈقȂ�Ǝ��̔��f�v�f�Ƃ����̂́A�ނ����Y���������������ƂƂ݂�ׂ��ł����āA�O���i�ׂł��{���ł������Ă���`�y�тa�̊e�����̕]�����@�Ȃ������z�ɂ��đO���X�������ƈقȂ�Ǝ��̔��f�v�f������킯�ł͂Ȃ�����A�x�̏�L�咣�͖{���X�����������O���i�ׂƂ̊W�Łu���̎����v�ɊY�����邱�Ƃ�ے肵������̂ł͂Ȃ��B (13)�x�i�T�i�l�E���R�퍐�j�́A�ېŒ��͑O�������ɂ�����{���e�����̕]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f����ɖ{���e������������E����̌������`�����Ȃ��|�咣���邪�A�ېł̓K���������邽�߁C�ېŒ��́A�\�����̒�o���������ꍇ�A���̐\�����ɋL�ڂ��ꂽ�ېŕW�������͐Ŋz���̌v�Z�����łɊւ���@���̋K��ɏ]���Ă��Ȃ������Ƃ��A���̑����Y�ېŕW�������͐Ŋz�������̒��������Ƃ���ƈقȂ�Ƃ��́A���̒����ɂ��A���Y�\�����ɌW��ېŕW�������͐Ŋz�����X�����邱�Ƃ��ł���̂ł����āi���Œʑ��@�Q�S���j�A�X���͑��z�X���݂̂Ȃ炸�A���z�X�������邱�Ƃ��ł��A�{���ł́A��Y�̕]�����@�Ȃ������z�͍��Œʑ��@�Q�R���̍X�����R�ɊY������Ƃ���A�O���������m�肵�����ɂ͂��̍X������̏��ˊ��ԁi���@�V�O���j���o�߂��Ă������A�O�������ɂ���ĉېŒ��̉ېŕW�����̎Z�o�ɂ�����]�����@�Ȃ������z�Ɍ�肪����|���f����A����Ώ�L���ˊ��ԓ��ɉېŒ��̍X���̌������K���ɍs�g����Ă��Ȃ��������Ƃ����炩�Ƃ�����ɂ�������炸�A�d�ō��E���̑����m��̊ϓ_���珜�ˊ��ԓ��𗝗R�Ɍ������`�����Ȃ��Ƃ��ď�L�O�������̔��f�̍S���͂ɏ]�����Ή������ނ̂́A��s�������i�ׂ̎��������m�ۂ��čs���̓K����}�낤�Ƃ���S���͂̎�|�ɔ�����B (14)�x�i�T�i�l�E���R�퍐�j�́A�O�i�����ɌW��]�����@�Ȃ������z�ɌW�锻�f�ɍS���͂�������Ɖ����邱�Ƃ́A�P�Ƒ������Ɣ�r���Ă�������������Ǝ咣���邪�A���������P�Ƒ����́A�\���O�ɐ\��������҂��擾�����Y���m�肵�A���̌����ϓ����\�肳��Ȃ��_�Ŗ{���̂悤�ɐ\����Ɉ�Y���������ꂽ�ꍇ�Ə�傫���قɂ��A�܂��A�{���̂悤�Ɉ�Y�����O�ɐ\���������ꍇ�́A�\���̍ۂ͑S�Ă̈�Y�ɂ��Ė@�葊�����ɉ����Ď擾�����Ƃ݂Ȃ���ĐŊz���v�Z����邩��A�ꕔ�̈�Y�̕]���Ɍ�肪����Ƃ��Ă��A����ɂ�苤�������l�Ԃɕs�����͐����Ȃ��̂ɑ��A��Y������̍X���̐�����X�������ɂ����ẮA�\�����̍ی���č��z�ɕ]�����ꂽ��Y�𑽂��擾���������l���������]������Ă����ꍇ�ɔ�ׂĉߑ�ȕ��S���A���̑����l�͂����Ƃ��Ƃ����s��������������̂ł���A�O�������̍S���͂��m�肷�邱�Ƃɂ���Ă��������K�v���͑傫���A���������āA�P�Ƒ����̏ꍇ��\�������܂łɈ�Y�������I�����ꍇ�Ɣ�r���Č�����������Ƃ̂x�̎咣�͍̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B |
|
���ō��ٔ����� �R�@�ō��ٔ����@�ߘa�Q�N�i�s�q�j��P�O�R�� �@�@�����ōX������������������� �@�@�ߘa�R�N�U���Q�S�������i�������ύX�E�������p�j �@�@�k�d�w�^�c�a�@�Q�T�T�V�P�T�X�W �y�����v�|�z �@�{���X�����������ꂽ���_�ō��Œʑ��@�i�����Q�R�N�@����P�P�S���ɂ������O�̂��́j����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂��Ă����{���ɂ����ẮC�����s�����́C�{���X������������ɍۂ��C�O�������Ɏ����ꂽ�{���e�����̉��z��]�����@��p���ĐŊz���̌v�Z�����ׂ����̂Ƃ͂������C�{���\���ɂ�����{���e�����̉��z����b�Ƃ��ĉېʼn��i�y�ё����Ŋz���v�Z���邱�ƂƂȂ邩��C�{���X�������͓K�@�ł���C�w�i��㍐�l�E���R�����j�́C�����ł̑��z�̌v�Z�ɂ����Ă͖{���\���ɂ�����{���e�����̉��z��p����Ƃ��Ă��C�e�����l�̎擾�����̌v�Z�ɓ������Ă͑O�������Ɏ����ꂽ���z��p����ׂ��ł���Ƃ��咣���邪�C�����Ŗ@��C�e�����l�̎擾�����̌v�Z�́C�����ł̑��z�̌v�Z�Ɠ��l�ɉېʼn��i�Ɋ�Â��Ă�����̂Ƃ���Ă��邱�Ɠ����炷��C��L�̎咣�͗��R���Ȃ��B 45��
�y���������z(1) �����Ŗ@�R�Q���P���y�тR�T���R���P���̋K��̎�|�B (2) �����Ŗ@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɂ����ẮC��U�m�肵�Ă��������Ŋz�̎Z���b�ƂȂ����X�̍��Y�̉��z�ɌW��]���̌��Y�����̗��R�Ƃ��邱�Ƃ��ł��邩�i���Ɂj�B (3) �������������������m�肵���ꍇ�ɂ́C���̍S���́i�s�������i�ז@�R�R���P���j�ɂ���čs�������@�ߏ�̍����������s�����`���t��������̂ł͂Ȃ�����C���̋`���̓��e�́C���Y�s������������s���@�ߏ�̌�����������̂Ɍ�����Ƃ�������B (4) �ېŒ��́C���Œʑ��@����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂�����ɑ����Ŗ@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɑ��鏈���y�ѓ��@�R�T���R���P���̋K��ɂ��X��������ꍇ�A���Ɋm�肵�������Ŏ����ꂽ�X�̍��Y�̉��z��]�����@��p���ĐŊz�����v�Z���ׂ��`����Ȃ��Ƃ�������B (5) �{���X������������ɍۂ��C�O�������Ɏ����ꂽ�{���e�����̉��z��]�����@��p���ĐŊz���̌v�Z�����ׂ����̂Ƃ͂����Ȃ��Ƃ�������B (6) �����Ŗ@�R�T���R���P���ɂ�鑝�z�X���́A���@�R�Q���P���Ɋ�Â��X���̐����ɑ���X�����ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����̓��e���ۂ���Ƃ��Ēʒm�����̎���������߂�i���͕s�K�@�Ƃ�������B �y�����v�|�z (1) �����Ŗ@�R�Q���P���y�тR�T���R���P���́C���@�T�T���Ɋ�Â��\���̌�Ɉ�Y�������s���Ċe�����l�̎擾���Y���ϓ������Ƃ��������œ��L�̌㔭�I���R���������ꍇ�ɂ����āC�X���̐����y�эX���ɂ��ċK�肷�鍑�Œʑ��@�Q�R���P���y�тQ�S���̓����Ƃ��āC���@����̊��Ԑ����ɂ�����炸�C��Y������̈��̊��ԓ��Ɍ���C��L�㔭�I���R�ɂ���L�\���ɌW�鑊���Ŋz�����ߑ�ƂȂ����Ƃ��čX���̐��������邱�Ƌy�ѓ��Y�����Ɋ�Â��X�������ꂽ�ꍇ�ɂ͑��̑����l�̑����Ŋz���ɐ�������L�㔭�I���R�ɂ��ϓ��̌��x�ōX�������邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ������̂ł���A���̎�|�́C�����Ŗ@�T�T���Ɋ�Â��\�����ɂ��@�葊�������ɏ]���Čv�Z�����U�m�肵�Ă��������Ŋz�ɂ��āC���ۂɍs��ꂽ��Y�����̌��ʂɏ]���čĒ������邽�߂̓��ʂ̎葱��݂��C�����đ����l�Ԃ̐ŕ��S�̌�����}�邱�Ƃɂ����Ɖ������B (2) �����Ŗ@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɂ����ẮC�㔭�I���R�ȊO�̎��R���咣���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��邩��C��U�m�肵�Ă��������Ŋz�̎Z���b�ƂȂ����X�̍��Y�̉��z�ɌW��]���̌��Y�����̗��R�Ƃ��邱�Ƃ͂ł����C�ېŒ����C���Œʑ��@����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂�����́C���Y�����ɑ��鏈���ɂ����ď�L�̕]���̌������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł����A�܂��C�ېŒ��́C�����Ŗ@�R�T���R���P���̋K��ɂ��X���ɂ����Ă��C���l�ɁC��L�̕]���̌������邱�Ƃ͂ł����C��L�̈�U�m�肵�Ă��������Ŋz�̎Z���b�ƂȂ������z��p���邱�ƂɂȂ����̂Ɖ�����̂������ł���B (3) �������������������m�肵���ꍇ�ɂ́C���̍S���́i�s�������i�ז@�R�R���P���j�ɂ��C�����������s�������́C���̎����ɂ����Y�����ɂ�����啶�������o�����̂ɕK�v�Ȏ����F��y�і@�����f�ɏ]���čs�����ׂ��`�������ƂƂȂ邪�C��L�S���͂ɂ���Ă��C�s�������@�ߏ�̍����������s�����`���t��������̂ł͂Ȃ�����C���̋`���̓��e�́C���Y�s������������s���@�ߏ�̌�����������̂Ɍ�������̂Ɖ������B (4) �����Ŗ@�T�T���Ɋ�Â��\���̌�ɂ��ꂽ���z�X�������̎���i�ׂɂ����āC�X�̍��Y�ɂ���L�\���Ƃ͈قȂ鉿�z��F�肵����ŁC���̌��ʎZ�o�����Ŋz����L�\���ɌW��Ŋz�������Ƃ̗��R�ɂ�蓖�Y�����̂�����L�\���ɌW��Ŋz���镔�����������|�̔������m�肵���ꍇ�ɂ́C���Y�����ɂ�葝�z�X�������̈ꕔ����������ꂽ��̐Ŋz����L�\���ɂ�����X�̍��Y�̉��z����b�Ƃ��ĎZ�肳�ꂽ���̂ł���ȏ�C�ېŒ��́C���Œʑ��@����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂�����ɂ����ẮC���Y�����Ɏ����ꂽ���z��]�����@��p���đ����Ŗ@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɑ��鏈���y�ѓ��@�R�T���R���P���̋K��ɂ��X��������@�ߏ�̌�����L���Ă��Ȃ����̂Ƃ��킴����A��������ƁC��L�̏ꍇ�ɂ����ẮC���Y�����̌X�̍��Y�̉��z��]�����@�Ɋւ��锻�f�����ɂ��čS���͂������邩�ۂ���_����܂ł��Ȃ��C�ېŒ��́C���Œʑ��@����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂�����ɑ����Ŗ@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɑ��鏈���y�ѓ��@�R�T���R���P���̋K��ɂ��X��������ɍۂ��A���Y�����̍S���͂ɂ���ē��Y�����Ɏ����ꂽ�X�̍��Y�̉��z��]�����@��p���ĐŊz�����v�Z���ׂ��`�������Ƃ͂Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B (5) �{���X�����������ꂽ���_�ō��Œʑ��@�i�����Q�R�N�@����P�P�S���ɂ������O�̂��́j����̍X���̏��ˊ��Ԃ��o�߂��Ă����{���ɂ����ẮC�]�����Ŗ������́C�{���X������������ɍۂ��C�O�������Ɏ����ꂽ�{���e�����̉��z��]�����@��p���ĐŊz���̌v�Z�����ׂ����̂Ƃ͂������C�{���\���ɂ�����{���e�����̉��z����b�Ƃ��ĉېʼn��i�y�ё����Ŋz���v�Z���邱�ƂƂȂ邩��C�{���X�������͓K�@�ł���A�w�i��㍐�l�E���R�����j�́C�����ł̑��z�̌v�Z�ɂ����Ă͖{���\���ɂ�����{���e�����̉��z��p����Ƃ��Ă��C�e�����l�̎擾�����̌v�Z�ɓ������Ă͑O�������Ɏ����ꂽ���z��p����ׂ��ł���Ƃ��咣���邪�C�����Ŗ@��C�e�����l�̎擾�����̌v�Z�́C�����ł̑��z�̌v�Z�Ɠ��l�ɉېʼn��i�Ɋ�Â��Ă�����̂Ƃ���Ă��邱�Ɠ����炷��C��L�̎咣�͗��R���Ȃ��B (6) �����Ŗ@�T�T���Ɋ�Â��\���̌�Ɉ�Y�������s��ꂽ�ꍇ�ɂ��������̑����l�ɂ�铯�@�R�Q���P���̋K��ɂ��X���̐����ɑ���X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����Ɠ��Y�����l�ɑ��铯�@�R�T���R���P���̋K��ɂ�鑝�z�X���́C����������Y��Y�����ɂ��e�����l�̎擾���Y�̕ϓ��Ƃ��������œ��L�̌㔭�I���R����b�Ƃ��Ă��ꂽ���ꑊ���l�ɑ��鏈���ł���C��L���z�X���́C��U�m�肵�Ă����Ŋz�Y��Y�������s��ꂽ���Ƃ𗝗R�ɑ��z�����Ċm�肷�鏈���ł��邩��C���Y��Y�����ɔ����Ŋz�����z���ׂ����R�͂Ȃ��Ƃ�����L�ʒm�����̓��e�������I�ɕ�ۂ�����̂Ƃ������Ƃ��ł��A�����āC��L�X���̐���������Ă��邽�߁C���Y�����l�́C��L���z�X���̎���i�ׂɂ����āC��L�X���̐����ɌW��Ŋz���镔���̎���������߂邱�Ƃ��\�ł���Ɖ�����A |
|
��350-1314 ��ʌ� ���R�s �����u 167-2�@������� �����p�^�R���^�Η��ŗ��m�������@☎04(2946)7704
|