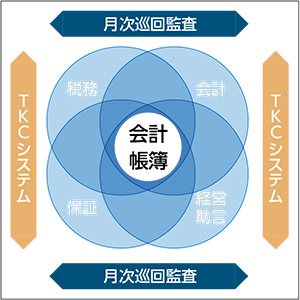�l���Ə��p���^����
���Œ��z�[���y�[�W���
 ���Y�ېŏ�����Y�ېʼnۏ��b��2���b�ߘa�Q�N�P��14���b���Œ��b���Y�ېʼn� 💛�l�̎��Ɨp���Y�ɂ��Ă̑��^�ŁE�����ł̔[�ŗP�\�y�іƏ��Ɋւ��鎿�^��������ɂ��� �ߘa���N�x�Ő������ɂ����đn�݂��ꂽ�l�̎��Ɨp���Y�ɂ��Ă̑��^�ŁE�����ł̔[�ŗP�\�Ɋւ��鎿�^������������܂Ƃ߂��̂ŁA�����̎Q�l�Ƃ��đ��t����B�Ȃ��A���^��������́A�ߘa�Q�N�P���P�����݂̖@�߂Ɋ�Â����̂ł���B �s���x�̊T�v���t �i��P�j�l�̎��Ɨp���Y�ɂ��Ă̑��^�ŁE�����ł̔[�ŗP�\�y�іƏ��̊T�v
�i���j
(��) �P �[�u�@�� 25 ���̂Q��R���̋K��ɂ����́i���K�̕�L�̌����ɂ����́B�Ȃ��A��̓I�ɂ͖� 16 ���Q�ƁB�j�Ɍ���B�ȉ������B �Q ���莖�Ɨp���Y�̊T�v�ɂ��ẮA��U���Q�ƁB �R ��㎖�Ǝ҂Ɛ��v����ɂ���z��҂��̑��̐e���y�ё[�u�@�ߑ� 40 ���̂V�̂W��S�����͑� 40 ���̂V�� 10 ��T���ɒ�߂�ҁi�ȉ��u���v��e�����v�Ƃ����B�j����̓��莖�Ɨp���Y�̑��^���͑����Ⴕ���͈②�ɂ��ẮA��L�̊��ԓ��ŁA��㎖�Ǝ҂���̑��^���͑����Ⴕ���͈②�̓�����P�N���o�߂�����܂łɂ��ꂽ���̂Ɍ���B �S �u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�ҁi�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W��P���ɋK�肷�鑡�^�҂������B�ȉ������B�j�����S�����ꍇ�ɂ́A���^�ł͖Ə������ƂƂ��ɁA�[�ŗP�\�̓K�p���Ă��鎑�Y�́A���^���̉��z�ɂ��҂��������͈②�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ��ꑊ���ł��ۂ���邪�i�[�u�@ 70 �̂U�̂X�j�A���̗v���������Ƃ��́A���Y�҂͓��Y���Y�ɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł���B �Q �������A��L�A�ɂ��Ə������܂łɁA���̐��x�̓K�p���鎑�Y�����̎��Ƃ̗p�ɋ����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ȂLj��̏ꍇ�ɂ́A�[�ł��P�\����Ă��鑡�^�ŁE�����ł̑S�����͈ꕔ�ɂ��Ĕ[�ŗP�\�̊������m�肵�A���̐Ŋz�Ɨ��q�ł�[�t����K�v������B �R �Ȃ��A�~�����@�F�����ɂ́A���� 31 �N�S���P������ߘa�U�N�R�� 31 ���܂łɒ�����Ƃɂ�����o�c�̏��p�̉~�����Ɋւ���@���{�s�K���i�ȉ��u�~�����ȗ߁v�Ƃ����B�j�� 16 ���R���ɋK�肷��l���Ə��p�v��i�ȉ��u�l���Ə��p�v��v�Ƃ����B�j��s���{���m���ɒ�o���A���̊m�F�i�~�����ȗ� 17�@�O�B�ȉ��u�l���Ə��p�v��̊m�F�v�Ƃ����B�j���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ���Ă���i�~�����ȗ߂U�O���`�A���g�A��j�A�\�j�A17�C�j�B �i�Q�l�P�j��p�҂̗v�� ��p�ҁi���᎖�ƎҖ��͓��᎖�Ƒ����l���j�̗v���́A���̂Ƃ���ł���i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�A��A70 �̂U�� 10�A��A�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂W�B�`�E�A23 �̂W�̂X�B�A�C�A㉙�j�B �P ���^�̓��ɂ����� 20 �Έȏ��ł��邱�Ɓi���^�ł̂݁j�i���P�j�B �Q �~�����@�F�����Ă��邱�ƁB �R ���^�̓��܂ň��������R�N�ȏ��ɂ킽����莖�Ɨp���Y�ɌW�����Ɓi���Q�j�ɏ]�����Ă������Ɓi���P�j�i�����ł̏ꍇ�ɂ́A�푊���l�� 60 �Ζ����Ŏ��S�����ꍇ�������A�����J�n�̒��O�ɂ����ē��莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�Ɓi���Q�j�ɏ]�����Ă������Ɓj�B �S ���^�i�����J�n�j�̎����瑡�^�Łi�����Łj�̐\�������܂ň����������Y���莖�Ɨp���Y�̑S�Ă�L���A���A���Ȃ̎��Ƃ̗p�ɋ����Ă��邱�ƁB �T ���^�Łi�����Łj�̐\�������ɂ������J�Ƃ̓͏o�����o���Ă��邱�Ƌy���F�\���̏��F���Ă��邱�Ɓi�����ł̏ꍇ�́A���F���錩���݂ł���ꍇ���܂ށB�j�B �U ���̎��Ƃ��A���^�i�����J�n�j�̎��ɂ����āA���Y�ۗL�^���ƁA���Y�^�p�^���Ƌy�ѐ������֘A����c�ƂɊY�����Ȃ����ƁB �V �l���Ə��p�v��̊m�F�i���R�j�����҂ł��邱�ƁB (��) �P ���莖�Ɨp���Y�̑��^�̎��O�ɑ������͈②�ɂ��擾�������Y���莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�ƂƓ���̎��ƂɌW�鑼�̎��Y�ɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���悤�Ƃ���ꍇ���͎Ă���ꍇ�́u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɂ��ẮA��L�P�y�тR�̗v���͕s�v�Ƃ���Ă���i�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂W�B�j�B �Q ���莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�ƂƓ��햔�͗ގ��̎��ƂɌW��Ɩ��i���Y���莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�ƂɕK�v�Ȓm���y�ыZ�\���K�����邽�߂̍����w�Z���̋���@�ւɂ�����C�w���܂ށB�j���܂܂��B �R �u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ�ɂ����āA�[�u�@�� 70 ���̂U�̂X�̋K��ɂ����᎖�Ǝ҂����Y���^�҂��瑊�����͈②�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ������Ɨp���Y�ɂ����u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����ꍇ�ɂ́A�~�����ȗߑ� 13 ���U���i�����W���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j���͑�X���i����� 11 ���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j���s���{���m���̊m�F�ɂ��i�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂X㉙�j�B �i�Q�l�Q�j���^�Җ��͔푊���l�̗v�� ���^�Җ��͔푊���l�̗v���́A���̋敪�ɉ������ꂼ��ɒ�߂�Ƃ���ł���i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�@�A70 �̂U�� 10�@�A�[�u�@�� 40 �̂V�̂W�@�A40 �̂V�� 10�@�j�B �P ���^�ҁi�푊���l�j�����Ƃ��s���Ă����ҁi��㎖�Ǝҁj�ł���ꍇ ⑴ ���^�ł̏ꍇ�ɂ́A�p�Ɠ͏o�����o���Ă��邱�Ɩ��͐\�������܂łɒ�o���錩���݂ł��邱�ƁB ⑵ ���^�̓��i�����J�n�̓��j�̑�����N�A���̑O�N�y�т��̑O�X�N�̊m��\�������F�\�����ɂ���o���Ă��邱�ƁB �Q �P�ȊO�̏ꍇ ⑴ �P�ɒ�߂�҂̑��^�̒��O�i�����J�n�̒��O�j�ɂ����āA���̎҂����v��e�����ł��邱�ƁB ⑵ �P�ɒ�߂�҂̑��^�̎��i�����J�n�̎��j��ɑ��^�i�����J�n�j�����Ă��邱�ƁB �i��Q�j�[�ŗP�\�̓K�p���邽�߂̎葱
�i���j
�� �P�@ ���^���͑�����ł����Ă��A�u�~�����@�F��v�̐\�����i��L�̊��ԓ��Ɍ���B�j�܂ł͒�o���\�B �Q�@ �u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���Ă����҂ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ�ɂ����āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����Ƃ��́u�~�����@�F��v�͕s�v�ł��邪�A�s���{���m���ɂ��u�~�����@�̊m�F�v���邽�߂̐\������L�̊����܂łɍs���K�v������i�~�����ȗ� 13�E�A�H�j�B �R �@��p�҂����^���͑����O���珳�p�������ƈȊO�̋Ɩ����s���Ă���ꍇ�ɂ́A�F�\�������悤�Ƃ���N���̂��̔N�̂R�� 15 ���܂łɐ\�����s���K�v������B �S�@ �F�\���̏��F���Ă����푊���l�̎��Ƃ𑊑��ɂ�菳�p�����ꍇ�́A�����J�n��m�������i���S�̓��j�̎����ɉ����āA���ꂼ�ꎟ�̊��ԓ��ɐ\�����s���K�v������B �@ ���̎��S�̓������̔N�̂P���P������W�� 31 ���܂ł̏ꍇ�E�E�E���S�̓�����S���ȓ� �A ���̎��S�̓������̔N�̂X���P������ 10 �� 31 ���܂ł̏ꍇ�E�E�E���̔N�� 12 �� 31 ���܂� �B ���̎��S�̓������̔N�� 11 ���P������ 12 �� 31 ���܂ł̏ꍇ�E�E�E���̔N�̗��N�̂Q�� 15 ���܂� �@�Ȃ��A��L�̂ق��A���^�҂ł����㎖�Ǝ҂́A�u�p�Ɠ͏o���v���A���̎��Ƃ�p�~����������P���ȓ��ɐŖ����ɒ�o����K�v������B �i����j
�Q�@ �u�l���Ə��p�v���v�̒�o �@��p�҂́A��㎖�Ǝ҂̎��Ƃ��m���ɏ��p���邽�߂̋�̓I�Ȍv����L�ڂ����u�l���Ə��p�v���v�����肵�A�F��o�c�v�V���x���@�ցi�ŗ��m�A���H��A���H��c�����j�̏������L�ڂ̏�A���� 31 �N�S���P�������ߘa�U�N�R�� 31 ���܂��ɁA��㎖�Ǝ҂̎傽�鎖���������݂���s���{���̒m���ɒ�o���A���̊m�F���邱�ƂƂ���Ă���i�~�����ȗ� 17�C�j�B �@ �Ȃ��A���^���͑�����ł����Ă��A�~�����@�F��̐\�����i��L�̊��ԓ��Ɍ���B�j�܂ł́u�l���Ə��p�v��v���o���邱�Ƃ��\�ł���i��R�Q�Ɓj�B �R�@ �u�~�����@�F���v�̐\�� �@ ��p�҂́A���^���͑�����ɁA�s���{���m���́u�~�����@�F���v����K�v������i�~�����@12�@�A�~�����ȗ߂U�O���`�\�j�B �@���́u�~�����@�F��v���邽�߂ɂ́A���^�̏ꍇ�ɂ́A���̑��^�����N�����N�P�� 15���܂��ɁA�����̏ꍇ�ɂ́A���̑����J�n�̓��̗��������W���ȓ��ɁA�F�����҂̎傽�鎖���������݂���s���{���̒m���ɁA�\�������o���邱�ƂƂ���Ă���i�~�����ȗ߂V�I�`�L�j�B �@�Ȃ��A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���Ă����҂ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ�ɂ����āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����Ƃ��́A�u�~�����@�F��v�͕s�v�ł��邪�A�s���{���m���ɂ��u�~�����@�̊m�F�v����K�v������A��L�̊����܂łɁA�m�F����҂̎傽�鎖���������݂���s���{���̒m���ɁA�\�������o���邱�ƂƂ���Ă���i�~�����ȗ� 13�E�`�J�j�B �S�@ �u�F�\���̏��F�v�̐\�� �@��p�҂͐F�\���̏��F���Ă��邱�Ɓi�����ł̏ꍇ�́A���̏��F���錩���݂ł��邱�Ƃ��܂ށB�j���v���Ƃ���Ă��邽�߁i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�A��z�A70 �̂U�� 10�A��j�j�A���̏����ł̔[�Œn�̏����Ŗ������ɑ��A�u�����ł̐F�\�����F�\�����v���o����K�v������B �@�Ȃ��A���̐\�����́A���Ƃ��J�n����������Q���ȓ��ɒ�o����K�v�����邪�i���@ 144�j�A�F�\���̏��F���Ă����푊���l�̎��Ƃ𑊑��ɂ�菳�p�����ꍇ�́A�����J�n��m�������i���S�̓��j�̎����ɉ����āA���ꂼ�ꎟ�̊��ԓ��ɒ�o���邱�ƂƂ���Ă���i����� 144�|�P�j�B �@ ���̎��S�̓������̔N�̂P���P������W�� 31 ���܂ł̏ꍇ�E�E�E���S�̓�����S���ȓ� �A ���̎��S�̓������̔N�̂X���P������ 10 �� 31 ���܂ł̏ꍇ�E�E�E���̔N�� 12 �� 31 ���܂� �B ���̎��S�̓������̔N�� 11 ���P������ 12 �� 31 ���܂ł̏ꍇ�E�E�E���̔N�̗��N�̂Q�� 15 ���܂� �@�������A��p�҂��A���^���͑����O���瑼�̋Ɩ����s���Ă���ꍇ�ɂ́A�F�\�������悤�Ƃ���N�������̔N�R�� 15 ���܂��ɐ\�����s���K�v������i���@ 144�j�B �@�Ȃ��A��p�҂����Y���̋Ɩ��ɂ��Ċ��ɐF�\���̏��F���Ă���ꍇ�ɂ́A�V���ɐ\�����s���K�v�͂Ȃ��B �T�@ �u�J�Ɠ͏o���v�̒�o �@ ��p�҂͏��p�������Ƃɂ��ĊJ�Ɠ͏o�����o���Ă��邱�Ƃ��v���Ƃ���Ă��邽�߁i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�A��z�A70 �̂U�� 10�A��j�j�A���̏����ł̔[�Œn�̏����Ŗ������ɑ��A���p�������ƂɌW��u�J�Ɠ͏o���v���A�J�Ƃ̓�����P���ȓ��ɒ�o����K�v������i���@ 229�j�B �U�@ �ȏ�́A��p�҂��K�v�ƂȂ�葱�ł��邪�A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�ɌW�鑡�^�҂̂�����㎖�Ǝ҂ɊY������҂ɂ��ẮA���̑��^���������ƂɌW��u�p�Ɠ͏o���v�̒�o���v���Ƃ���Ă���i�[�u�@�� 40 �̂V�̂W�@��C�j�A���Y�͏o���ɂ��ẮA�������Ƃ�p�~����������P���ȓ��ɔ[�Œn�̏����Ŗ������ɒ�o���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�i���@ 229�j�B |
��Ђ̎��Ə��p�Ő��Ƃ̑���_
��Ђ̎��Ə��p�Ő��͔[�ŗP�\�̑Ώێ��Y�����ꊔ�����ł����A�l�Ŏ��Ə��p�Ő��̑Ώێ��Y�͎��Ɨp�̓y�n�⌚�����A���̌������p���ł���_����ȑ���_�ł��B
�k��~�ҁuQ��A�ŗ�������I�l�Ŏ��Ə��n�Ő��̎d�g�݂Ǝ葱���v�Ŗ�������o�ŋǁi2019�N�A54�Łj �i��R�j�����J�n��̌l���Ə��p�v��̒�o�̉�
�i���j �@�]�́A���v�̗v���������ƂŁA�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł���B �i����j �P�@ �u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邽�߂ɂ́A���̎��Ƃ����p���悤�Ƃ����p�҂͉~�����@�F�����K�v�����邪�i�[�u�@ 70 �̂U�� 10�A��C�j�A�~�����ȗ߂ł́A���̉~�����@�F��̑O��Ƃ��āA�l���Ə��p�v���s���{���m���ɒ�o���A���̊m�F���邱�Ƃ��v���Ƃ���Ă���i�~�����ȗ߂U�O���`�A���g�A��j�A�\�j�j�B �Q�@ ���̌l���Ə��p�v��ɂ��ẮA�~�����ȗ߂ɂ����āA���� 31 �N�S���P������ߘa�U�N�R��31 ���܂ł̊Ԃɒ�o���邱�ƂƂ���Ă��邪�i�~�����ȗ� 17�C�j�A�����J�n�O�ɒ�o���邱�Ƃ܂ł́A�v���Ƃ���Ă��Ȃ��B �R �@���������āA�l���Ə��p�v��̒�o�͑����J�n��ł����Ă��~�����@�F��̐\�����܂łɍs���悭�A���Y�l���Ə��p�v��ɂ��s���{���m���̊m�F����ƂƂ��ɁA�~�����@�F�������ő����ł̐\���������̒�o�����܂łɒ�o����ȂǁA���v�̗v���������Ƃ��́A�]�͍b����擾�������莖�Ɨp���Y�ɂ��u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł��邱 �ƂƂȂ�B (��) �P�@ �~�����@�F����邽�߂ɂ́A�����J�n��W���ȓ��ɐ\�����s���K�v������i�~�����ȗ߂V�J�A�L�j�B �Q �@�l���Ə��p�v���ߘa�U�N�R�� 31 ���܂łɓs���{���m���ɒ�o����K�v�����邱�Ƃ́A�����J�n��ɒ�o����ꍇ�ł����Ă����l�ł���B �S�@ �Ȃ��A���Y���擾������Ɍl���Ə��p�v��̒�o���\�ȓ_�́A���^�̏ꍇ�����l�ł���B �i��S�j�[�ŗP�\�̓K�p��ɕK�v�ƂȂ�葱�i�p���͏o���̒�o�j
�i���j �@ ���^�ŁE�����ł̑S���ɂ��Ĕ[�ł̗P�\�ɌW��������m�肷��܂ł̊ԁA�R�N���ƂɁA���� ���ނ�Y�t�����u�p���͏o���v���A�[�Œn�̏����Ŗ������ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i����j �P �u�l�̎��Ɨp���Y�ɂ��Ă̑��^�ŁE�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p������᎖�Ǝғ� �i���᎖�ƎҖ��͓��᎖�Ƒ����l���������B�ȉ������B�j�́A���^�Ŗ��͑����ł̑S���ɂ� �[�ł̗P�\�ɌW��������m�肷����܂ł̊Ԃɓ��ᑡ�^������͓��ᑊ������i�� ��\�������̗�������R�N���o�߂��邲�Ƃ̓��������B�ȉ��u�������v�Ƃ����B�j������ ��ꍇ�ɂ́A�͏o�����i���Y�������̗�������R�����o�߂�����������B�j�܂łɁA���� �����Ĕ[�ŗP�\�̓K�p�������|�y�ѓ���i�j���Ɨp���Y�i������Ɨp���Y���͓��� ���Ɨp���Y�������B�ȉ������B�j�ɌW�鎖�ƂɊւ��鎖�����L�ڂ����͏o���i�ȉ��u�p���͏o���v �Ƃ����B�j���A�[�Œn�̏����Ŗ������ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƂ���Ă���i�[�u�@ 70 �� �U�̂W�H�A70 �̂U�� 10�I�A�[�u�@�� 40 �̂V�̂W㉘�A40 �̂V�� 10㉖�A�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂W�P �`�R�A23 �̂W�̂X�N�`�P�j�B (��) �u����\�������v�Ƃ́A���᎖�Ǝғ��̍ŏ��̑[�u�@�� 70 ���̂U�̂W��P���̋K��̓K�p�ɌW�鑡�^ �̓��̑�����N���̑��^�ł̐\�����̒�o�������͍ŏ��̑[�u�@�� 70 ���̂U�� 10 ��P���̋K��̓K�p�ɌW �鑊���ɌW�铯���ɋK�肷�鑊���ł̐\�����̒�o�����̂����ꂩ�������������i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�E�A70 �̂U�� 10�E�j�B �Q �Ȃ��A�p���͏o���ɂ́A���̏��ނ�Y�t����K�v������i�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂W�P�A23 �̂W�� �X�N�j�B ⑴ �������ɂ����鎟�̓���i�j���Ɨp���Y�̋敪�ɉ������ꂼ��ɒ�߂鏑�� �C�@ ���p���Y ���Y���Y�ɌW��Œ莑�Y�ł̒ʒm���̎ʂ����̑��̏��ށi���Y���Y�̏��L�҂� �Z���y�ю������тɓ��Y���Y�̏��݁A��ށA���ʋy�щ��i���L�ڂ��ꂽ���̂Ɍ���B�j �� �@�����ԁA�y�����ԁA�����@�t���]�� �����Ԍ����̎ʂ��A�����Ԑœ��ېŖ����̎ʂ� ���̑��̏��ނł����̎��Y�����莖�Ɨp���Y�ɊY�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ������ �n �@�ʎ��� ���̉ʎ��������݂���y�n���k��̗p�ɋ�����Ă��邱�Ƃ����鏑�� ⑵ �������̑�����N�̑O�N�ȑO�R�N���̊e�N�ɂ��������i�j���Ɨp���Y�ɌW�� ���ƂɌW�鎟�Ɍf���鏑�ށi���᎖�Ǝғ����c�ގ��Ƃ����Y����i�j���Ɨp���Y�ɌW �鎖�Ƃ݂̂ł���ꍇ�ɂ́A�C�Ɍf���鏑�ނ������B�j �C�@���Y���ƂɌW��ݎؑΏƕ\�y�ё��v�v�Z�� ���@���Y����i�j���Ɨp���Y�Ƃ��̑��̎��Y�̓�����L�ڂ������ނœ��Y����i�j���� �p���Y���C�̑ݎؑΏƕ\�Ɍv�コ��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ�����́i�Œ莑�Y�䒠���j ⑶ ���̑��Q�l�ƂȂ�ׂ����� (��) �@��Ђ̐ݗ��ɔ��������o���ɂ�����i�j���Ɨp���Y�̑S�Ă̈ړ]�ɂ��đ[�u�@�� 70 ���̂U�̂W�� �U�����͑� 70 ���̂U�� 10 ��U���̏��F�i�����o�����F�j�������᎖�Ǝғ����p���͏o�����o�� ��ꍇ�̓Y�t���ނ́A���̉�Ђ̒芼�̎ʂ����A�u���ꊔ�����ɌW�鑊���ŁE���^�ł̔[�ŗP�\�v�i�[�u�@ 70 �̂V���j�ɂ�����Y�t���ނɏ��������ނƂ���Ă���i�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂W�M�A23 �̂W�̂X�K�j�B |
| �s���莖�Ɨp���Y�t �i��U�j�[�ŗP�\�̑ΏۂƂȂ���莖�Ɨp���Y�̊T�v
�i���j �P ���̐��x�̑ΏۂƂȂ�u���莖�Ɨp���Y�v�Ƃ́A��㎖�Ǝҁi���^�Җ��͔푊���l�j�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă������̎��Y�ŁA���̑��^���͑����J�n�̓��̑�����N�̑O�N���̎��Ə����ɌW��F�\�����̑ݎؑΏƕ\�Ɍv�コ��Ă������̂�����( �[�u�@ 70 �̂U�̂W�A��A70 �̂U�� 10�A��j�B �@ ��n���i���̖ʐς̍��v�̂��� 400 �u�ȉ��̕����j �A �����i���̏��ʐς̍��v�̂��� 800 �u�ȉ��̕����j �B ���̌������p���Y �E �Œ莑�Y�ł̉ېőΏۂƂ���Ă������ �E �����ԐŁE�y�����Ԑł̉c�Ɨp�̕W���ŗ����K�p����鎩���� �E ���̑����̂��́i�ݕ��^���p�ȂLj��̎����ԁA�����E�ʎ����̐����A���������̖��`�Œ莑�Y�j (��) �P �u��n���v�Ƃ́A�y�n���͓y�n�̏�ɑ����錠���������A���̌������͍\�z���̕~�n�̗p�ɋ�����Ă�����̂̂����A���̑��^���͑����J�n�̒��O�Ɏ��Ƃ̗p�ɋ�����Ă������̂Ƃ��đ[�u�@�ߑ� 40 ���̂V�̂W��U�����͑[�u�@�ߑ� 40 ���̂V�� 10 ��U���ɒ�߂���̂Ɍ�����B�ȉ������B �Q ��㎖�ƎҖ��͐��v��e�������瑊�����͈②�ɂ��擾������n���ɂ��đ[�u�@�� 69 ���̂S((���K�͑�n���ɂ��Ă̑����ł̉ېʼn��i�̌v�Z�̓���))�̋K��i�ȉ��u���K�͑�n���̓���v�Ƃ����B�j�̓K�p����҂�����ꍇ�ɂ́A��L�@�̖ʐς�����̖ʐς��T�������ʐςɂ��i�� 30 �Q�Ɓj�B �R �u�����v�́A���̑��^���͑����J�n�̒��O�Ɏ��Ƃ̗p�ɋ�����Ă������̂Ƃ��đ[�u�@�ߑ� 40 ���̂V�̂W��V�����͑[�u�@�ߑ� 40 ���̂V�� 10 ��W���ɒ�߂���̂Ɍ�����B�ȉ����B �Q �Ȃ��A��㎖�Ǝ҂̐��v��e���������L���鎑�Y�ł����Ă��A��㎖�Ǝ҂̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă�����L�P�Ɍf���鎑�Y�ŏ�L�P�̑ݎؑΏƕ\�Ɍv�コ��Ă������̂ɂ��ẮA���莖�Ɨp���Y�ɊY������B �i��V�j���莖�Ɨp���Y�̊�ƂȂ�ݎؑΏƕ\
�i���j �@��������A���Ƃ��c��ł����b�̑��^�̓��̑�����N�i�ߘa�Q�N�j�̑O�N���i�ߘa���N���j�̎��Ə����ɌW��F�\�����̑ݎؑΏƕ\�ɂ��B �i��W�j���莖�Ɨp���Y�͈̔́i���̂P�j�F������
�i���j ���̎����Ԃ��ΏۂƂȂ�i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�A��n�A�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂W�A��A�O�j�B �@ �����ԐŁE�y�����Ԑł̉c�Ɨp�̕W���ŗ����K�p����鎩���� �A �@�ȊO�̎����ԂŎ��Ɍf������� �C �����ԓo�^�K���ʕ\��Q�̎����Ԃ͈̔͗��̂P�A�Q�A�S�y�тU�Ɍf���镁�ʁE���^������ �� ���H�^���ԗ��@�{�s�K���ʕ\��Q�̂S�̎����Ԃ̗p�r�ɂ��敪���̂P�y�тR�Ɍf����y������ �B �����@�t���]�ԁA�y�����ԁi�Q�ւ̂��̂Ɍ���B�j�y�я��^���ꎩ���ԁi�S�ֈȏ�̂��̂̂����A��p�̂��̋y�щc�Ɨp�̕W���ŗ����K�p�����ݕ��p�̂��̂������B�j �C �Œ莑�Y�ł̉ېőΏۂƂ�����^���ꎩ���� (��) ��L�̂����A�y�чB�ɂ��ẮA��Ƃ��Ď���͌�y�̗p�ɋ�����ړI�ŕۗL������̂͏�����A���̎��Y�̂����ɓ��莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�Ƃ̗p�ȊO�̗p�ɋ�����Ă�������������Ƃ��́A���Y���Ƃ̗p�ɋ�����Ă��������Ɍ�����B �i��X�j���莖�Ɨp���Y�͈̔́i���̂Q�j�F���`�Œ莑�Y�E����
�i���j ���莖�Ɨp���Y�ɊY�����錸�����p���Y�ł��閳�`�Œ莑�Y�y�ѐ����Ƃ́A�����Ŗ@�{�s�ߑ�U���W���Ɍf���閳�`�Œ莑�Y�y�ѓ����X���Ɍf���鐶���������A��̓I�ɂ́A���̕\�̂Ƃ���ł���i�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂W�A��A���߂U���A��j�B
�i�� 10�j��n���ɌW����x�ʐρi���̂P�j�F�����̎҂�����̑��^�҂��瑡�^�����ꍇ
�i���j �@�K�p�ΏۂƂȂ�ʐς́A����n�y�т���n�̍��v�� 400 �u�܂łƂȂ�B �Ȃ��A�[�ŗP�\�̓K�p�����n���̖ʐς̓���ɂ��ẮA�w�y�тx�̍��ӂɊ�Â��I���ɂ��B �i�� 11�j��n���ɌW����x�ʐρi���̂Q�j�F��̎҂������̑��^�҂��瑡�^�����ꍇ
�i���j ����n�� 500 �u�̂��� 400 �u�܂ŁA ����n�� 200 �u�̑S�Ăɂ��āA�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p ���邱�Ƃ��ł���B �i�� 12�j��n���ɌW����x�ʐρi���̂R�j�F���^�ł̔[�ŗP�\�ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ
�i���j �a��n�̂��� 150 �u���u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ�B �i�� 13�j��n���ɌW����x�ʐρi���̂S�j�F���x�ʐϗv�������Ȃ��ꍇ
�i���j �@�q�w�y�юq�x���u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A����n�y�т���n�� �݂ł���A���̎��Ɨp���Y�ɂ��Ắu���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł���B �s�l�̎��Ɨp���Y�ɂ��Ă̑��^�ł̔[�ŗP�\�y�іƏ��W�t �i�� 14�j���^�҂̗v���i���̂P�j�F���Ǝ҂Ƃ��̐��v��e��������̑��^
�i���j ���̂Ƃ���B �E ����@�̏ꍇ�ɂ́A�b�y�щ��Ƃ��Ɂu���^�ł̔[�ŗP�\�v�ɌW�鑡�^�҂ɊY������B �E ����A�̏ꍇ�ɂ́A�b�̂݁u���^�ł̔[�ŗP�\�v�ɌW�鑡�^�҂ɊY������B �i�� 15�j���^�҂̗v���i���̂Q�j�F���v����ɂ���e�������ꂼ�ꎖ�Ƃ��s���Ă���ꍇ
�i���j �@����@�y�чA�̂�����̏ꍇ���A�b�y�щ��́u���^�ł̔[�ŗP�\�v�ɌW�鑡�^�҂ɊY������B ���[�ŗP�\�̓K�p����ɂ́A���ꂼ��̑��^��31�N�P���P������ߘa10�N12 ��31���܂ł̊Ԃɍs���K�v������B �i�� 16�j���^�҂̗v���i���̂R�j�F�F�\��
�i���j �b�́u���^�ł̔[�ŗP�\�v�ɌW�鑡�^�҂ɊY�����Ȃ��B �@���莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�Ƃ��s���Ă���҂ɂ��ẮA���̎��Ƃɂ��āA���^�̓��̑�����N�A���̑O�N�y�ёO�X�N�̏����ł̊m��\�������A�F�\�����ɂ���o���Ă��邱�Ƃ��A���^ �ł̔[�ŗP�\�ɌW�鑡�^�҂̗v���̈�Ƃ��Đ݂����Ă���i�[�u�@70�̂U�̂W�@�A�[�u�@�� 40�̂V�̂W�@�ꃍ�j�B |
�i�� 17�j���^�҂̗v���i���̂S�j�F�u���ɑ��^�����Ă�����́v�̈Ӌ`�@
�i���j �@����B�ȊO�́A�b�́u���ɑ��^�����Ă�����́v�ɊY������B �P�@�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W��P���́A���^�҂ɂ��āA�u���ɂ��̍��̋K��̓K�p�ɌW�鑡�^���� �Ă�����̂������v�ƋK�肵�Ă���B ���������āA���^�҂͂��̎��ƂɌW����莖�Ɨp���Y�̑S�Ă��ꊇ���đ��^����K�v������� �ł����āA���^�҂������̎��Ƃ��c��ł���ꍇ�ɂ��A���̕����̎��ƂɌW����莖�Ɨp���Y�� �S�Ă��ꊇ���đ��^����K�v������B �Q�@�������A���᎖�Ǝ҂��Q�l�ȏ゠��ꍇ�ɂ����āA����N���ɁA�����̓��᎖�Ǝ� �ɓ��莖�Ɨp���Y�̑��^���s�����̂́u���ɑ��^�����Ă�����́v�Ɋ܂܂�Ȃ����ƂƂ���Ă� ��i�[�u�� 70 �̂U�̂W�|�P(��)�P�j�B �R ��̎��������ƁA ����@�́A����N���̑��^�ł��邪�A�҂�����ł��邽�߁A ����A�́A�قȂ�N���̑��^�ł��邽�߁A ����C�́A�قȂ�҂ւ̑��^�ł��邪�A����N���̑��^�łȂ����߁A ���ꂼ��̎���̍b�́A�u���ɑ��^�����Ă�����́v�ɊY�����邱�ƂƂȂ�i�i�Q�l�j����P�E�Q�j�B �S�@�����A����B�̍b�́A����N���ɈقȂ�҂ɑ��^�����Ă��邱�Ƃ���A�u���ɑ��^�����Ă���� �́v�ɂ͊Y�����Ȃ����ƂƂȂ�i�i�Q�l�j����R�j�B �T�@�Ȃ��A�u���ɑ��^�����Ă�����́v�ɊY�����邩�ǂ����̔���͑��^�҂��Ƃɍs�����Ƃ���A���鑡�^�҂����莖�Ɨp���Y�̑��^�������ꍇ�ɁA���̑��^�҂ɌW��҂����̎҂�����ɓ��� ���Ɨp���Y�̑��^���Ă����Ƃ��ł����Ă��A���Y���̎҂́A���Y���^�҂��u���ɑ��^�����Ă�����́v�ɊY�����邩�ǂ����̔���ɂ͊W���Ȃ����ƂƂȂ�i�i�Q�l�j����S�E�T�j�B �i�� 18�j���^�҂̗v���i���̂T�j�F�u���ɑ��^�����Ă�����́v�̈Ӌ`�A
�i���j ���y�n�̑��^�i��^�j���A��ꑡ�^�Ɠ���N���ɍs���A���A���̎҂��قȂ�҂ł��� �ꍇ�������A�b�́u���ɑ��^�����Ă���ҁv�ɊY������B �i�� 19�j�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邽�߂̊���
�i���j �@����@�̏ꍇ�͗ߘa�Q�N�U���P���܂łɁA����A�̏ꍇ�͗ߘa 10 �N 12 �� 31 ���܂łɁA���ꂼ�� ���^���s���K�v������B �@�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W��P���́A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̑ΏۂƂȂ鑡�^�ɂ��āA�u���� 31 �N �P���P������ߘa 10 �N 12 �� 31 ���܂ł̊Ԃ̑��^�ŁA�ŏ��̂��̍��̋K��̓K�p�ɌW�鑡�^�y�� ���Y���^�̓����̑����߂Œ�߂������P�N���o�߂�����܂ł̑��^�Ɍ���v�ƋK�肵�Ă��邱�Ƃ���A�u���� 31 �N�P���P������ߘa 10 �N 12 �� 31 ���܂ł̊ԁv�Ƃ������Ԃ́u�ŏ��̂��̍��̋K��̓K�p�ɌW�鑡�^�v�Ɓu���Y���^�̓����̑����߂Œ�߂������P�N���o�߂�����܂ł̑��^�v�̗����ɌW�邱�ƂƂȂ�A���Y���ԓ��ɍs���邱���̑��^���A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̑ΏۂƂȂ邱�ƂƂȂ�i�[�u�� 70 �̂U�̂W�\�R�j�B (��) �u���߂Œ�߂���v�Ƃ́A�ŏ��̑[�u�@�� 70 ���̂U�� 10 ��P���̋K��̓K�p�ɌW�鑊���̊J�n�̓������� �i�[�u�@�� 40 �̂V�̂W�A�j�B �i�� 20�j���^�ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z�i���̂P�j�F��N�ېłɂ��ꍇ
�i���j �@�P�\�Ŋz�� 1,035.5 ���~�A�\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz�� 244.5 ���~�ƂȂ�B �i����j �P �u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�ɂ��擾����������Ɨp���Y����N�ېł̓K�p�ɌW����̂ł���ꍇ�ɂ́A���̔N���ɂ��̎҂����^�ɂ��擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�Ŋz�̂����A�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W��Q����R���C�̋K��Ɋ�Â����Y������Ɨp���Y�̉��z�����̔N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��Čv�Z�������z���[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�ƂȂ�A���̔[�ł��P�\����邱�ƂƂȂ�B �i���j��L�ɂ��v�Z�����[�ŗP�\���̑��^�Ŋz���O�ƂȂ�ꍇ�ɂ́A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�͂Ȃ��B �Q ���������āA��̎���ł́A���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ ���̔N���Ɏ擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�ł̊z �@�@���� �@�@�@���Ɨp���Y �@��b�T���z {�i500 ���~�{3,000 ���~�j�| 110 ���~ }× 50�� �| 415 ���~ �� 1,280 ���~ ⑵ ���Ɨp���Y�ɌW��[�ŗP�\���̑��^�Ŋz �@���Ɨp���Y �@��b�T���z �i3,000 ���~ �| 110 ���~ �j× 45�� �| 265 ���~ �� 1,035.5 ���~ ⑶ �\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz ⑴ �| ⑵ �� 244.5 ���~ �i�� 21�j���^�ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z�i���̂Q�j�F���������Z�ېłɂ��ꍇ
�i���j �@�P�\�Ŋz�� 400 ���~�A�\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz�� 100 ���~�ƂȂ�B �i����j �P �u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�ɂ��擾����������Ɨp���Y�����������Z�ېł̓K�p������̂ł���ꍇ�ɂ́A���̔N���ɑ����Ŗ@�� 21 ���̂X��T���ɋK�肷����葡�^�҂��瑡�^�ɂ��擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�Ŋz�̂����A�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W��Q����R �����̋K��Ɋ�Â����Y������Ɨp���Y�̉��z�����̔N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��Čv�Z�������z���[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�ƂȂ�A���̔[�ł��P�\����邱�ƂƂȂ�B �i���j �@��L�ɂ��v�Z�����[�ŗP�\���̑��^�Ŋz���O�ƂȂ�ꍇ�ɂ́A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�͂Ȃ��B �Q�@���������āA��̎���ł́A���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ �b�i���葡�^�ҁj����擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�ł̊z �@���Ɨp���Y�@�����@�@�@�@���ʍT���z {3,000 ���~�{500 ���~�|�i2,500 ���~�|1,500 ���~�j}×20�� �� 500 ���~ ⑵ ���Ɨp���Y�ɌW��[�ŗP�\���̑��^�Ŋz �@���Ɨp���Y �@���ʍT���z {3,000 ���~�|�i2,500 ���~�|1,500 ���~�j}× 20�� �� 400 ���~ ⑶ �\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz ⑴ �| ⑵ �� 100 ���~ �i�� 22�j���^�ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z�i���̂R�j�F�����̑��^�҂����N�ېłɂ�鑡�^�����ꍇ
�i���j �@�b�y�щ����ꂼ�ꂩ��u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�ɂ��擾�������Ɨp���Y�̉��z �̍��v�z���A���̔N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��Ĕ[�ŗP�\���̑��^�Ŋz���v�Z���A���̋��z�� ���^�ҁi�b�y�щ��j�̈قȂ���̂��Ƃ̎��Ɨp���Y�̉��z�ɂ�肠���邱�ƂŁA���ꂼ�ꂲ�� �̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�i�P�\�Ŋz�j���v�Z�����B �@�Ȃ��A��̎���̏ꍇ�ɂ́A�P�\�Ŋz�́A1,530 ���~�i�����A�b��������^�ɌW����� 1,147.5 ���~�A����������^�ɌW����� 382.5 ���~�j�A�\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz�� 250 ���~�ƂȂ�B �i����j �P�@������Ɨp���Y�ɌW�鑡�^�҂��Q�ȏ゠��ꍇ�̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z�ɂ��ẮA �[�u�@�ߑ�40���̂V�̂W��11���y�ё�12���ɋK�肪�݂����Ă���B �@��̓I�ɂ́A���̑��^����N�ېłɂ����̂ł���ꍇ�ɂ́A���᎖�Ǝ҂����̔N���ɑ��^�ɂ��擾�����S�Ă̓�����Ɨp���Y�̉��z�̍��v�z���A���Y���᎖�Ǝ҂ɌW�邻�� �N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��i�[�u�@��40�̂V�̂W�J��j�A�[�u�@��70���̂U�̂W��Q����R ���C�̋K��Ɋ�Â����^�Ŋz�̌v�Z���s���i100�~�����̒[�������͍s��Ȃ��j�B �@�����āA����ɂ��v�Z���ꂽ���z���A���^�҂̈قȂ���̂��Ƃ̓�����Ɨp���Y�̉��z�ɂ�肠�������̂��A���̈قȂ���̂��Ƃ̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�i100�~�����̒[���؎̂āj �ƂȂ�i�[�u�@��40�̂V�̂W�K�j�A�����̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̍��v�z���A���Y���᎖�Ǝ҂ɌW��[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�ƂȂ�B �Q�@���������āA��̎���ł́A���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ ���̔N���Ɏ擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�ł̊z ���Ɨp���Y�i�b�j �����i�b�j ���Ɨp���Y�i���j ��b�T���z {�i3,000 ���~ �{ 500 ���~ �{ 1,000 ���~ �j�| 110 ���~ }×50���|415 ���~��1,780 ���~ ⑵ ���Ɨp���Y�ɌW��[�ŗP�\���̑��^�Ŋz �@ ���Ɨp���Y�̂ݎ擾�������̂Ƃ��Čv�Z�������^�ł̊z ���Ɨp���Y�i�b�j ���Ɨp���Y�i���j ��b�T���z {�i 3,000 ���~ �{ 1,000 ���~ �j�| 110 ���~ }× 50�� �| 415 ���~ �� 1,530 ���~ �A �@�̂����A�b����̑��^�ɌW����� ���Ɨp���Y�i�b�j ���Ɨp���Y�i�b�j ���Ɨp���Y�i���j �@ × 3,000 ���~ / �i 3,000 ���~ �{ 1,000 ���~ �j�� 1,147.5 ���~ �B �@�̂����A������̑��^�ɌW����� ���Ɨp���Y�i���j �@���Ɨp���Y�i�b�j ���Ɨp���Y�i���j �@ × 1,000 ���~ / �i 3,000 ���~ �{ 1,000 ���~ �j�� 382.5 ���~ �C �[�ŗP�\���̑��^�Ŋz �A �{ �B �� 1,530 ���~ ⑶ �\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz ⑴ �| ⑵ �� 250 ���~ �R�@�Ȃ��A�����̑��^�҂��瑡�^�����ꍇ�ɂ����āA���̑��^�҂����S�����Ƃ��ɂ�����Ə������P�\�Ŋz�̌v�Z�ɂ��ẮA�� 57 ���Q�ƁB �i�� 23�j���^�ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z�i���̂S�j�F�����̑��^�҂��瑊�������Z�ېłɂ�鑡�^�����ꍇ
�i���j �@�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�ɂ��擾�������Ɨp���Y�̉��z����葡�^�ҁi�b�y�� ���j���Ƃɍ��v�����z�̂��ꂼ��̊z���A���̔N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��Ĕ[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�i�P�\�Ŋz�j���v�Z����B �@�Ȃ��A��̎���̏ꍇ�ɂ́A�P�\�Ŋz�� 700 ���~�i�����A�b��������^�ɌW����� 600 ���~�A ����������^�ɌW����� 100 ���~�j�A�\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz�� 100 ���~�ƂȂ�B �i����j �P ������Ɨp���Y�ɌW�鑡�^�҂��Q�ȏ゠��ꍇ�̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z�ɂ��ẮA �[�u�@�ߑ�40���̂V�̂W��11���y�ё�12���ɋK�肪�݂����Ă���B ��̓I�ɂ́A���̑��^�����������Z�ېłɂ����̂ł���ꍇ�ɂ́A���᎖�Ǝ҂����̔N ���ɓ���[�u�̓K�p�ɌW�鑡�^�ɂ��擾�����S�Ă̓�����Ɨp���Y�̉��z����葡�^�҂��Ƃɍ��v�����z�̂��ꂼ��̊z�Y���᎖�Ǝ҂ɌW�邻�̔N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��i�[�u�@��40�̂V�̂W�J��j�A�[�u�@��70���̂U�̂W��Q����R�����̋K��Ɋ�Â����葡�^�҂̈قȂ���̂��Ƃ̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z���s�����ƂƂȂ�i100�~�����̒[���؎̂āj�B �@�����āA�����̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̍��v�z���A���Y���᎖�Ǝ҂ɌW��[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�ƂȂ�B �Q ���������āA��̎���ł́A���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ ���̔N���Ɏ擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�ł̊z �@ �b����擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�ł̊z �@�@���Ɨp���Y�@�@�����@�@�@�@�@�@���ʍT���z {�i 4,000 ���~ �{ 500 ���~ �j�| �i 2,500 ���~ �| 1,500 ���~ �j }× 20�� �� 700 ���~ �A ������擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�ł̊z �@�@���Ɨp���Y �@���ʍT���z �i 3,000 ���~ �| 2,500 ���~ �j× 20�� �� 100 ���~ �B �@ �{ �A �� 800 ���~ ⑵ ���Ɨp���Y�ɌW��[�ŗP�\���̑��^�Ŋz �@ �b����̑��^�ɌW����� �@���Ɨp���Y�@�@�@ ���ʍT���z �o 4,000 ���~ �| �i 2,500 ���~ �| 1,500 ���~ �j �p× 20�� �� 600 ���~ �A ������̑��^�ɌW����� �@�@���Ɨp���Y�@ ���ʍT���z �i 3,000 ���~ �| 2,500 ���~ �j× 20�� �� 100 ���~ �B �@ �{ �A �� 700 ���~ ⑶ �\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz ⑴ �| ⑵ �� 100 ���~ �R �Ȃ��A�����̑��^�҂��瑡�^�����ꍇ�ɂ����āA���̑��^�҂����S�����Ƃ��ɂ�����Ə������P�\�Ŋz�̌v�Z�ɂ��ẮA�� 57 ���Q�ƁB |
�i�� 25�j���^�ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z�i���̂U�j�F���ƂɌW����̈�������ꍇ
�i���j �@�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�ɂ��擾�������Ɨp���Y�̉��z������̋��z�i�_���ɂ�莖�ƂɊւ�����̂ƔF�߂�����ȊO�̍��ł��邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă�����̋��z�������B�j���T���������z���A���̔N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��Ĕ[�ŗP�\���̑��^�Ŋz���v�Z����B �@�܂��A���̏ꍇ�ɂ�����u���Ɨp���Y�̉��z�v�́A���̈����Ȃ����̂Ƃ����ꍇ�ɂ����鉿�z�i�����ŕ]���z�j�ɂ��B �@�Ȃ��A��̎���̏ꍇ�ɂ́A�P�\�Ŋz�� 1,035.5 ���~�A�[�t�Ŋz�� 494.5 ���~�ƂȂ�B �i����j �P ������Ɨp���Y�̑��^�ƂƂ��Ɉ�������������ꍇ�̔[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z�ɂ��ẮA������Ɨp���Y�̉��z����A���̈��������̉��z�i�_���ɂ����� ���Ɨp���Y�ɌW�鎖�ƂɊւ�����̂ƔF�߂�����ȊO�̍��ł��邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă�����̋��z�������B�j���T���������z���A���̔N���̑��^�ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��Čv�Z���� ���ƂƂ���Ă���i�[�u�@70�̂U�̂W�A�O�C�A�[�u�@��40�̂V�̂W�G�j�B �Q �Ƃ���ŁA���Y�̑��^�ƂƂ��ɍ����������ꍇ�ɂ����āA���Y���Y���y�n�y�ѓy�n�̏� �ɑ����錠�����тɉƉ��y�т��̕����ݔ����͍\�z���ł���Ƃ��́A�����̎��Y�̉��z�͍��Y�]����{�ʒB�̒�߂ɂ���ĎZ�肵�����z�ɂ�炸�A�u�ʏ�̎�����z�v�ɑ���������z�ɂ���� �]���������ƂƂ���Ă���i�������N�R��29���t���]�T�A�����Q�\204�u���S�t���^���͑Ή��� ������ɂ��擾�����y�n���y�щƉ����ɌW��]�����тɑ����Ŗ@��V���y�ё�X���̋K��̓K �p�ɂ��āv�i�ȉ��u���S�t���^�ʒB�v�Ƃ����B�j�P�j�B �@�������A�[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z�ɓ������ẮA�����̎��Y�ł��������Ɨp���Y�̉��z�͍��̈����Ȃ����̂Ƃ����ꍇ�ɂ����鉿�z�Ƃ���|�K�肳��Ă��邽���i�[�u�@ ��40�̂V�̂W�H�j�A�����̎��Y�̉��z�ɂ��Ă͕��S�t���^�ʒB�̓K�p�͂Ȃ��A���Y�]����{�ʒB�̒�߂ɂ���ĎZ�肵�����z�ɂ�邱�ƂƂȂ��B (��) �@������Ɨp���Y�̉��z�����̈����Ȃ����̂Ƃ����͔̂[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z������ꍇ�Ɍ������̂ł����āA�[�t���ׂ����^�ł̊z�̌v�Z�ɂ��Ắu�ʏ�̎�����z�v�ɑ���������z�ɂ�� ���ƂƂȂ�B �R ���������āA��̎���ł́A���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ ���̔N���Ɏ擾�����S�Ă̍��Y�ɌW�鑡�^�ł̊z �@�@�y�n�E���� �i�ʏ�̎�����z�j �@�B���u �@�@�� �@�@�@�@��b�T���z {�i5,000 ���~ �{ 1,000 ���~ �| 2,000 ���~�j�| 110 ���~ }×50���|415 ���~��1,530 ���~ ⑵ ���莖�Ɨp���Y�ɌW��[�ŗP�\���̑��^�Ŋz �@�@�y�n�E���� (�]��ʂɂ�鉿�z�j �@�B���u�@�@ �� �@�@�@�@��b�T���z {�i4,000 ���~ �{ 1,000 ���~ �| 2,000 ���~�j�| 110 ���~ }×45���|265 ���~��1,035.5 ���~ ⑶ �\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz ⑴ �| ⑵ �� 494.5 ���~ �S �Ȃ��A���^�҂����S�����ꍇ�ɂ́A�P�\�Ŋz�͖Ə������ƂƂ��Ɂi�[�u�@ 70 �̂U�̂W�M��j�A ���̗P�\�Ŋz�ɑΉ����������Ɨp���Y�ɂ��ẮA���᎖�Ǝ҂��A���̑��^�҂��瑊 �����͈②�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���A���̓�����Ɨp���Y�̑��^���̉��z�ɂ�葊�� �ł̌v�Z���s�����ƂƂ���Ă��邪�i�[�u�@ 70 �̂U�̂X�j�A�[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z�ɓ��� ��T�����ꂽ��������ꍇ�ɂ́A�������͈②�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���������Ɨp���Y�̉��z�́A���̎Z���ɂ��v�Z�������z�ƂȂ�i�[�u�@�� 40 �̂V�� 10㉟�Z�j�B �i�Z���j ������Ɨp���Y�̉��z×(�`−�a)�^�` (��) �P �u������Ɨp���Y�̉��z�v�́A���̈����Ȃ����̂Ƃ����ꍇ�̉��z�ɂ��B �Q ��L�Z�����̕����͎��̂Ƃ��� �`���[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z�ɌW�������Ɨp���Y�̉��z�̍��v�z �a���[�ŗP�\���̑��^�Ŋz�̌v�Z�ɂ����čT�����ꂽ���̋��z �R ��̎���̏ꍇ�ɁA�b�̎��S�̎��ɂ����đ������͈②�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���������Ɨp���Y�̉��z�͎��̂Ƃ���i�b�̎��S�̎��܂łɔ[�ŗP�\�̊����̊m�肪�Ȃ������ꍇ�j�B �i4,000 ���~�{1,000 ���~�j ×{ (4,000 ���~�{1,000 ���~)- 2,000 ���~}�^( 4,000 ���~�{1,000 ���~) �� 3,000 ���~ �s�l�̎��Ɨp���Y�ɂ��Ă̑����ł̔[�ŗP�\�y�іƏ��W�t �i�� 26�j�����ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z���@�i���̂P�j�F�ʏ�̏ꍇ
�i���j ���̂Ƃ���B
�i����j �P �u�����ł̔[�ŗP�\�v�ł́A���᎖�Ƒ����l�����擾�������Y�͓��᎖�Ɨp���Y�݂̂ł���Ƃ��āA���̉��z�Y���᎖�Ƒ����l���ɌW�鑊���ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��āi���̑����l���ɂ��ẮA���̎҂��擾�����S�Ă̍��Y�̉��z�ɂ��B�j�v�Z�������Y���᎖�Ƒ����l���ɌW�鑊���Ŋz���A�[�ŗP�\���̑����Ŋz�ƂȂ�i�[�u�@ 70 �̂U�� 10�A�O�j�A����ƁA�ʏ�̌v�Z���@�i�����l�����擾�����S�Ă̍��Y�̉��z�ɂ��B�j�ɂ�铖�Y���᎖�Ƒ����l���ɌW�鑊���ł̊z�Ƃ̍��z���A���Y���᎖�Ƒ����l�����\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz�ƂȂ�B �@�܂��A���᎖�Ƒ����l���ȊO�̎҂ɂ��ẮA�����l�����擾�����S�Ă̍��Y�Ɋ�Â��v�Z�������z���A���̎҂̑����Ŋz�ƂȂ�B �Q ���������āA��̎���ł́A���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ �w�y�тx���擾�����S�Ă̍��Y�Ɋ�Â��w�y�тx�̎Z�o�Ŋz�̌v�Z �@ �ېʼn��i�̍��v�z �i�R���~�i���Ɨp���Y�j�{�Q���~�i���̑��j�j�y�w�̎擾���Y�z�{�T���~�y�x�̎擾���Y�z��10 ���~ �A �ېň�Y���z �@�@ �| 4,200 ���~�i��b�T���z���j�� �X�� 5,800 ���~ ���u3,000 ���~�{�@�葊���l�̐�×600 ���~�v�ɂ��B�Ȃ��A��̎���ł́A�@�葊���l�̐��͂w�y�тx�� �Q�l�ł��邽�߁A��b�T���z�� 4,200 ���~�ƂȂ�i�ȉ��A�� 27 �܂łɂ����ē����B�j�B �B �A�̋��z�Ɋ�Â������ł̑��z �@�R�� 9,500 ���~ �C �e�l�̎Z�o�Ŋz �w�F �B × �T���~/10 ���~ �� �P�� 9,750 ���~ �x�F �B × �T���~/10 ���~ �� �P�� 9,750 ���~ ⑵ �w�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz�i�w���擾�������Y�͎��Ɨp���Y�݂̂Ƃ��Čv�Z�j �@ �ېʼn��i�̍��v�z �R���~�y�w�̎擾���Y�F���Ɨp���Y�z �{ �T���~�y�x�̎擾���Y�z�� �W���~ �A �ېň�Y���z �@ �| 4,200 ���~�i��b�T���z�j�� �V�� 5,800 ���~ �B �A�̋��z�Ɋ�Â������ł̑��z �Q�� 9,500 ���~ �C �w�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz �B × �R���~/�W���~ �� �P�� 1,062.5 ���~ ⑶ �\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz �w�F�P�� 9,750 ���~ �| �P�� 1,062.5 ���~ ��8,687.5 ���~ �x�F�P�� 9,750 ���~ �R �Ȃ��A��L�̌v�Z�́A��̓��᎖�Ƒ����l�����擾�������᎖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�Ƃ���������ꍇ�����l�ł���B �i�� 27�j�����ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z���@�i���̂Q�j�F���᎖�Ƒ����l������������ꍇ
�i���j �w�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz�́A�w�ɂ��Ă͂`���Ɨp���Y�̉��z�����̑����ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ��āi�x�ɂ��ẮA�擾�����S�Ă̍��Y�̉��z�ɂ��B�j�v�Z���������Ŋz�ɂ��B �܂��A�x�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz�́A�x�ɂ��Ă͂a���Ɨp���Y�̉��z�����̑����ł̉ې� ���i�Ƃ݂Ȃ��āi�w�ɂ��ẮA�擾�����S�Ă̍��Y�̉��z�ɂ��B�j�v�Z���������Ŋz�ɂ��B �Ȃ��A��̎���̗P�\�Ŋz���́A���̂Ƃ���ƂȂ�B
|
| �i����j �P ���᎖�Ƒ����l���ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz�̌v�Z�͖� 26 �̂Ƃ���ł���Ƃ���A�푊���l �ɌW����᎖�Ƒ����l�����Q�ȏ゠��ꍇ�ɂ����邻�̌v�Z�́A���ꂼ��̓��᎖�Ƒ����l���� �Ƃɍs�����ƂƂȂ�B �Q �܂�A������᎖�Ƒ����l���ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz�̌v�Z���s���ꍇ�ɂ́A���̎҂� ���Ă͓��᎖�Ɨp���Y�̉��z�������ł̉ېʼn��i�Ƃ݂Ȃ���邪�A���̓��᎖�Ƒ����l���ɌW ��ېʼn��i�́A���̎҂��擾�����S�Ă̍��Y�Ɋ�Â����̂ƂȂ�B �R ���������āA��̎���ł́A���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ �w�y�тx���擾�����S�Ă̍��Y�Ɋ�Â��w�y�тx�̎Z�o�Ŋz�̌v�Z �@ �ېʼn��i�̍��v�z �i�R���~�i�`���Ɨp���Y�j�{�Q���~�i���̑��j�j�y�w�̎擾���Y�z �{�i�Q���~�i�a���Ɨp���Y�j�{�R���~�i���̑��j�j�y�x�̎擾���Y�z�� 10 ���~ �A �ېň�Y���z �@ �| 4,200 ���~�i��b�T���z�j�� �X�� 5,800 ���~ �B �A�̋��z�Ɋ�Â������ł̑��z �R�� 9,500 ���~ �C �e�l�̎Z�o�Ŋz �w�F �B × �T���~/10 ���~ �� �P�� 9,750 ���~ �x�F �B × �T���~/10 ���~ �� �P�� 9,750 ���~ ⑵ �e�l�̔[�ŗP�\���̑����Ŋz �@ �w�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz�i�w���擾�������Y�͂`���Ɨp���Y�݂̂Ƃ��Čv�Z�j �C �ېʼn��i�̍��v�z �R���~�y�w�̎擾���Y�F�`���Ɨp���Y�z �{ �T���~�y�x�̎擾���Y�z�� �W���~ �� �ېň�Y���z �C �| 4,200 ���~�i��b�T���z�j�� �V�� 5,800 ���~ �n ���̋��z�Ɋ�Â������ł̑��z �Q�� 9,500 ���~ �j �w�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz �n × �R���~/�W���~ �� �P�� 1,062.5 ���~ �A �x�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz�i�x���擾�������Y�͂a���Ɨp���Y�݂̂Ƃ��Čv�Z�j �C �ېʼn��i�̍��v�z �T���~�y�w�̎擾���Y�z �{ �Q���~�y�x�̎擾���Y�F�a���Ɨp���Y�z�� �V���~ �� �ېň�Y���z �C �| 4,200 ���~�i��b�T���z�j�� �U�� 5,800 ���~ �n ���̋��z�Ɋ�Â������ł̑��z �Q�� 4,500 ���~ �j �x�ɌW��[�ŗP�\���̑����Ŋz �n × �Q���~/�V���~ �� 7,000 ���~ ⑶ �\�������܂łɔ[�t���ׂ��Ŋz �w�F�P�� 9,750 ���~ �| �P�� 1,062.5 ���~ �� 8,687.5 ���~ �x�F�P�� 9,750 ���~ �| 7,000 ���~ �� �P�� 2,750 ���~ �i�� 28�j�����ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z���@�i���̂R�j�F�T�����ׂ���������ꍇ
�i���j �P�\�Ŋz���v�Z����ꍇ�̓��᎖�Ɨp���Y�̉��z�� 7,000 ���~�ƂȂ�B �i����j �P �u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����ꍇ�̗P�\�Ŋz�̌v�Z�͖� 26 �̂Ƃ���ł��邪�A���̓K �p������᎖�Ƒ����l���ɂ��đ����Ŗ@�� 13 ���̋K��ɂ��T�����ׂ���������ꍇ�ɂ́A�P�\�Ŋz�̌v�Z�̊�b�ƂȂ���᎖�Ɨp���Y�̉��z�́A���̉��z���������z���T�������c�z�i�ȉ��u���艿�z�v�Ƃ����B�j�ɂ�邱�ƂƂ���Ă���i�[�u�@�� 40 �̂V�� 10�H�j�B �Q �����āA���́u������z�v�Ƃ́A���̎Z���ɂ��v�Z�������z���������ƂƂ���Ă���i�[�u �@�� 40 �̂V�� 10�I�j�B (Ⓐ �[ Ⓑ �{ Ⓒ) Ⓐ = �� �[ ���Ɗ֘A���� Ⓑ �� ���᎖�Ƒ����l�����擾�������̑��̍��Y�̉��z © �� ���Ɗ֘A���� �i���j �P �u���Ɗ֘A�����v�Ƃ́A�����Ŗ@�� 13 ���̋K��ɂ��T�����ׂ����᎖�Ƒ����l���̕��S�ɑ����� ���̂����A���᎖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�ƂɊւ�����ȊO�̍��ł��邱�Ƃ����K�̑ݕt�ɌW��_�� �̏��ʂɂ�薾�炩�ɂ���Ă�����̈ȊO�̍��������B �Q Ⓐ�|Ⓑ���O�̏ꍇ�ɂ͂O�B �R ��̎���ł́A���Ɗ֘A������ 3,000 ���~�i��4,000 ���~�|1,000 ���~�j�ł���Ƃ���A��L �Q�̎Z���ɂ��v�Z����������z�� 3,000 ���~�ƂȂ邽�߁A�����ł̗P�\�Ŋz���v�Z����ꍇ�̓��᎖�Ɨp���Y�̉��z�i���艿�z�j�� 7,000 ���~�i���P���~�|3,000 ���~�j�ƂȂ�B �i�Q�l�j�T�����ׂ���������ꍇ�̓��艿�z�̌v�Z�C���[�W�i���j �i�� 29�j�����ł̔[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z���@�i���̂S�j�F�㏞�������������ꍇ
�i���j �@�㏞���Y�̉��z��㏞���Y�̌�t�������҂��������͈②�ɂ��擾�������ꂼ��̑������Y�̉��z�̊����ɂ�肠���A���ꂼ��̑������Y�̉��z���瓖�Y����̑㏞���Y�̉��z���T��������@�ɂ�邱�Ƃ������I�Ȍv�Z���@�ƍl�����邪�A�@�ߏ���i�̍T�����@�͒�߂��Ă��� ���̂ŁA�㏞���Y�̉��z�𑊑��ł̔[�ŗP�\�̓���̓K�p���Ȃ����Y�̉��z����D��I�ɍT�����v�Z���č����x���Ȃ��B �i����j �P �u�㏞�����v�Ƃ́A���������l���͕���҂̂����P�l���͐��l���������͕�②�ɂ��擾�������Y�̌������擾���A���̌������擾�����҂����̋��������l���͕���҂ɑ��� ���S���镪���̕��@�������̂ł��邪�A�㏞�����̕��@�ɂ���Y�������s���A�㏞���Y�̌�t�����Ă���ꍇ�̓��Y�㏞���Y�̌�t�������҂ɌW�鑊���ł̉ېʼn��i�̌v�Z�ɂ��� �́A�����Ŗ@��{�ʒB 11 �̂Q�|�X((�㏞�������s��ꂽ�ꍇ�̉ېʼn��i�̌v�Z))�ɂ��A�u�������͈②�ɂ��擾���������̍��Y�̉��z�����t�������㏞���Y�̉��z���T���������z�v�Ƃ��Ă���B �Q ����́A�������Y�������Ŏ擾�����҂ɂ��ẮA���@�� 909 ���̋K��ɂ�肻�̎擾�����������Y�̌��������ڔ푊���l���珳�p�擾�������̂Ƃ���A�܂��ɂ��̎擾�����������Y���̂��̂��������͈②�ɂ��擾�������Y�ƂȂ�Ƃ��Ă��A���̍��Y�̂����ɂ́A�㏞���Y�̌�t����҂̂��̑㏞���Y�̉��z���������Ă�����̂ƌ��킴��Ȃ����Ƃ���A���ʒB�ɂ����ẮA�㏞���Y����t�����҂ɂ��ẮA�����ł̉ېʼn��i�̌v�Z��̋Z�p�I�[�u�Ƃ��āA�擾�����������Y�̌����̉��z���炻�̑㏞���Y�̉��z���T�����Ă���Ƃ���ł���B �R �����āA���̂��Ƃ́u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����҂��㏞���Y�̌�t�������҂ł��� �ꍇ�����l�ł��邱�Ƃ���A���̎҂ɌW�鑊���Ŋz�y�є[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z�ɓ������Ă��A���ʒB�ɂ�邱�ƂƂȂ�B �S �������Ȃ���A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����҂��㏞���Y�̌�t�������҂ł���ꍇ�ŁA�������͈②�ɂ��擾���������Y�̒��ɔ[�ŗP�\�̓K�p������莖�Ɨp���Y�Ƃ���ȊO�̍��Y�Ƃ�����ꍇ�ɂ����āA�[�ŗP�\�̓K�p����҂ɌW�鑊���ł̉ېʼn��i�̌v�Z���@�ɂ��ẮA�@�ߏ���i�̒�߂͂Ȃ��B �T ���̌v�Z���@�ɂ��ẮA �@ �㏞���Y�Ƃ��Č�t���������Y�̉��z��[�ŗP�\�̓K�p������莖�Ɨp���Y�̉��z����D��I�ɍT��������@ �A �㏞���Y�Ƃ��Č�t���������Y�̉��z��[�ŗP�\�̓K�p������莖�Ɨp���Y�ȊO�̍��Y�̉��z����D��I�ɍT��������@ �B ��t�������㏞���Y�̉��z��㏞���Y�̌�t�������҂��������͈②�ɂ��擾���������ꂼ��̍��Y�̉��z�ɂ�肠���A���ꂼ��̍��Y�̉��z���瓖�Y����̑㏞���Y�̉��z ���T��������@ �̂����ꂩ���l�����邪�A����̌������Y�Ƒ㏞���Y�Ƃ��Ђ��t���ɂȂ��Ă��炸�A�������Y�S�̂ɑ��đ㏞�������s��ꂽ�ꍇ�ɂ́A���ꂼ��̑������Y�ɑ��㏞���Y�̉��z���ϓ��ɍ������Ă���Ƃ���̂��ł������I�ȍl�����ł���ƍl������B �U �������A��L�S�̂Ƃ���A�[�ŗP�\�̓K�p������莖�Ɨp���Y�Ƃ���ȊO�̍��Y�Ƃ�����ꍇ�̑㏞���Y�̉��z�̍T�����@�ɂ��Ė@�߂ɂ����Ē�߂��Ă��Ȃ��ȏ�A�B�̕��@�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��閾�m�ȍ����͂Ȃ��A�܂��A�[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z��A�[�ŗP�\�̓K�p������莖�Ɨp���Y�̉��z���傫�������P�\�Ŋz���傫���Ȃ邱�Ƃ��炷��A�[�ŗP�\�̓K�p������莖�Ɨp���Y�ȊO�̍��Y�̉��z����D��I�ɑ㏞���Y�̉��z���T�����Đ\�����Ȃ���Ă� ���Ƃ��Ă��A�����F�߂č����x���Ȃ����̂ƍl����B �V ��̎���ł́A�q�w�́A�����ɂ����莖�Ɨp���Y�i�P���~�j�̂ق��A���̑��̍��Y�i2,000 �� �~�j���擾�������A�㏞���Y�i6,000 ���~�j����t���Ă���B �@���������āA�㏞���Y�̉��z 6,000 ���~�̂����A2,000 ���~��[�ŗP�\�̓K�p���Ȃ����̑��̍��Y�̉��z����T�����A���̎c�z 4,000 ���~����莖�Ɨp���Y�̉��z�i�P���~�j����T�����A���̍T��������̉��z�i6,000 ���~�j�Ɋ�Â��A�ʏ�̑����Ŋz�y�є[�ŗP�\�Ŋz�̌v�Z���s���č����x���Ȃ����ƂƂȂ�B (�Q�l) �@��t�������㏞���Y�̉��z�𑊑��ɂ��擾�������ꂼ��̍��Y�̉��z�ɉ����Ă��� ������@�i��L�T�B�̕��@�j�ɂ�����ꍇ�̊e���Y�̉��z �@���̂Ƃ���A�ʏ�̑����ł̌v�Z�ɂ�����q�w�̉ېʼn��i�� 6,000 ���~�ƂȂ�A��L�V�Ɠ��l�ł��邪�A�P�\�Ŋz���v�Z����ꍇ�̎q�w�̉ېʼn��i�� 5,000 ���~�ƂȂ�A��L�V�ɔ� �������邽�߁A�P�\�Ŋz���������邱�ƂƂȂ�B �E ���莖�Ɨp���Y�F�P���~ �| 6,000 ���~ × �P���~ �^�i�P���~�{2,000 ���~�j �� 5,000 ���~ �E ���̑��̍��Y�F2,000 ���~ �| 6,000 ���~ × 2,000 ���~�^ �i�P���~�{2,000 ���~�j �� 1,000 ���~ (�� 30�j���K�͑�n���̓���̓K�p����҂�����ꍇ�i���̂P�j�F���x�ʐϓ�
�i���j ���̂Ƃ���B �@ ����@�̏ꍇ�E�E�E�q�w�͂`���ƂɌW�鎖�Ɨp���Y�̑S�Ăɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �A ����A�̏ꍇ�E�E�E300 �u �B ����B�̏ꍇ�E�E�E260 �u �C ����C�̏ꍇ�E�E�E400 �u �i����j �P �u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ��n���ɂ� 400 �u�̌��x�ʐς��݂����Ă��邪�A���̑����ɌW��푊���l���瑊�����͈②�ɂ��擾��������n���ɂ��āu���K�͑�n���̓���v�̓K�p����҂�����ꍇ�ɂ́A���̓K�p����[�u�@�� 69 ���̂S��P���ɋK�肷�鏬�K�͑�n���i�ȉ��u���K�͑�n���v�Ƃ����B�j�̋敪�ɉ����A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ��n���̖ʐϓ��́A���̂Ƃ���ƂȂ�i�[�u�@ 70 �̂U�� 10�A��C�A��w�A�[�u�@�� 40 �̂V�� 10�F�j�B
�� �P ���ɑݕt���Ɨp��n���ɂ��ď��K�͑�n���̓���̓K�p����ꍇ�ɂ́A�n�ɂ��B �Q α�͓��苏�Z�p��n���̖ʐρAβ�͓��蓯����Ў��Ɨp��n���̖ʐρAγ�͑ݕt���Ɨp��n���̖ʐρB �Q ���������āA��̎���ɂ��ẮA���̂Ƃ���ƂȂ�B ⑴ ����@ �@�q�x�����K�͑�n���̓���̓K�p���邂��n�́u���莖�Ɨp��n���v�ł��邽�߁A�q�w�͂���n�����łȂ��A�`���ƂɌW�鎖�Ɨp���Y�̑S�Ăɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�� �邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂȂ�B ⑵ ����A �@�q�x�����K�͑�n���̓���̓K�p���邃��n�i100 �u�j�́u���蓯����Ў��Ɨp��n���v�ł��邽�߁A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ��n���̌��x�ʐς́A300 �u�i��400 �u�|100 �u�j�ƂȂ�B ⑶ ����B �@�q�x�����K�͑�n���̓���̓K�p���還��n�i70 �u�j�́u�ݕt���Ɨp��n���v�ł��邽�߁A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ��n���̌��x�ʐς́A260 �u�i��400 �u�|�Q×70 �u�j�ƂȂ�B ⑷ ����C �@�q�x�����K�͑�n���̓���̓K�p���邅��n�i99 �u�j�́u���苏�Z�p��n���v�ł��邽�߁A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ��n���̌��x�ʐς́A400 �u�ƂȂ�B �R �Ȃ��A�푊���l����u�����ł̔[�ŗP�\�v�̑ΏۂƂȂ��n�����́u���K�͑�n���̓���v�̑ΏۂƂȂ��n���𑊑����͈②�ɂ��擾�����҂���l�łȂ��ꍇ�ɂ́A�����̑�n�����擾�����S�Ă̎҂́A�����̐��x�̓K�p������̂̑I���ɂ��Ă̓��ӂ����鏑�ނ��A�����ł̐\�����ɓY�t���邱�ƂƂ���Ă���i�[�u�@�� 40 �̂Q�D�O�A�[�u�@�K�� 23 �̂W�̂X�M���j�B |
| �i�Q�l�j�����̑�n���ɂ��ď��K�͑�n���̓���̓K�p�����ꍇ�̌��x�ʐς̌v�Z�� ��̎���ɂ����āA�q�x�������̑�n���ɂ��ď��K�͑�n���̓���̓K�p�����ꍇ�̌��x�ʐς͎��̂Ƃ���ƂȂ�B
����n�i���蓯����Ў��Ɨp��n���j�F100 �u ����n�i�ݕt���Ɨp��n���j �F 70 �u ����n�i���苏�Z�p��n���j �F 99 �u ���Q ����n�i���莖�Ɨp��n���j�ɂ��ď��K�͑�n���̓���̓K�p����ꍇ�A���ɏ��K�͑�n���̓���̓K�p�����n�̋敪�ɂ�����炸�A�q�w�͎��Ɨp���Y�̑S�Ăɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �s�l�̎��Ɨp���Y�̑��^�҂����S�����ꍇ�̑����ł̉ېł̓���W�t �i�� 33�j�T�v
�i���j �@�b�̎��S�ɂ��A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���������Ɨp���Y�ɂ��ẮA�w���b���瑊���ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���A���^���̉��z�ɂ�葊���ł̉ېőΏۂƂȂ����A���v�̗v���������Ƃɂ��A���Y������Ɨp���Y�ɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł����B �@�Ȃ��A�b�̎��S�ɂ��A�[�ŗP�\����Ă������^�ł͖Ə�������B �i����j �P �u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p������᎖�Ǝ҂ɌW�鑡�^�ҁi�O�̑��^�҂��܂ށB�j�����S�����ꍇ�ɂ́A���̓K�p���������Ɨp���Y�i�[�u�@��70���̂U�̂W��T����R�����͑�U���̋K��ɂ�������Ɨp���Y�Ƃ݂Ȃ��ꂽ���̂��܂݁A�P�\�����^�Ŋz�ɑΉ����镔���Ɍ���B�j�́A���̎҂̎��S�ɂ�鑊���łɂ��ẮA���Y���᎖�Ǝ҂����Y���^�҂��瑊���i���Y���᎖�Ǝ҂����Y���^�҂̑����l�ȊO�̎҂ł���ꍇ�ɂ́A�②�j�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���A���^�i�O�̑��^�҂̎��S�̏ꍇ�͑O�̑��^�j�̎��i�[�u�@��70���̂U�̂W��18���̋K��ɂ��Ə������ꍇ�ɂ́A�����ɋK�肷��F������j�̉��z�ɂ�葊���ł̉ېőΏۂƂȂ�i�[�u�@70�̂U�̂X�j�B �i���j �P�@ �u�O�̑��^�ҁv�Ƃ́A���Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ����A���ꂼ��ɒ�߂�҂ɓ��莖�Ɨp���Y�̑��^�������҂������i�[�u�@70�̂U�̂W�@�A�[�u�@��40�̂V�̂W�B�j�B �C�@ ���^�҂ɑ���[�u�@��70���̂U�̂W��P���̋K��̓K�p�ɌW�鑡�^���A�����14����R���̑��^�i�Ə��Ώۑ��^�j�ł���ꍇ �Ə��Ώۑ��^�������҂̂����ŏ��ɑ[�u�@��70���̂U�̂W��P���̋K��̓K�p������ ���@ �C�Ɍf����ꍇ�ȊO�̏ꍇ ���^�� �Q�@ �u�O�̑��^�v�Ƃ́A(��)�P�̃C���̓��Ɍf����ꍇ�̋敪�ɉ����A���ꂼ��ɒ�߂�҂ɑ��铖�Y������Ɨp���Y�̑��^�������B �Q�@ ���̍ہA�s���{���m���́u�~�����@�̊m�F�v�i�~�����ȗ�13�E�`�J�j����ȂǏ��v�̗v���������Ƃ��́A���Y���᎖�Ǝ҂͓��Y������Ɨp���Y�ɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł���B �R �Ȃ��A���^�҂̎��S�ɂ��A�[�ŗP�\����Ă������^�ł͖Ə�����邱�ƂƂȂ�i�[�u�@70�̂U�̂W�M��j�B �i�� 34�j�K�p�����̗L��
�i���j �@�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ�ɂ�����u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɂ��ẮA�K�p�����݂͐����Ă��Ȃ��B �i����j �P�@�u�����ł̔[�ŗP�\�v�ł́A�[�u�@��70���̂U��10��P���ɂ����āA���̑ΏۂƂȂ鑊�����͈②�ɂ��āA�����Ƃ��āA����31�N�P���P������ߘa10�N12��31���܂ł̊Ԃ̂��̂Ɍ���|�K�肵�Ă���B �Q�@ �������A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ�ɂ́A�[�u�@��70���̂U��10��30���ɂ����ē����P���̓ǑK�肪�݂����Ă���A���́u����31�N�P���P������ߘa10�N12��31���܂ł̊ԁv�̎擾�Ƃ����v���͕s�v�Ƃ���Ă��邱�Ƃ���A���Y���Ԍ�ɑ��^�҂����S�����ꍇ�ɂ����Ă����Y���^�҂ɌW����᎖�Ǝ҂͑[�u�@��70���̂U�̂X�̋K��ɂ�蓖�Y���^�҂��瑊�����͈②�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ������Ɨp���Y�ɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂȂ�B �R�@ �Ȃ��A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���Ă������᎖�Ǝ҂��u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����ꍇ�ɂ́A�~�����ȗߑ�13���U���i�����W���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j���͑�X���i�����11���ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j�̋K��ɂ��s���{���m���̊m�F����K�v�����邪�i�[�u�@70�̂U��10�A��g�A�[�u�@�K��23�̂W�̂X�C�A㉙�j�A���̏ꍇ�̑����ɌW��u�l���Ə��p�v��v�̓s���{���m���ւ̒�o���͕s�v�ł���B �i�� 35�j���K�͑�n���̓���Ƃ̓K�p�W
�i���j �@�ɂ��āF �q�x�́A�a��n�ɂ��ē��莖�Ɨp��n���ɌW��u���K�͑�n���̓���v�̓K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �A�ɂ��āF �`��n 250 �u�̂��� 100 �u�܂ł��u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ�B �i����j �P �@�ɂ��� ⑴ �[�u�@��69���̂S��U���́A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�������᎖�Ǝ҂ɌW�鑡�^�҂��瑊�����͈②�ɂ��擾�������莖�Ɨp��n���y�сu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�������᎖�Ƒ����l���ɌW��푊���l���瑊�����͈②�ɂ��擾�������莖�Ɨp��n���ɂ��ẮA�u���K�͑�n���̓���v�̓K�p���Ȃ��|�K�肵�Ă���B ⑵ ���������āA��̎���̎q�x�́A�a��n�ɂ��āu���K�͑�n���̓���v�̓K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����ƂƂȂ�B �Q �A�ɂ��� ⑴ ���᎖�Ǝ҂��A�[�u�@��70���̂U�̂X�̋K��ɂ��u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�҂��瑊�����͈②�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ������Ɨp���Y�ɂ��āu�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p����ꍇ�ɂ������A���Y���^�҂��瑊�����͈②�ɂ��擾�������Y�ɂ����u���K�͑�n���̓���v�̓K�p����҂�����Ƃ����A���Y������Ɨp���Y�̂�����n���ɊY��������̂ɂ��ẮA���^�ł̐\�����ɋL�ڂ��ꂽ���Y��n���̖ʐς̂���400�u�����[�u�@�ߑ�40���̂V��10��V������߂�ʐς��T�������ʐςɒB����܂ł̕����Ɍ���A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p���邱�Ƃ��ł������ƂƂ���Ă���i�[�u�@��40�̂V��10㉟�O�j�B (��)�u�[�u�@�ߑ�40���̂V��10��V���ɒ�߂�ʐρv�ɂ��ẮA��30���Q�ƁB ⑵ ��̎���ł́A�q�y���ݕt���Ɨp��n���ɊY������b��n�i150�u�j�ɂ��āu���K�͑�n���̓���v�̓K�p���邽�߁A�u�[�u�@�ߑ�40���̂V��10��V���ɒ�߂�ʐρv��300�u�i���Q×150�u�j�ƂȂ�A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ��n���́A���^�ł̐\�����ɋL�ڂ����`��n�̖ʐ�250�u�̂����A100�u�i��400�u�|300�u�j�܂ł̕����ƂȂ�B �i�� 36�j������Ɨp���Y�ɌW�鑡�^�����������Z�ېł̓K�p�ɌW�鑡�^�ł���ꍇ�ɂ����đ��^�҂����S�����ꍇ�̎戵���i���̂P�j�F�m��Ŋz������ꍇ
�i���j ⑴�@ ���ɔ[�ŗP�\�̓K�p���Ă��鎖�Ɨp���Y �@���Y���Ɨp���Y�ɂ��Ă��A�[�u�@�� 70 ���̂U�̂X�� 1 ���̋K��ɂ��A�q�w���b���瑊���ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���A���^���̉��z�i8,000 ���~�j�ɂ�葊���ł̉ېőΏۂƂȂ��B �@�Ȃ��A���Y���Ɨp���Y�́A���v�̗v���������ꍇ�ɂ́A�u�����ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ΏۂƂȂ��B ⑵�@ ���n�������Ɨp���Y ���Y���Ɨp���Y�ɂ��Ă��A�����Ŗ@�� 21 ���� 15 �̋K��ɂ��A�q�w���b���瑊���ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���A���^���̉��z�i2,000 ���~�j�ɂ�葊���ł̉ېőΏۂƂȂ��B �@ �܂��A�[�ŗP�\�̊����������������^�Ŋz�i300 ���~�j�́A�����Ŋz����T������A�T��������Ȃ��������z�͊ҕt��������ƂƂȂ�B �i����j �P�@ �u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ�i�[�u�@�� 70 ���̂U�̂X��Q���̋K��̓K�p������ꍇ�������B�j�ɂ́A����܂Ŕ[�ł̗P�\���Ă������^�ł͖Ə�����i�[�u�@70 �̂U�̂W�M��j�A���̖Ə������[�ŗP�\�Ŋz�ɌW�������Ɨp���Y�́A�����P���̋K��ɂ����᎖�Ǝ҂����Y���^�҂��瑊���i���Y���᎖�Ǝ҂����Y���^�҂̑����l�ȊO�̎҂ł���ꍇ�ɂ́A�②�j�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ���A�����ł��ېł���邱�ƂƂȂ�i�[�u�@ 70 �̂U�̂X�@�j�B �Q�@ �������A���̋K��̓K�p�����������Ɨp���Y�͓��Y���^�҂̎��S�̎��ɂ����đ[�u�@��70 ���̂U�̂W��P���̋K��̓K�p���Ă�����̂Ɍ�����̂ł����āA���Y���^�҂̎��S�̓��O�ɂ��̑S�����͈ꕔ�ɂ��Ĕ[�ŗP�\�ɌW��������m�肵�����^�łɑΉ����������Ɨp���Y�ɂ��ẮA�[�u�@�� 70 ���̂U�̂X��P���̋K��͓K�p����Ȃ��B �R�@ �����Ƃ��A���������Z�ېœK�p�҂ɌW�鑡�^�ҁi���葡�^�ҁj�����S�����ꍇ�ɂ����āA���葡�^�҂��瑊�����͈②�ɂ����Y���擾�����Ƃ��́A�����Ŗ@�� 21 ���� 15 �̋K��ɂ��A���Y���葡�^�҂���̑��^�ɂ��擾�������Y�ő��������Z�ېł̓K�p������̂̉��z�𑊑��ł̉ېʼn��i�ɉ��Z���A���葡�^�҂��瑊�����͈②�ɂ����Y���擾���Ȃ������ꍇ�ɂ́A���@�� 21 ���� 16 �̋K��ɂ��A���Y���葡�^�҂���̑��^�ɂ��擾�������Y�ő��������Z�ېł̓K�p������̂Y���葡�^�҂��瑊���i���Y���������Z�ېœK�p�҂����Y���葡�^�҂̑����l�ȊO�̎҂ł���ꍇ�ɂ́A�②�j�ɂ��擾�������̂Ƃ݂Ȃ��āA���ꂼ�ꑊ���ł̌v�Z�����邱�ƂƂ���Ă���B �i��) ���葡�^�҂���̑��^�ɂ��擾�������Y�ł����Ă��A���Y���葡�^�҂̎��S�ɂ��[�u�@�� 70 ���̂U�̂W�� 14 ����Q���̋K��ɂ��Ə����ꂽ�P�\�����^�Ŋz�ɑΉ����������Ɨp���Y�ɂ��ẮA�����Ŗ@�� 21 ���� 14 ����� 21 ���� 16 �܂ł̋K��͓K�p���Ȃ����ƂƂ���Ă���i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�L�Z�j�A��L�P�̑[�u�@�� 70 ���̂U�̂X�̋K��݂̂��K�p����邱�ƂɂȂ�B �S�@ ���������āA�[�ŗP�\�̓K�p�ɌW�鑡�^�҂����S�����ꍇ�ɂ����āA���Y���^�҂̎��S�̓��O�ɁA���Y�[�ŗP�\�ɌW�鑡�^�ł̑S�����͈ꕔ�ɂ��Ă̔[�ŗP�\�̊������m�肵�Ă���Ƃ��ɂ����铖�Y�����̊m��ɌW�������Ɨp���Y�́A�����Ŗ@�� 21 ���� 15 ���͑� 21 ���� 16 �̋K��ɂ��A���^�̎��ɂ����鉿�z�ő����ł��ېł���邱�ƂɂȂ�B �@���̏ꍇ�A���Y�[�ŗP�\�̊����̊m�肵�����^�łɂ��ẮA�����ł���T������i���@ 21 ��16�B�A21 �� 16�C�j�A�T��������Ȃ��������z�ɂ��Ă͊ҕt����邱�ƂƂȂ�i���@ 33 �̂Q�j�B |
�i�� 37�j������Ɨp���Y�ɌW�鑡�^�����������Z�ېł̓K�p�ɌW�鑡�^�ł���ꍇ�ɂ����đ��^�҂����S�����ꍇ�̎戵���i���̂Q�j�F�Ə��Ŋz������ꍇ
�i���j �@���Y���Ɨp���Y�ɂ��Ă��A�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W�� 17 ���̋K��ɂ���Ə������P�\�Ŋz�ɑΉ����镔���i1,500 ���~���j�������A�����Ŗ@�� 21 ���� 15 �̋K��Ɋ�Â��A���^���̉��z�i�P���~�|1,500 ���~��8,500 ���~�j�ɂ��A�����ł̉ېőΏۂƂȂ��B �@�܂��A�[�ŗP�\�̊����������������^�Ŋz�i1,200 ���~�j�́A�����Ŋz����T�������A�T��������Ȃ��������z�͊ҕt��������ƂƂȂ�B �� �i�P���~�|8,000 ���~�j× 300 ���~�^(300 ���~�{100 ���~) ��1,500 ���~ �i����j �P�@ �� 36 �̂Ƃ���A�u���^�ł̔[�ŗP�\�v�̓K�p�ɌW�������Ɨp���Y�̑��^�����������Z�ېł̓K�p�ɌW�鑡�^�ł���ꍇ�ɂ����āA���Y���^�ɌW�鑡�^�ҁi���葡�^�ҁj�����S�����Ƃ��́A���ɔ[�ŗP�\�̓K�p���Ă��Ȃ�������Ɨp���Y�ɂ��ẮA�����Ŗ@�� 21 ���� 15���͑� 21 ���� 16 �̋K��ɂ��A���^���̉��z�ɂ�葊���ł̉ېőΏۂƂȂ�B �Q�@ �������A�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W�� 13 ����U���́A���᎖�Ǝ҂������ 14 ���A�� 16 ������� 18 ���܂ł̋K��ɂ��P�\�Ŋz�̖Ə����Ă���ꍇ�ɂ́A������Ɨp���Y�̂������̖Ə������P�\�Ŋz�ɑΉ����镔���ɂ��Ă͑����Ŗ@�� 21 ���� 14 ����� 21 ���� 16 �܂ł̋K��͓K�p���Ȃ��|�K�肵�Ă��Ă���A���Y�����ɂ��Ă͑����ł̉ېőΏۂƂȂ�Ȃ����� �ƂȂ�B �R�@ �����āA�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W�� 17 ���̋K��ɂ��Ə��i���z�Ə��j�̓K�p�����ꍇ�́u������Ɨp���Y�̂����Ə������P�\�Ŋz�ɑΉ����镔���v�Ƃ͎��̎Z���ɂ��v�Z�������z�ɑ������镔�����Y�����邱�ƂƂȂ�i�[�u�� 70 �̂U�̂W�|57⑹�j�B �i�Z���j �i�`�|�a�j× �b�^(�b�{�c) (��)�P �@��L�Z�����̕����͎��̂Ƃ���B �`�����Y������Ɨp���Y�̑��^���̉��z �a�����Y������Ɨp���Y�̑[�u�@��70���̂U�̂W��17����P���C�̏��n���̑Ή��̊z���͓�����Q���C�̔p�~�̒��O�ɂ����铖�Y������Ɨp���Y�̎����ɑ���������z�i���Y���n���̑Ή��̊z���A������P���C�ɋK�肷�铖�Y������Ɨp���Y�̎����ɑ���������z�̂Q���̂P�ȉ��ł���ꍇ�ɂ́A���Y�Q���̂P�ɑ���������z�j �b���[�u�@��70���̂U�̂W��17���̋K��ɂ��Ə����ꂽ���^�ł̊z �c�����n�����͔p�~�̓��ȑO�T�N�ȓ��ɂ�����K�v�o��s�Z���Ή����̍��v�z �Q �u���z�Ə��v�ɂ��Ă͖�61���A�u�K�v�o��s�Z���Ή����v�ɂ��Ă͖�42���Q�ƁB �S�@ ���������āA��̎���ɂ����鎖�Ɨp���Y�ɂ��ẮA�[�u�@�� 70 ���̂U�̂W�� 17 ���̋K��ɂ��Ə������P�\�Ŋz�ɑΉ����镔���i1,500 ���~�j�������A�����Ŗ@�� 21 ���� 15 �̋K��Ɋ�Â��A���^���̉��z�i�P���~�|1,500 ���~��8,500 ���~�j�ɂ��A�����ł̉ېőΏۂƂȂ�B �@ �܂��A�[�ŗP�\�̊����������������^�Ŋz�i1,200 ���~�j�́A�����Ŋz����T������A�T��������Ȃ��������z�͊ҕt����邱�ƂƂȂ�B �i�Q�l�j�����ł̉ېőΏۂƂ���Ȃ������̃C���[�W�i��̎���̏ꍇ�j �i���j �i�� 38�j�m�莖�R�̊T�v
�i���j �P �S���m�肷��ꍇ ⑴ ���̐��x�̓K�p������᎖�Ǝғ��A����i�j���Ɨp���Y���͓��Y����i�j���Ɨp���Y�ɌW�鎖�Ƃɂ��āA���̕\�Ɍf����ꍇ�̂����ꂩ�ɊY�����邱�ƂƂȂ����ꍇ�ɂ́A���ꂼ��ɒ�߂�������Q�����o�߂�����������āA�P�\�Ŋz�̑S�Ăɂ��Ĕ[�ŗP�\�̊����������������ƂƂ���Ă���i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�B�A70 �̂U�� 10�B�j�B
(��)�@ ��L�����ꂼ��ɒ�߂�����炻�̂Q�����o�߂�����܂ł̊Ԃɓ��Y���᎖�Ǝғ������S�����ꍇ�ɂ�����[�ł̗P�\�ɌW��������A���Y���᎖�Ǝғ��̑����l�i����҂��܂ށB�j�����Y���᎖�Ǝғ��̎��S�ɂ�鑊���̊J�n�����������Ƃ�m�������̗�������U�����o�߂�����Ƃ���Ă���i�[�u�@ 70 �̂U�̂W㉖�A70 �̂U�� 10㉗�B�Q�ɂ����ē����B�j�B ⑵�@ �܂��A⑴�̂ق��A�p���͏o����͏o�����܂łɒ�o���Ȃ������ꍇ�i�͏o�����܂łɒ�o����Ȃ��������Ƃɂ���ނȂ��������ƔF�߂���ꍇ�Ɍp���͏o������o���ꂽ�Ƃ��������B�j��S�ۖ��߂ɉ����Ȃ��ꍇ�ɂ��A�P�\�Ŋz�̑S�Ăɂ��Ĕ[�ŗP�\�̊����������������ƂƂȂ�i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�J�A�K�A70 �̂U�� 10�K�A�L�j�B �Q�@ �ꕔ�m�肷��ꍇ �@����i�j���Ɨp���Y�̑S�����͈ꕔ�����᎖�Ǝғ��̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ��A�P�\�Ŋz�̂������Y���Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ��������ɑΉ�����Ŋz�ɂ��ẮA���Y���Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ����������Q�����o�߂�����������Ĕ[�ł̗P�\�ɌW������Ƃ�����i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�C�A70 �̂U�� 10�C�j�B �@�������A��L�ɊY������ꍇ�ł��A���Ɍf����ꍇ�ɊY������Ƃ��́A�[�ŗP�\�͌p������邱�ƂƂ���Ă���B ⑴�@����i�j���Ɨp���Y��������̎��R�ɂ��p���������ꍇ�ɂ����āA���̔p��������������Q���ȓ��ɐŖ������ɂ��̎|�̓͏o�������Ƃ��i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�C�A70 �̂U�� 10�C�B�ڍׂɂ��Ă͖� 45 �Q�ƁB�j ⑵�@ ����i�j���Ɨp���Y�����n�����ꍇ�ɂ����āA���̏��n��������������P�N�ȓ��ɂ��̑Ή��ɂ��V���Ȏ��Ɨp���Y���擾���錩���݂ł��邱�Ƃɂ����̏��n��������������P���ȓ��ɐŖ������ɐ\�������A���̏��F�����Ƃ��i�擾�ɏ[�Ă�ꂽ�Ή��ɑ������镔���Ɍ���B�j�i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�D�A70 �̂U�� 10�D�B�ڍׂɂ��Ă͖� 48 �Q�ƁB�j ⑶ �@��Ђ̐ݗ��ɔ��������o���ɂ��S�Ă̓���i�j���Ɨp���Y���ړ]�����ꍇ�ɂ����āA���̈ړ]�ɂ����̈ړ]��������������P���ȓ��ɐŖ������ɐ\�������A���̏��F�����Ƃ��i�[�u�@ 70 �̂U�̂W�E�A70 �̂U�� 10�E�B�ڍׂɂ��Ă͖� 53 �Q�ƁB�j �R�@ �Ȃ��A���᎖�Ǝғ����[�u�@�� 70 ���̂U�̂W��U�����͑� 70 ���̂U�� 10 ��U���̏��F�i�����o�����F�j�����ꍇ�̔[�ŗP�\�̊����̊m��ɂ��ẮA�u���ꊔ�����ɌW��[�ŗP�\�v�i�[�u�@ 70 �̂V�A70 �̂V�̂Q�A70 �̂V�̂T�A70 �̂V�̂U�j�ɂ�����i����j�o�c�i���^�j���p���Ԍo�ߌ�̊m�莖�R�ɏ������戵���ƂȂ�i�[�u�@�� 40 �̂V�̂W㉗�A40 �̂V�� 10㉕�B�ڍׂɂ��Ă͖� 53 �Q�ƁB�j�B |
�i�� 39�j���q�ł̌v�Z
�i���j �@���q�łɂ��ẮA�[�ŗP�\�̊�������������Ŋz�ɁA�\�����̒�o�����̗�������[�ŗP�\�̊����܂ł̊��Ԃɉ����A�N 3.6���̊������悶�Čv�Z����B �@�Ȃ��A�e�N�̓����������N 7.3���̊����ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̔N���ɂ����闘�q�ł̊����ɂ��ẮA���̊����Ɍy������A�Ⴆ�A�ߘa���N�i���� 31 �N�j�y�їߘa�Q�N�ɂ��ẮA�N0.7���Ɍy������Ă���B �i����j �P �@�[�ŗP�\�̊��������������Ŋz��[�t����ꍇ�A�����ė��q�ł�[�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̗��q�łɂ��ẮA�[�ŗP�\�̊�������������Ŋz�ɁA�\�����̒�o�����̗�������[�ŗP�\�̊����܂ł̊��Ԃɉ����A�N 3.6���̊������悶�Čv�Z���邱�ƂƂ���Ă���i�[�u�@ 70 �̂U�̂W㉕�A70 �̂U�� 10㉖�j�B �Q�@�Ȃ��A�e�N�̓����������N 7.3���̊����ɖ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̔N���ɂ����闘�q�ł̊����ɂ��ẮA���̎Z���ɂ��v�Z���������i0.1�������̒[���؎̂āj�Ƃ���Ă���i�[�u�@93�D�j�A�Ⴆ�A�ߘa���N�i���� 31 �N�j�y�їߘa�Q�N�ɂ��ẮA����������������� 1.6���ł��邽�߁A���q�ł̊����͔N 0.7���Ɍy������邱�ƂƂȂ�B �i�Z���j �@�@���q�ł̊��� �� 3.6�� × (���������^7.3%) (��)�@ �u���������v�Ƃ́A�e�N�̑O�X�N�� 10 ������O�N�̂X���܂ł̊e���ɂ������s�̐V�K�̒Z���ݏo��蕽�ϋ����̍��v�� 12 �ŏ����ē��������Ƃ��āA�e�N�̑O�N�� 12 �� 15 ���܂łɍ�����b���������銄���ɔN�P���̊��������Z���������������i�[�u�@ 93�A�j�B �i�Q�l�j�ߘa�Q�N�x�Ő������i�āj �@ �ߘa�Q�N�x�Ő������i�āj�ł́A�ߘa�R�N�P���P���Ȍ�̊��ԂɑΉ����闘�q�łɂ��ẮA��L�Z���́u���������v���A�e�N�̑O�X�N�̂X������O�N�̂W���܂ł̊e���ɂ������s�̐V�K�̒Z���ݏo��蕽�ϋ����̍��v�� 12 �ŏ����ē��������Ƃ��āA�e�N�̑O�N�� 11 �� 30 ���܂łɍ�����b���������銄���ɔN 0.5���̊��������Z���������i���q�œ��������j�Ɍ��������邱�ƂƂ���Ă���B �@ ����ɂ��A�Ⴆ�A���q�œ��������� 1.1���ł���ꍇ�ɂ́A���q�ł̊����͔N 0.5���Ɍy������邱�ƂƂȂ�B �i�� 41�j�����̎��Ƃ��c�ޏꍇ�̎��Y�ۗL�^���Ɠ��̔���
�i���j �`���Ƌy�тa���Ƃɂ��ẮA�����̎��ƂɌW�鑍���Y�̒��뉿�z���̍��v�z�Ɋ�Â�������s���A�b���Ƃɂ��ẮA���Y���ƂɌW�鑍���Y�̒��뉿�z���Ɋ�Â�������s���B �i�� 42�j�K�v�o��s�Z���Ή����̈Ӌ`
�i���j �@�ȊO�͑S�āA�K�v�o��s�Z���Ή����ɊY������B �i����j �P�@ �[�u�@��70���̂U�̂W��Q����S���n�ɋK�肷��K�v�o��s�Z���Ή����́A���Y�ۗL�^���Ƃ̔���i�[�u�@70�̂U�̂W�A�l�j�̍ۂɗp������ق��A�����16�������18���܂ł̋K��ɂ��P�\�Ŋz�̖Ə��̓K�p����ꍇ�ɂ́A���̕K�v�o��s�Z���Ή����ɑ������鑡�^�łɂ��Ă͖Ə����ꂸ�[�t��v���邱�ƂƂ���Ă���B �Q �@���̕K�v�o��s�Z���Ή����ɂ��ẮA�[�u�@�ߑ�40���̂V�̂W��16���ɂ����āA���᎖�Ǝ҂̓��ʊW�҂����莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�Ƃɏ]���������Ƃ��̑��̎��R�ɂ�蓖�Y���᎖�Ǝ҂���x�������Ή����͋��^�̋��z�ł����āA�����Ŗ@��56��((���Ƃ���Ή�����e��������ꍇ�̕K�v�o��̓���))���͑�57��((���Ƃɏ]������e��������ꍇ�̕K�v�o��̓��ᓙ))�̋K��ɂ�蓖�Y���ƂɌW�鎖�Ə����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ���������̈ȊO�̂��́A�ƋK�肳��Ă���B �@�܂�A���᎖�Ǝ҂̓��ʊW�҂����Y���᎖�Ǝ҂���x�������Ή����͋��^�̋��z�́A���@��56�͑�57���̋K��ɂ��K�v�o��ɎZ���������̂������A�S�ĕK�v�o��s�Z���Ή����ɊY�����邱�ƂƂȂ�B (��) �@���莖�Ɨp���Y�ɌW�鎖�Ƃɏ]�����铖�Y���᎖�Ǝ҂̎g�p�l�i�[�u�@�ߑ�40���̂V�̂W��15����P�����͑�Q���Ɍf����҂������B�j�����Y���Ƃɏ]���������Ƃɂ��x�������Ή����͋��^�́A�K�v�o��s�Z���Ή����ɊY�����Ȃ����̂Ƃ��č����x���Ȃ����ƂƂ���Ă���i�[�u��70�̂U�̂W�|23�j�B �R �@�����āA���́u�����Ŗ@��56�͑�57���̋K��ɂ��K�v�o��ɎZ���������́v�Ƃ́A���Ƃ��c�ދ��Z�҂Ɛ��v����ɂ���z��҂��̑��̐e�������̎��Ƃ���x������Ή��ɌW��e�폊���̋��z�̌v�Z��K�v�o��ɎZ���������́i���@56�j��A���Y���v����ɂ���z��҂��̑��̐e�������@��57���P���ɋK�肷��F���Ɛ�]�҂ɊY������ꍇ�ɓ��Y���Ƃ���x��������̋��^�i���@57�@�j���Y������B �S�@ ���������āA���᎖�Ǝ҂Ɛ��v����ɂ���e���ɊY�����Ȃ����ʊW�҂����Y���Ƃ���x �������Ή����͋��^�̋��z�́A���Y���ƂɌW�鎖�Ə����̋��z�̌v�Z��A�K�v�o��ɎZ���������̂ł����Ă��A�K�v�o��s�Z���Ή����ɊY�����邱�ƂƂȂ�B �T �@��̎���ɂ����ẮA�@�̋��^�́u�����Ŗ@��56�͑�57���̋K��ɂ��K�v�o��ɎZ���������́v�ɊY�����邪�A�A����D�͂���ɊY�����Ȃ����߁A�K�v�o��s�Z���Ή����ɊY�����邱�ƂƂȂ�B �i�Q�l�j�K�v�o��s�Z���Ή����͈̔́i�C���[�W�j �i���j �i��43�j�ꕔ�m�莖�R�ɊY�������ꍇ�ɂ�����m��Ŋz
�i���j �@�̎��_�F 47,995,000 �~×1,000 ���~�^�P���~ ��4,799,500 �~ �A�̎��_�F �i47,995,000 �~�|4,799,500 �~�j× 600 ���~�^(�P���~-1,000 ���~) ��2,879,700 �~ �i����j �P�@ �l�̎��Ɨp���Y�ɌW��[�ŗP�\�ł́A���̓K�p�������i�j���Ɨp���Y�����̎��Ƃ̗p�ɋ����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A�P�\�Ŋz�̂����A���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ�������i�j���Ɨp���Y�ɑΉ����镔���ɂ��ẮA�[�ŗP�\�ɌW��������������邱�ƂƂ���Ă���i�[�u�@70�̂U�̂W�C�A70�̂U��10�C�j�B �Q�@ �����āA���̔[�ŗP�\�ɌW���������������Ŋz�́A���̎Z���ɂ��v�Z���邱�ƂƂ���Ă���i�[�u�@��40�̂V�̂W�S�A40�̂V��10�P�j�B �i�Z���j �[�ŗP�\�ɌW���������������Ŋz�i100�~�����؎̂āj�� �` × (�b�^�a) ���P ��L�Z���̕����͎��̂Ƃ���B �`�����Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ������O�̗P�\�Ŋz �a�����Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ������̒��O�ɂ����ē��Y���Ƃ̗p�ɋ�����Ă����S�Ă̓���i�j���Ɨp ���Y�̑��^�E�����J�n�̎��ɂ����鉿�z �b�����Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ�������i�j���Ɨp���Y�̑��^�E�����J�n�̎��ɂ����鉿�z �Q �a�̓���i�j���Ɨp���Y�ɂ́A�[�u�@�ߑ�40���̂V�̂W��18�����͑�40���̂V��10��15���̔p���̓͏o�ɌW�����i�j���Ɨp���Y���܂܂��B �R �[�u�@��70���̂U�̂W��18�����͑�70���̂U��10��19���̋K��ɂ��Ə������ꍇ�ɂ������L�Z�����́u���^�E�����J�n�̎��ɂ����鉿�z�v�́A�F������ɂ����鉿�z�ƂȂ�B �R ��̎���ɂ��ď�L�Z���ɓ��Ă͂߂Čv�Z����ƁA�@�̎��_�ł̊m��Ŋz��4,799,500�~�A�A�̎��_�ł̊m��Ŋz��2,879,700�~�ƂȂ�B �i�� 44�j���x�ʐς����n���̈ꕔ�����n�����ꍇ
�i���j ��̎���̏��n�́A�m�莖�R�ɊY�����Ȃ��B �i����j �P �u�����ł̔[�ŗP�\�v�ł́A��n���ɂ��Ă͌��x�ʐϗv�����݂����Ă���A�[�ŗP�\�̑ΏۂƂȂ���莖�Ɨp���Y�ɊY�������n���́A���̖ʐς̍��v�̂���400�u�i�u���K�͑�n���̓���v�̓K�p����҂�����ꍇ�ɂ́A���K�͑�n���ɑ�������ʐςƂ��đ[�u�@�ߑ�40���̂V��10��V���̋K��ɂ��v�Z�����ʐς�400�u����T�������ʐρj�ȉ��̕����Ɍ����Ă���i�[�u�@70�̂U��10�A��C�j�B �Q �Ƃ���ŁA��̎���̂悤�ɁA���᎖�Ƒ����l���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă����n���̖ʐς����x�ʐς��Ă���ꍇ�ɂ����āA���̑�n���̈ꕔ�����n�����Ƃ��ɁA���̏��n���������̖ʐς����̒����镔���̖ʐςɌ�����ꍇ�ł����Ă��A���Y���Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ������̂Ƃ��đ[�u�@��70���̂U��10��S���̋K��ɂ��[�ŗP�\�̊����̊m�莖�R�ɊY������̂��A�Ƃ����^�₪������B �R ���̓_�A�[�u�@�ߑ�40���̂V��10��37���ł́A���᎖�Ƒ����l�����Ώێ��Ɨp���Y�i���᎖�Ɨp���Y�y�ѓ�����Ɨp���Y�������B�ȉ������B�j�ȊO�̓��Y���᎖�Ƒ����l���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�̏��n���͑��^�������Ƃ��i�[�u�@��70���̂U��10��15����Q���̋K��̓K�p�ɌW�鑡�^�������Ƃ��������B�j�́A���Y�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Y�����ɏ��n���͑��^�������̂Ƃ݂Ȃ��|�K�肵�Ă���B �S ��̎���̂`��n�͌��x�ʐς��Ă��邱�Ƃ���A���̑�n�̂����ɂ́u�Ώێ��Ɨp���Y�v�ɊY�����镔���i400�u�j�Ɓu�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�v�ɊY�����镔���i100�u�j�����݂��Ă���Ƃ���A���̈ꕔ�����n�����ꍇ�ɂ́A�[�u�@�ߑ�40���̂V��10��37���̋K��ɂ��A�u�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�v�ɊY�����镔���i100�u�j�����ɏ��n�������̂Ƃ݂Ȃ���邱�ƂƂȂ�B �����āA���̏��n������n�̖ʐς�100�u�ł����̎���ɂ����ẮA�u�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�v�̂ݏ��n�������ƂƂȂ邱�Ƃ���A���Y���n�́A�[�u�@��70���̂U��10��S���̊m�莖�R�ɊY�����Ȃ����ƂƂȂ�B �s�m�莖�R�ɌW�����t �i�� 45�j���Ɨp���Y�̔p���������ꍇ�̔[�ŗP�\�̌p������i���̂P�j�F�T�v
�i���j ���̔p��������������Q���ȓ��Ɉ��̓͏o����[�Œn�̏����Ŗ������ɒ�o�����ꍇ�ɂ́A�[�ŗP�\�̊����͓��������A�[�ŗP�\���p�������B |
�i�� 44�j���x�ʐς����n���̈ꕔ�����n�����ꍇ
�i���j ��̎���̏��n�́A�m�莖�R�ɊY�����Ȃ��B �i����j �P �u�����ł̔[�ŗP�\�v�ł́A��n���ɂ��Ă͌��x�ʐϗv�����݂����Ă���A�[�ŗP�\�̑ΏۂƂȂ���莖�Ɨp���Y�ɊY�������n���́A���̖ʐς̍��v�̂���400�u�i�u���K�͑�n���̓���v�̓K�p����҂�����ꍇ�ɂ́A���K�͑�n���ɑ�������ʐςƂ��đ[�u�@�ߑ�40���̂V��10��V���̋K��ɂ��v�Z�����ʐς�400�u����T�������ʐρj�ȉ��̕����Ɍ����Ă���i�[�u�@70�̂U��10�A��C�j�B �Q �Ƃ���ŁA��̎���̂悤�ɁA���᎖�Ƒ����l���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă����n���̖ʐς����x�ʐς��Ă���ꍇ�ɂ����āA���̑�n���̈ꕔ�����n�����Ƃ��ɁA���̏��n���������̖ʐς����̒����镔���̖ʐςɌ�����ꍇ�ł����Ă��A���Y���Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ������̂Ƃ��đ[�u�@��70���̂U��10��S���̋K��ɂ��[�ŗP�\�̊����̊m�莖�R�ɊY������̂��A�Ƃ����^�₪������B �R ���̓_�A�[�u�@�ߑ�40���̂V��10��37���ł́A���᎖�Ƒ����l�����Ώێ��Ɨp���Y�i���᎖�Ɨp���Y�y�ѓ�����Ɨp���Y�������B�ȉ������B�j�ȊO�̓��Y���᎖�Ƒ����l���̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�̏��n���͑��^�������Ƃ��i�[�u�@��70���̂U��10��15����Q���̋K��̓K�p�ɌW�鑡�^�������Ƃ��������B�j�́A���Y�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Y�����ɏ��n���͑��^�������̂Ƃ݂Ȃ��|�K�肵�Ă���B �S ��̎���̂`��n�͌��x�ʐς��Ă��邱�Ƃ���A���̑�n�̂����ɂ́u�Ώێ��Ɨp���Y�v�ɊY�����镔���i400�u�j�Ɓu�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�v�ɊY�����镔���i100�u�j�����݂��Ă���Ƃ���A���̈ꕔ�����n�����ꍇ�ɂ́A�[�u�@�ߑ�40���̂V��10��37���̋K��ɂ��A�u�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�v�ɊY�����镔���i100�u�j�����ɏ��n�������̂Ƃ݂Ȃ���邱�ƂƂȂ�B �����āA���̏��n������n�̖ʐς�100�u�ł����̎���ɂ����ẮA�u�Ώێ��Ɨp���Y�ȊO�̎��Ƃ̗p�ɋ�����Ă��鎑�Y�v�̂ݏ��n�������ƂƂȂ邱�Ƃ���A���Y���n�́A�[�u�@��70���̂U��10��S���̊m�莖�R�ɊY�����Ȃ����ƂƂȂ�B �s�m�莖�R�ɌW�����t �i�� 45�j���Ɨp���Y�̔p���������ꍇ�̔[�ŗP�\�̌p������i���̂P�j�F�T�v
�i���j ���̔p��������������Q���ȓ��Ɉ��̓͏o����[�Œn�̏����Ŗ������ɒ�o�����ꍇ�ɂ́A�[�ŗP�\�̊����͓��������A�[�ŗP�\���p�������B �i����j �P �l�̎��Ɨp���Y�ɌW��[�ŗP�\�ł́A���̓K�p�������i�j���Ɨp���Y�����̎��Ƃ̗p�ɋ����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A���Y����i�j���Ɨp���Y�ɑΉ�����P�\�Ŋz�ɂ��ẮA�[�ŗP�\�ɌW��������������邱�ƂƂ���Ă���i�[�u�@70�̂U�̂W�C�A70�̂U��10�C�j�B �Q �������A���ꂪ����i�j���Ɨp���Y�̒����A���H�A���Ղ��̑������ɏ����鎖�R�ɂ�铖�Y����i�j���Ɨp���Y�́u�p���v�ł���ꍇ�ɂ́A���̎������L�ڂ����͏o���ɔp�����������Ƃ��m�F�ł��鏑�ނ�Y�t���āA��������̔p��������������Q���ȓ��ɔ[�Œn�̏����Ŗ������ɒ�o�����Ƃ��́A�[�ŗP�\�͌p������邱�ƂƂ���Ă���i�[�u�@70�̂U�̂W�C�A70�̂U��10�C�A�[�u�@��40�̂V�̂W�Q�A40�̂V��10�N�j�B (��) �[�u�@��40���̂V�̂W��18�����͑�40���̂V��10��15���ɂ͂䂤����K�肪�݂����Ă��Ȃ����߁A��L�Q�̓͏o�����̔p��������������Q���ȓ��ɍs��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̔p��������������Q�����o�߂�����ɂ����āA�[�ŗP�\�ɌW��������������邱�ƂƂȂ�B �R �Ȃ��A��L�Q�̓͏o����������i�j���Ɨp���Y�ɌW��P�\�Ŋz�ɂ��ẮA�S���m�莖�R���������ꍇ�ɑ��̓���i�j���Ɨp���Y�ɌW��P�\�Ŋz�ƂƂ��ɔ[�ŗP�\�ɌW��������������A�܂��A�Ə����R���������ꍇ�ɑ��̓���i�j���Ɨp���Y�ɌW��P�\�Ŋz�ƂƂ��ɖƏ�����邱�ƂƂȂ�B �i�� 46�j���Ɨp���Y�̔p���������ꍇ�̔[�ŗP�\�̌p������i���̂Q�j�F���Ɨp���Y�̏����ɂ���ē����Ή�������ꍇ
�i���j �@�̏ꍇ�́u�p���v�ɊY�����Ȃ����A�A�̏ꍇ�́u�p���v�ɊY������B �i����j �P ����i�j���Ɨp���Y�����Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ����āA���ꂪ���Y����i�j���Ɨp���Y�������A���H�A���Ղ��̑������ɏ����鎖�R�ɂ�����Y����i�j���Ɨp���Y�́u�p���v�ł���Ƃ����A���̔p��������������Q���ȓ��ɔ[�Œn�̏����Ŗ������ɂ��̎|�̓͏o�������ꍇ�ɂ��A�[�ŗP�\�ɌW������͓������Ȃ����ƂƂ���Ă����i�[�u�@70�̂U�̂W�C�A70�̂U��10�C�A�[�u�@��40�̂V�̂W�Q�A40�̂V��10�N�j�B �Q �Ƃ���ŁA���̓���́u���Ƃ̗p�ɋ�����Ȃ��Ȃ���������Ɨp���Y�́E�E�E�m�肵���Ŋz��[�t���邱�Ƃ������ł����A�����⌸�����p���Y�̏ꍇ�A�o�N������ɔ�����ނ��p������ꍇ���z�肳��A���̂悤�ȏꍇ�ɂ܂ňꗥ�ɗP�\�Ŋz�̔[�t�����߂邱�Ƃ͍��Ǝv���邽�߁v�i������HP�u�ߘa���N�x�Ő������̉���v521�Łj�ɐ݂���ꂽ���̂ł���A���������āA�������̗��R�ɂ�����i�j���Ɨp���Y�����������ꍇ�ł����Ă��A���̏����ɂ���ē����Ή�������Ƃ��́A���̏����͑[�u�@��40���̂V�̂W��18�����́u�p���v�ɂ́A�Y�����Ȃ����ƂƂȂ�i�[�u��70�̂U�̂W�|37�A70�̂U��10�|32�j�B �R �����Ƃ��A����i�j���Ɨp���Y�̏����ɔ����������p�ޓ��̔���肪�s��ꂽ�ꍇ�ł����Ă��A���̑Ή��̊z�����Y�����ɓ�����v������p�̊z�ȉ��ł���Ƃ��́A�����I�ɂ́A���Y�����ɂ���ē����Ή��͂Ȃ����̂ƍl�����邱�Ƃ���A���̂悤�ȏꍇ�ɂ��ẮA��L�Q�́u�����ɂ���ē����Ή�������ꍇ�v�ɊY�������A�u�p���v�ɊY�����邱�ƂƂȂ�B �S ��̎���@�̏ꍇ�ɂ́A�p�ޑ����z�Ƃ���10���~���擾���Ă��邱�Ƃ���A�`�@�B���u�̏����́u�p���v�ɊY�����Ȃ����A����A�̏ꍇ�ɂ́A�p�ޑ����z�i10���~�j�������ɗv������p�i20���~�j�ȉ��ł��邱�Ƃ���A�`�@�B���u�̏����́u�p���v�ɊY�����邱�ƂƂȂ�B (��) ����@�̏ꍇ�ɂ́A���̏����̓�����P���ȓ��ɑ[�u�@��70���̂U�̂W��T���̔������F�̐\�����s���A�����̋K��ɂ��Ŗ������̏��F���A���̏����̓�����P�N�ȓ��ɂ��̏����ɂ���ē����Ή��������Ď��Ƃ̗p�ɋ����鎑�Y���擾�����ꍇ�ɂ́A���̎擾�ɏ[�Ă��Ή��ɑ������镔���͔[�ŗP�\�̊����͊m�肵�Ȃ����ƂƂȂ�i��48�Q�Ɓj�B �ȉ��̍��ڂ́A���ʂ̎���ɂ��H���� �Q�l https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/pdf/0019012-113.pdf 
|
|
��350-1314 ��ʌ� ���R�s �����u 167-2�@������� �����p�^�R���^�Η��ŗ��m�������@☎04(2946)7704
|