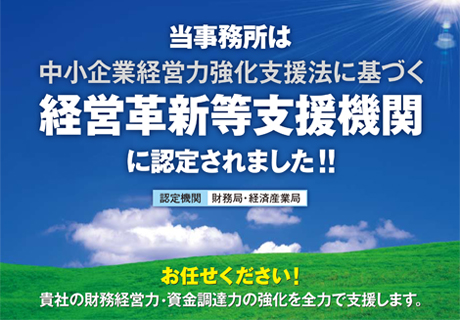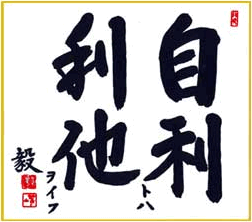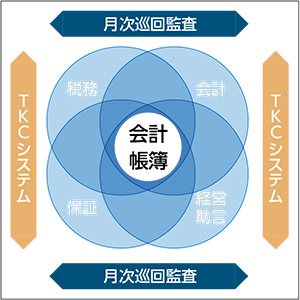経営革新等支援機関
根拠法令 中小企業等経営強化法 (認定経営革新等支援機関) 第26条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。 2 前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 経営革新若しくは異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析 二 経営革新のための事業若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言 3 (以下、略) |
貴社の永続的繁栄のために、円滑な事業承継をご支援します (特例事業承継税制)
抜本的な事業承継税制改革 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。 ※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください! 今回の改正のポイント事業承継税制の現行(一般)と特例の相違点
対象株式が100%に! 相続時の猶予対象が株式評価額の100%に! 雇用確保要件が実質撤廃に! 受贈者の範囲拡大! ➤ 相続税シミレーション(全国会) 家族状況や所有財産と、将来の贈与案を入力することにより、相続税・贈与税の総額を試算することができます。 特例事業承継税制の適用を受けるために提出する「特例承継計画」とは? 承継計画は会社名、先代経営者の氏名、後継者の氏名(最大3名)事業内容、承継時までの経営の見直し、5年間に行う承継実施内容、認定経営革新等支援機関等による所見などを記載したものです。
<特例承継計画の記載事項>
1. 会社について 2. 特例代表者について 3. 特例後継者について 4. 特例代表者が有する株式等を特例後継者が取得するまでの期間における経営の計画について 5. 特例後継者が株式等を承継した後5年間の経営計画 6. 認定支援機関による所見等(指導・助言の内容) 事業承継を成功に導く5つのステップ 「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。 経営者の気付きと動機付け なんとなくで始められるほど事業承継は単純なものではありません。事業承継を真剣に考えることが最初のスタートです。そして戦略的思考をもって経営計画を策定し、これから先の経営のあり方を考えてみれば自ずと事業承継の場面のイメージは出来るはずです。 現状分析 事業承継にあたっては、会社の状態をよく現状分析することが大切です。経営者は当然のように知っていることでも、後継者にとってはそうでないこともあります。しっかりと現状分析を行い、後継者に会社の強み、弱みをしっかりと伝え、強みを特化すればどうすればよいかを考えましょう。 方向性の決定 現状分析を行った結果、親族外承継を行わざる得ない場合もあります。また、後継者がどうしても見つからない場合は、売却も視野にいれなければなりません。 事業承継計画の策定・スケジュール化 事業承継に向けて必要な項目ごとに「いつ」「誰が」「何を」行うのかを決定し、スケジュール化します。ここでは目的と手段を整理してまとめる必要があります。 計画の実施・見直し 承継計画が策定できたらあとはスケジュール通りに実施するだけです。経営環境に変化が生じると想定外のことも起こります。そのようなときには柔軟に計画を見直し、変化に対応する必要があります。
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください! |