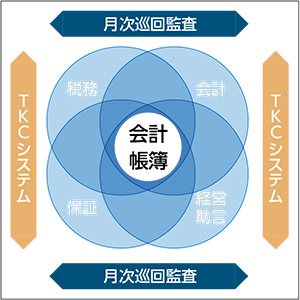�Ŗ��֘A���
�Ŗ��֘A��� �@�@ �@�@
♥�@�ō��ٔ����F�����łɂ������Y������̍X���̐����̋��e�͈� ♥�@�ٗp�ҋ��^���x�������z�������ۂ������z�ɋL�ڂ���������Y�t���Ċm��\���������ꍇ�̏C���̉� ♥�@���Q��������F�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̐Ŋz�T���i�����g��Ő��j�̓K�p���O ♥�@�b��ٌ̍�����F�e�q�Ԃ̎����ړ� ♥�@�ٔ���(2)�F�������^�ɂ�����u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v�̈Ӌ` ♥�@�Ő�������j�^�ŗ��m�̋`���i�����n�فj ♥�@���{���P���~�ȉ��̗��_ 1. ���z�\���`���� 2. �F���搶�I��ςł��� 3. ����Ōo�������ʒB���� 4. ����Ōo�������ʒBQ&A 5. �ƐŎ��Ǝ҂̌o������ 6. ����Ԃɂ����ĖƐŎ��Ǝ҂ł������҂̉ېŔ��㍂�̔��� 7. �܂�ڂ� * �r���ƌ� |
�ٔ���

�d�œ��ʑ[�u�@42����12��4��1���ɂ��@�l�Ŋz�̓��ʍT������ɂ�����ٗp�ҋ��^���x�������z�������ۂ������z�ɋL�ڂ���������Y�t���Ċm��\���������ꍇ�̏C���̉� �����n���ٔ����@ �@�@����29�N�i�s�E�j��490���@�@�l�œ��X��������������������i��P�����j �@�@����30�N�i�s�E�j��144���@�X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm����������������i��Q�����j�@�@ �@�@����31�N1��25�������i�ꕔ���p�C�ꕔ�p���jLEX / DB 25559039 1�@���Ă̊T�v �@����X���C���V��Ŗ������ɑ��C �i1�j�{�����ƔN�x�̖@�l�ł̊m��\���������ہC�d�œ��ʑ[�u�@42����12��4��1��*1���K�肷��@�l�Ŋz�̓��ʍT��*2�ɂ��āC�ٗp�ҋ��^���x�������z��49,041,011�~�C�������b�Ƃ��Čv�Z�����@�l�Ŋz�̓��ʍT���z��4,904,101�~���ƋL�ڂ�������*3��Y�t�����m��\����*4���o����ƂƂ��ɁC �i2�j�{���ېŎ��ƔN�x�̕������ʖ@�l�ł̊m��\���������ہC�{���@�l�Ŋm��\�����y�і{�����������̋L�ڂ�O��Ƃ����m��\����*5���o�����Ƃ���C���V��Ŗ������́C����28�N6��28���t���ŁC�{�����ʍT���Ɋ�Â��Ė@�l�ł̊z����T���������z�́C�����S��*6�̋K��ɂ��{�����������ɋL�ڂ��ꂽ���z�Ɍ�����Ƃ��āC�{���e�X�����������������߁C�������C�@�l�ŋy�ѕ������ʖ@�l�ł̊e�\���ɌW��Ŋz�ɂ��X�������ׂ��|�̐����i�{���e�X���̐����j���������̂́C���V��Ŗ������́C����29�N11��27���t���ŁC�{���e�ʒm�i�X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�j�����������B �@�{���́C�������C�{�����������̋L�ڂ͖��炩�ȓ]�L�~�X�ɂ����̂ł���C�{���e�X���������͈�@�ł���Ƃ��āC�{���e�X���������̈ꕔ�̎���������߂鎖�āi��1�����j�ƁC�{���e�X������������@�ł��邱�Ƃɂ��C�{���e�X���̐����ɂ͂���������R������Ƃ��āC�{���e�ʒm�����̎���������߂鎖�āi��2�����j�ł���B *1�i�������C����27�N�@����9���ɂ������O�̂��́B�ȉ������B�j *2�i�ȉ��u�{�����ʍT���v�Ƃ����B�j *3�i�@�l�Ŗ@�{�s�K���ʕ\�Z�i��\�j�B�������C����27�N�����ȗߑ�46���ɂ������O�̂��́B�ȉ��u�{�������v�Ƃ����B�j *4�i�ȉ��u�{���@�l�Ŋm��\�����v�Ƃ����C�{���@�l�Ŋm��\�����ɓY�t���ꂽ�������u�{�����������v�Ƃ����B�j *5�i�ȉ��u�{�������Ŋm��\�����v�Ƃ����C�{���@�l�Ŋm��\�����Ƒ��̂��āu�{���e�m��\�����v�Ƃ����B�j *6�i�������C����28�N�@����15���ɂ������O�̂��́B�ȉ������B�j 2�@����X�������e�Ɣ��� ��P�����i�@�l�ōX�������̎���E�������ʖ@�l�ōX�������̎���E�ߏ��\�����Z�ŕ��ی��菈���̎���j �i1�j���V��Ŗ�����������28�N6��28���t���Ō����ɑ��Ă��������̕���25�N10��1�����畽��26�N9��30���܂ł̎��ƔN�x*1�ɌW��@�l�ł̍X���̏���*2�̂����@�l�ł̊z117,029,000�~�����镔���y�щߏ��\�����Z�ł̕��ی��菈��*3���������B *1�i�ȉ��u�{�����ƔN�x�v�Ƃ����B�j *2�i�ȉ��u�{���@�l�ōX�������v�Ƃ����B�j *3�i�ȉ��u�{���@�l�ŕ��ی��菈���v�Ƃ����B�j �i2�j���V��Ŗ�����������28�N6��28���t���Ō����ɑ��Ă��������̕���25�N10��1�����畽��26�N9��30���܂ł̉ېŎ��ƔN�x*1�̕������ʖ@�l�ł̍X���̏���*2�̂����@�l�Ŋz11,703,900�~�����镔���y�щߏ��\�����Z�ł̕��ی��菈��*3���������B *1�i�ȉ��u�{���ېŎ��ƔN�x�v�Ƃ����B�j *2�i�ȉ��u�{�������ōX�������v�Ƃ����C�{���@�l�ōX�������Ƒ��̂��āu�{���e�X�������v�Ƃ����B�j *3�i�ȉ��u�{�������ŕ��ی��菈���v�Ƃ����C�{���@�l�ŕ��ی��菈���Ƒ��̂��āu�{���e���ی��菈���v�Ƃ����B�܂��C�{���e�X�������Ɩ{���e���ی��菈���̂��āu�{���e�X���������v�Ƃ����B ��→���p�i�����e���������ė��R���Ȃ��Ƃ��đނ��邱�ƁB�j �i�P�ʁF�~�j
��Q�����i�X���̐����ɑ���u�X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�����v�̎���j �i�P�j���V��Ŗ�����������29�N11��27���t���Ō����ɑ��Ă����{�����ƔN�x�̖@�l�ł̍X���̐����ɑ���X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�̏������������B �i�Q�j���V��Ŗ�����������29�N11��27���t���Ō����ɑ��Ă����{���ېŎ��ƔN�x�̕������ʖ@�l�ł̍X���̐���*1�ɑ���X�������ׂ����R���Ȃ��|�̒ʒm�̏���*2���������B�@ *1�i�ȉ��C�O�L�i�P�j�̍X���̐����Ƒ��̂��āu�{���e�X���̐����v�Ƃ����B�j *2�i�ȉ��C�O�L�i�P�j�̒ʒm�̏����Ƒ��̂��āu�{���e�ʒm�����v�Ƃ����B�j ��→�p���i���葱�̕s���Ȃǂŕs�K���ȑi�ׂƂ��Đ����̒��g����������邱�ƂȂ��ނ��邱�ƁB��O�����̔����B�j 3�@�W�@�߂̒�� �ʎ��P�@�W�@�߂̒�߁i���j �P�@�d�œ��ʑ[�u�@42����12��4�i�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���j�̒�� �i�P�j�d�œ��ʑ[�u�@42����12��4��1���̒�� �@�d�œ��ʑ[�u�@42����12��4��1���̒������́C�F�\�������o����@�l���C����25�N4��1�����畽��30�N3��31���܂ł̊ԂɊJ�n����e���ƔN�x�i�����j�ɂ����č����ٗp�҂ɑ��ċ��^�����x������ꍇ�ɂ����āC���Y�@�l�̌ٗp�ҋ��^���x���z�����ٗp�ҋ��^���x���z���T���������z�i�ȉ��C�u�ٗp�ҋ��^���x�������z�v�Ƃ����B�j�̓��Y��ٗp�ҋ��^���x���z�ɑ��銄����100����5�i����27�N4��1���O�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ����Ă�100����2�Ƃ��C�������畽��28�N3��31���܂ł̊ԂɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ����Ă�100����3�Ƃ���B�j�ȏ�ł���Ƃ��i���Ɍf����v�������ꍇ�Ɍ���B�j�́C���Y�@�l�̓��Y���ƔN�x�̏����ɑ���@�l�ł̊z�i�����j����C���Y�ٗp�ҋ��^���x�������z��100����10�ɑ���������z�i�ȉ��C�u�Ŋz�T�����x�z�v�Ƃ����B�j���T������i�O�i�j���C���Y�Ŋz�T�����x�z���C���Y�@�l�̓��Y���ƔN�x�̏����ɑ���@�l�ł̊z��100����10�i���Y�@�l��������Ǝғ��i�����j�ł���ꍇ�ɂ́C100����20�j�ɑ���������z����Ƃ��́C���̍T��������z�́C���Y100����10�ɑ���������z�����x�Ƃ���i��i�j�|���߂Ă���B ��E��i���j �i�Q�j�d�œ��ʑ[�u�@42����12��4��4���̒�߁i→�@�����\���v���E�K�p�z�̐����j �@�d�œ��ʑ[�u�@42����12��4��4���́C����1���̋K��́C�m��\������*�C�C���\�������͍X���������ɁC�����̋K��ɂ��T���̑ΏۂƂȂ�ٗp�ҋ��^���x�������z�C�T��������z�y�ѓ��Y���z�̌v�Z�Ɋւ��閾�ׂ��L�ڂ������ނ̓Y�t������ꍇ�Ɍ���C�K�p���邪�i�O�i�j�C���̏ꍇ�ɂ����āC�����̋K��ɂ��T���������z�́C���Y�m��\������*�ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ�ٗp�ҋ��^���x�������z����b�Ƃ��Čv�Z�������z�Ɍ�����̂Ƃ���i��i�j�|���߂Ă���B *�u�m��\�������v���i�d�œ��ʑ[�u�@2���i�p��̈Ӌ`�j�A��\���j�m��\�����i������\�����j�E���Ԑ\���� �O��ƂȂ鎖���W�i�����҂̊Ԃɑ������Ȃ����͓��ٔ����Ɍ����Ȏ����j �i�P�j�����ғ� �A�@�����́C�����Q�N�P�Q���U���C��ǂ̌o�c����ړI�Ƃ��Đݗ����ꂽ������Ђł���B �C�@�c�ŗ��m�@�l�i�ȉ��u�{���ŗ��m�@�l�v�Ƃ����B�j�́C�����Q�U�N�P�P���Q�W�������C�����̂�����ږ�ŗ��m�ɏA�C���Ă����@�l�ł���B �i�Q�j�{���e�X���������Ɏ���o�� �A�@�{���ŗ��m�@�l�̏]�ƈ��́C�����Q�U�N�P�P�����C�{�����ƔN�x�̖@�l�ł̊m��\���̏��������邽�߁C�̌n�ʋ��^���v�\���Q�Ƃ�����ŁC�\�v�Z�̃\�t�g�E�F�A�ł���G�N�Z���̂����郏�[�N�V�[�g�i�ȉ��u�{���G�N�Z���V�[�g�v�Ƃ����B�j���쐬�������C�Z���ԘJ���ҁi������p�[�g�^�C�}�[�j�ɑ���ېŎx���z����L�̑̌n�ʋ��^���v�\����]�L���悤�Ƃ����ہC�ېŎx���z�ł͂Ȃ���ېł̒ʋΎ蓖�̊z��{���G�N�Z���V�[�g�̉ېŎx���z�̗��ɓ]�L�����B���]�ƈ��́C������f�[�^�����͂��ꂽ�{���G�N�Z���V�[�g�̃f�[�^��O��Ƃ��āC�{�������������쐬���C�����Y�t�����m��\�����i�{���@�l�Ŋm��\�����j���쐬�����B �@�@�{���ŗ��m�@�l�́C�����Q�U�N�P�P���Q�W���C���V��Ŗ������ɑ��C�����̋��z���T���P�W�T�P���W�T�P�U�~�C�[�t���ׂ��@�l�ł̊z���P���R�P�R�W���Q�O�X�O�~�C�@�l�ł̊z����T�������@�l�Ŋz�̓��ʍT���̊z���T�O�Q���P�V�O�P�~�i�{�����ʍT���̊z���S�X�O���S�P�O�P�~�C���̗]�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���̊z���P�P���V�U�O�O�~�j���Ƃ��錴�����@�l�Ŗ@�̋K��Ɋ�Â��Ă���{�����ƔN�x�̖@�l�ł̊m��\���ɂ�������㗝���C�{���@�l�Ŋm��\�������o����ƂƂ��ɁC�ېŕW���@�l�Ŋz���P���Q�U�R�U���~�C�[�t���ׂ��������ʖ@�l�ł̊z���P�Q�U�R���T�V�O�O�~���Ƃ���{���ېŎ��ƔN�x�̕������ʖ@�l�ł̊m��\���ɂ�������㗝���C�{�������Ŋm��\�������o�����B �C�@���V��Ŗ����̐E���́C�����Q�V�N�Q�����C�����̖@�l�łɊւ��钲�����s�����Ƃ���C�{���ŗ��m�@�l�́C��L�̒����ɐ旧���C���Ŗ����̐E���ɑ��C���炩���߁C�{�����������Ɍ�肪���邱�Ƃ�`���Ă����B �i�R�j�{���e�X���������Ƃ��̌�̌o�ܓ� �A�@���V��Ŗ������́C�����Q�V�N�V���R�P���t���Ō����ɑ��C�ʕ\�P�|�P�y�тP�|�Q�̂����u�N�����v���Ɂu�Q�V�E�V�E�R�P�v�Ƃ̋L�ڂ����镔���ɑΉ�����u�敪�v�����u�X�������v���ɂ��ꂼ��L�ڂ�����Ƃ���C�����̖{�����ƔN�x�̖@�l�ŋy�і{���ېŎ��ƔN�x�̕������ʖ@�l�ł̊e�X���̏����������B �C�@���V��Ŗ������́C�����Q�W�N�U���Q�W���t���Ō����ɑ��C�ʕ\�P�|�P�y�тP�|�Q�̂����u�N�����v���Ɂu�Q�W�E�U�E�Q�W�v�Ƃ̋L�ڂ����镔���ɑΉ�����u�敪�v�����u�X�������v���ɂ��ꂼ��L�ڂ�����Ƃ���C�{���e�X���������������B �E�@�����́C�����Q�W�N�W���Q�X���C�{���e�X����������s���Ƃ��č��ŕs���R�������ɑ��ĐR�����������ꂼ�ꂵ�����C���ŕs���R�������́C�����Q�X�N�S���P�S���C��L�̐R������������������p����|�ٌ̍��������B �G�i�A�j�����́C�����Q�X�N�W���Q�W���C���V��Ŗ������ɑ��C�ʕ\�P�|�P�y�тP�|�Q�̂����u�N�����v���Ɂu�Q�X�E�W�E�Q�W�v�Ƃ̋L�ڂ����镔���ɑΉ�����u�敪�v�����u�X���̐����v���ɂ��ꂼ��L�ڂ�����Ƃ���C�{���e�X���̐��������ꂼ�ꂵ���B �i�C�j���V��Ŗ������́C�����Q�X�N�P�P���Q�V���C�����ɑ��C�{���e�ʒm���������ꂼ�ꂵ���B �i�E�j�����́C�����Q�X�N�P�Q���Q�P���C�{���e�ʒm������s���Ƃ��č��ŕs���R�������ɑ��ĐR�����������ꂼ�ꂵ�����C���ŕs���R�������́C�����R�O�N�U���P�P���C��L�̐R������������������p����|�ٌ̍��������B �i�S�j�{���i���̒�N �@�����́C�����Q�X�N�P�O���Q�R���C��P�����ɌW��i�����C�����R�O�N�S���P�Q���C��Q�����ɌW��i�����C���ꂼ���N�����B |
||||||||||||||||||
�����̎咣�v��i�퍐�咣�̔��_�j ���_�@�{�����ʍT���ɂ��Čٗp�ҋ��^���x�������z������I�ɏC�����邱�Ƃ̉�
�y���������z�y�����v�|�z (1) ����̉ېŕW���ɑ��������ɍs��ꂽ���z�X�������ƍX���̐����ɗ��R���Ȃ��|�̒ʒm�����̑o���𑈂��ꍇ�̑i���̗��v �@���z�X�������ƍX���̐����ɗ��R���Ȃ��|�̒ʒm�����́C�葱�I�ɂ͕ʌƗ��̏����ł��邪�C������������ł̔[�ŋ`���̊m��Ɋւ�鏈���ł���Ƃ���C�X���̐����ɗ��R���Ȃ��|�̒ʒm�����́C�\�����ꂽ�Ŋz�̌����݂̂Ɋւ��̂ɑ��C���z�X�������́C�ېŗv��������S�̓I�Ɍ������C�\���ɌW��Ŋz���܂߂āC�S�̂Ƃ��Ă̔[�t���ׂ��Ŋz�̑��z���m�肷����̂ł����āC�����I�ɂ͐\���ɌW��Ŋz�����z���Ȃ��Ƃ�����|���܂ނ��̂ł��邩��C���҂�����̖@�l�ł̔[�ŋ`���ɂ��čs��ꂽ�ꍇ�C���z�X�������̓��e���X���̐����ɗ��R���Ȃ��|�̒ʒm�����̓��e���ۂ���W�ɂ���Ƃ������Ƃ��ł��C���������āC���z�X�������ƍX���̐����ɗ��R���Ȃ��|�̒ʒm���������ꂽ�ꍇ�C�Ŋz���𑈂��[�Ŏ҂́C�����̏����̑O����킸�C���z�X�������̎���������߂�i�����N���čX���̐����ɗ��R���Ȃ��|�̒ʒm�����̈�@�������Ď咣���đ������Ƃɂ��C�X���̐����ɌW��Ŋz���镔���̎���������߂邱�Ƃ��ł�����̂Ɖ�����C�Ŋz�̑S�̂𑈂����Ƃ��ł���̂ł����āC����ƕʌɍX���̐����ɗ��R���Ȃ��|�̒ʒm�����𑈂����v��L���Ȃ����̂Ɖ����ׂ��ł���C�����āC���̂悤�ɉ����邱�Ƃ��C����̖@�l�ł̔[�ŋ`���Ɋւ��Q�̏����̑i�ׂ��ʌɌW�����邱�Ƃɂ�萶����R���y�є��f�̏d�����͒�G������邽�߂ɂ������ł���C���������āC�{���i���̂����{���e�ʒm�����̎���������߂镔���́C�i���̗��v���Ȃ��C�s�K�@�ł���Ƃ����ׂ��ł���B (2) �d�œ��ʑ[�u�@�S�Q���̂P�Q�̂S�̋K�肷��@�l�Ŋz����T���������z�̈Ӌ` �@�d�œ��ʑ[�u�@�S�Q���̂P�Q�̂S��S���́C�����P���̋K��́C�m��\�������C�C���\�������͍X���������ɓ����̋K��ɂ��T���̑ΏۂƂȂ�ٗp�ҋ��^���x�������z�C�T��������z�y�ѓ��Y���z�̌v�Z�Ɋւ��閾�ׂ��L�ڂ������ނ̓Y�t������ꍇ�Ɍ���C�K�p���i�O�i�j�C���̏ꍇ�ɂ����āC�����̋K��ɂ��T���������z�́C���Y�m��\�������ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ�ٗp�ҋ��^���x�������z����b�Ƃ��Čv�Z�������z�Ɍ�����̂Ƃ���i��i�j�|���߂Ă���C�����̋K��̕����y�ѕ����ɂ��C�d�œ��ʑ[�u�@�S�Q���̂P�Q�̂S�̋K��ɂ��@�l�Ŋz����T���������z�́C�m��\�������ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ�ٗp�ҋ��^���x�������z����b�Ƃ��Čv�Z�������z�Ɍ�������̂ƔF�߂�̂������ł���B (3) �d�œ��ʑ[�u�@�S�Q���̂P�Q�̂S�̓K�p�W�Ŋm��\�������Y�t���ދL�ڂ̌ٗp�ҋ��^���x�������z���قȂ��Ă������Ƃ𗝗R�ɍX���̐��������邱�Ƃ͉\���i���Ɂj �@�d�œ��ʑ[�u�@�S�Q���̂P�Q�̂S�̋K��ɂ��@�l�Ŋz����T���������z�́C�m��\�������ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ�ٗp�ҋ��^���x�������z����b�Ƃ��Čv�Z�������z�Ɍ�������̂ƔF�߂�̂������ł���Ƃ���C���ɁC�^���̌ٗp�ҋ��^���x�������z�Ɗm��\�������ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ�ٗp�ҋ��^���x�������z���قȂ��Ă����Ƃ��Ă��C���Y�����́C���Œʑ��@�Q�R���P���P���ɂ����u���Y�v�Z�Ɍ�肪���������Ɓv�ɂ͊Y�����Ȃ����ƂƂȂ邩��C�m��\���������o�����҂́C�Ŗ������ɑ��C�^���̌ٗp�ҋ��^���x�������z�Ɗm��\�������ɓY�t���ꂽ���ނɋL�ڂ��ꂽ�ٗp�ҋ��^���x�������z���قȂ��Ă������Ƃ𗝗R�Ƃ��āC�����̋K��Ɋ�Â��X���̐��������邱�Ƃ�������Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B (4) �ō��ٔ����𗝗R�ɑd�œ��ʑ[�u�@�S�Q���̂P�Q�̂S�̓��ʍT���̓K�p�ɓ�����\�����L�ڊz���ɌW��X���̐����͗e�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��ꂽ���� �@�w�i�����j�́C�ō��ٕ����Q�P�N�V���P�O����@�씻���i�ō��ٕ����Q�P�N�����j�̔����ɏƂ炵�C�d�œ��ʑ[�u�@�S�Q���̂P�Q�̂S��S���͊m��\�����̋L�ڂ��疾�炩�ł͂Ȃ��v�Z�̌�肪�C�K�p�͈͂�lj��I�Ɋg�������|�ɊY�����邩�ۂ��̃��x���Ŗ��ɂȂ蓾�邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���C�m��\�����̋L�ڂ��疾�炩�ł͂Ȃ��v�Z�̌��𗝗R�Ƃ���X���̐������F�߂���]�n�����邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���Ƃ�����|�咣���邪�C���ɁC�ō��ٕ����Q�P�N�����̔����ɂ��āC�m��\�����̋L�ڂ��疾�炩�ł͂Ȃ��v�Z�̌��𗝗R�Ƃ���X���̐������F�߂���]�n������Ɖ����邱�Ƃ�O��Ƃ����Ƃ��Ă��C�ō��ٕ����Q�P�N�����́C�m��\�����ɓY�t���ꂽ���ނ̋L�ڂ���C���̏��L���銔���̑S�����ɌW�鏊���Ŋz�̑S����ΏۂƂ��āC�@�߂Ɋ�Â������Ɍv�Z�������z�ɂ��C�����Ŋz�̍T���̐��x�̓K�p���邱�Ƃ�I������ӎv�ł��������Ƃ����Ď��鎖�Ăł���C�{���Ƃ͎��Ă��قɂ��Ă��邩��C�w�������{���e�X���̐������F�e����邱�Ƃ𗠕t���邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �ʕ\�Q�|�P�@�{�����ƔN�x�̖@�l�łɌW�鏊�����z�y�є[�t���ׂ����z�i28�E6�E28�X�������j
�i�P�ʁF�~�j
�ʕ\�Q�\�Q �{���ېŎ��ƔN�x�̕������ʖ@�l�łɌW��ېŕW���@�l�Ŋz�y�є[�t���ׂ��Ŋz�i28�E6�E28�X�������j �i�P�ʁF�~�j
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���Q��������
 �ŗ��m�E�Ɣ����ӔC�ی����̎��� �i2017�N7��1���`2018�N6��30���j �ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̐Ŋz�T���i�����g��Ő��j�̓K�p���O�i67���j �����g�呣�i�Ő��ɂ�����u��ٗp�ҋ��^���x���z�v�̋L�ڌ��ɂ��ߑ�[�t�ƂȂ������� �����̂̊T�v�� �@�ŗ��m�́A����28�N4�����̖@�l�ł̐\���ɂ����āA�u�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���v��K�p���Đ\���������A�K�p�ɓ�����Y�t���ׂ��u�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���Ɋւ��閾���v�i�ȉ��u�v�Z�Ɋւ��閾���v�j�́u��ٗp�ҋ��^���x���z�v���ɁA����25�N4�����̋��^�x���z���L���ׂ��Ƃ���A����āA����26�N4�����̋��^�x���z���v�Z���Ă��܂����B �@����ɂ��u�ٗp�ҋ��^���x�������z�v���ߏ��ƂȂ�A���ʂƂ��ĉߑ�[�t�@�l�Ŋz���������������ߑ��Q�������������B ���R�����g�� �@�ŗ��m�́A�˗��҂�����28�N4�����ɏ�L�Ŋz�T���̏������������߁A��L�Ŋz�T����K�p���Đ\�������B�������A�T�����邽�߂́u�v�Z�Ɋւ��閾���v�̋L�ڂɂ����āA�u��ٗp�ҋ��^���x���z�v�̋��z��25�N4�����̋��^�x���z���L�ڂ��ׂ��Ƃ��땽��26�N4�����̋��^���x���z���L�ڂ��Đ\���������߁A�Ŋz�T���z�����Ȃ��Ȃ�A���̌��ʁA�ߑ�[�t�@�l�ŐŊz�������������B �@��L�Ŋz�T���Ɋւ��ẮA�[�u�@�̋K��ɂ��u�v�Z�Ɋւ��閾���v�ɋL�ڂ��ꂽ�u�ٗp�ҋ��^���x�������z�v�̌��x�z���ł���X���̐������F�߂��邪�A�{�����̂ɂ����ẮA�\�����ɋL�ڂ����u�ٗp�ҋ��^���x�������z�v������Ă������߁A���Y�葱���͔F�߂��Ȃ������B �@�ŗ��m�̊m�F�s������L�ڂ��ׂ����z����������̂ł���A�����ȋ��z���L�ڂ��Ă���Ήߑ�[�t�z�͔������Ă��Ȃ��������Ƃ���A�ŗ��m�ɐӔC����Ɣ��f���ꂽ�B �@���̌��ʁA����25�N4�����̋��^�x���z�𐳂����L�ڂ��Ă���ΐŊz�T���ł����z�ƁA����26�N4�����̋��^�x���z������ċL�ڂ������ƂŐŊz�T���ł����z�Ƃ̍��z��1,100���~��F�e���Q�z�Ƃ��A�ƐӋ��z30���~���T��������1,070���~���ی����Ƃ��Ďx����ꂽ�B �i2018�N7��1���`2019�N6��30���j �ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̐Ŋz�T���i�����g��Ő��j�̓K�p���O�i54���j �ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̐Ŋz�T���i�����g��Ő��j�̌v�Z��� �����g�呣�i�Ő��K�p�ɂ����āA�]�L���ׂ����z������ċL�ڂ������߉ߑ�[�t�ƂȂ������� �����̂̊T�v�� �@�ŗ��m�́A����28�N5���A�˗��Җ@�l�̕���28�N3�����@�l�ł̐\���ɂ����āA�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���i�����g�呣�i�Ő��j�̓K�p�ɂ�����Y�t���ׂ��ʕ\6(19)�̌ٗp�ҋ��^���x���z������ċL�ڂ��A�\�������o�����B �@���̌�A�˗��Җ@�l���Ŗ��������A�����g�呣�i�Ő��ɂ�����ʕ\6(19)�ٗp�ҋ��^���x���z�̌�L�ڂɋC�t���A�{���ߌ낪���o�����B �@����29�N9���A�Ŗ�����菊���g�呣�i�Ő��ɂ�����ʕ\6(19)�ٗp�ҋ��^���x���z��L�ڕ��ɂ��āA�����\�����L�ڊz�Ɍ�����Ƃ��čX���ʒm�����������ꂽ�B �@���̌�A�ŗ��m�͐R�������y�ѓ����n�ق֑i�ג�N�������Ȃ�������������F�߂�ꂸ�A���ʂƂ��Ĉ˗��Җ@�l���瑹�Q�������������B �����̔��o�̌o�܁� �@�˗��Җ@�l���Ŗ����������ۂɐŗ��m���x���z����L�ڂ��������ɋC�t�����o�����B �����̂̌����� �@�ŗ��m���A�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���i�����g�呣�i�Ő��j�̓K�p�ɓ�����A�ʕ\6(19)�̌ٗp�ҋ��^���x���z�̋L�ڂ����A����28�N3�����@�l�Ŋm��\�������쐬��o�������߁B ���Ŕ��ی��ɂ����锻�f�� �@�ŗ��m�̊m�F�s������ٗp�ҋ��^���x���z�̋L�ڂ���������̂ł���A�����ȋ��z���L�ڂ��Ă���Ήߑ�[�t�Ŋz�͔������Ȃ��������Ƃ���A�ŗ��m�ɐӔC����Ɣ��f���ꂽ�B ���x���ی����� �@�ߑ�[�t�ƂȂ����@�l�Ŋz�E�����Ŋz�E�s���Ŋz��1,300���~��F�e���Q�z�Ƃ��A�ƐӋ��z30���~���T��������1,270���~���ی����Ƃ��Ďx����ꂽ�B �����g�呣�i�Ő��̓K�p���O�ɂ��ߑ�[�t�ƂȂ������� �����̂̊T�v�� �@�ŗ��m�́A����28�N3�������畽��30�N3�����@�l�Ŋm��\�����쐬�̍ہA�����g�呣�i�Ő��K�p�ɂ��Č�����ӂ�A�\�������쐬���Ē�o�����B �@����31�N2���A�˗��Җ@�l�̌o���S���҂��w�E���Ċm�F�������ʁA�˗��Җ@�l�͗v�������Ă���Ŋz�T�����邱�Ƃ��\�ł��������Ƃ����o�����B �@�˗��Җ@�l�֕����Ƃ���A�Ŋz�T���ł����ɉߑ�[�t�ƂȂ����Ŋz�y�ё��Q�������̉v���Z���ɔ����ŕ��S�z�ɂ��āA�˗��Җ@�l���瑹�Q�����������������B �����̔��o�̌o�܁� �@�˗��Җ@�l�̌o���S���҂�菊���g�呣�i�Ő��̓K�p���O�̎w�E�����o�����B �����̂̌����� �@�ŗ��m���A����28�N3�������畽��30�N3�����̏����g�呣�i�Ő��̓K�p�ɂ��Ă̌�����ӂ�A�@�l�Ŋm��\�������쐬���Ē�o�������߁B ���Ŕ��ی��ɂ����锻�f�� �@�ŗ��m���A�˗��Җ@�l�ɂ��ď����g�呣�i�Ő��̓K�p���������A�Ŋz�T��������Ă���Ήߑ�[�t�Ŋz�͔������Ȃ��������Ƃ���A�����g�呣�i�Ő��̓K�p��ӂ������Ƃ͐ŗ��m�ɐӔC����Ɣ��f���ꂽ�B ���x���ی����� �@����28�N3�������畽��30�N3�����̉ߑ�[�t�@�l�Ŋz�E�Z���Ŋz��1,200���~��F�e���Q�z�Ƃ��A�ƐӋ��z30���~���T��������1,170���~���ی����Ƃ��Ďx����ꂽ�B �@�Ȃ��A�ی���ɂ����āu��Q�҂���ی��҂����葹�Q���������G�������̑��̉v���Ƃ��Čv�シ�邱�Ƃɂ��A��Q�҂��[�t���ׂ��@�l�ŁE�����ŁA�Z���ł��̑��̑d�ł̊z�������������ƂɋN�����鑹�Q�͊܂݂܂���i���j�v�ƒ�߂��Ă��邱�Ƃ���A���Q�������̉v���Z���ɔ��������Ŋz�ɂ��Ă͕ی����x�����̑Ώۊz�Ɣ��f���ꂽ�B (��)���ۃW���p�����{�����ЁF�ŗ��m��������@��1���i�Q�j �����C������ЁG�ŗ��m�E�Ɗ댯���ʖ@��1���i�Q�j �i2019�N7��1���`2020�N6��30���j �ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̐Ŋz�T���i�����g��Ő��j�̓K�p���O�i32���j �����g�呣�i�Ő��̓K�p���O�ɂ��ߑ�[�t�@�l�Ŋz�������������� �����̂̊T�v�� �@�ŗ��m�́A�˗��Җ@�l�̕���29�N3�����ȑO�ɂ��āA�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���i�ٗp�g�呣�i�Ő��j��K�p���邱�Ƃ����O���Ă��܂����B �@�˗��Җ@�l�֕����Ƃ���A����A�ŗ��m�͈˗��Җ@�l������e�ؖ��X�ւɂđ��Q��������������|�̒ʒm����̂����B �����̔��o�̌o�܁� �@�˗��Җ@�l���A�Ј����^�����ɂ��ߐő��K�p���̗L���Ɋւ��鎿�₪����ŗ��m���m�F�����Ƃ���A����30�N3�����͓K�p���Ă��邪�A����29�N3�����ȑO�ɂ��ẮA�ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���i�ٗp�g�呣�i�Ő��j��K�p���Ă��Ȃ����ƂɋC�Â����o�����B �����̂̌����� �@�ŗ��m�͖��N�̐Ő������ɂ��Č��C���Ŋw��ł������A�s���ӂ���{����ɂ����ēK�p���邱�Ƃ����O���Ă��܂������߁B ���Ŕ��ی��ɂ����锻�f�� �@�˗��Җ@�l�̕���27�N3�����ƕ���28�N3�����̌ٗp�ҋ��^���x���z�����������ꍇ�̖@�l�Ŋz�̓��ʍT���i�����g�呣�i�Ő��j�̓K�p��ӂ�A�@�l�Ŋm��\�������쐬��o�������Ƃ́A�ŗ��m�ɐӔC����Ɣ��f���ꂽ�B ���x���ی����� �@�ߑ�[�t�@�l�Ŋz��700���~��F�e���Q�z�Ƃ��A�Ɛ�30���~���T������670���~���ی����Ƃ��Ďx����ꂽ�B |
�b��ٌ̍�

���ŕs���R�����^�ٌ��^�ߘa���N6��27�� ���̗a����������o������A���̎q�ł���R�������l�̗a�������֓������ꂽ���K�̈ړ��������āA������q�ւ̑��^�ɓ����邩�ۂ�������ꂽ���� �K����ݎ،_��̒������Ȃ����������݂̂������ĐR�������l�ƕ��Ƃ̊Ԃɑ��^�ɂ��Ăَ̖��̍��ӂ��������ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ�������B LEX/DB26013024�^TKCLawLibrary(260) * |
�ٔ���i�Q�j
147-2 ��147�ጤ����@�������^�ɂ�����u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v�̈Ӌ` �����n�ف@�ߘa�Q�N�P���R�O�������i��P�R�jLEX/DB 25582001 �y�I��̗��R�z �{���́A�����Ԃ̗A�����Ɠ���ړI�Ƃ�������@�l���A���̑�\������̈�l�Ɏx�������������^�̑S�z���ɎZ�����Đ\���������Ƃ���A�ېŒ����A�{���������^�̊z�ɂ́A�@�l�Ŗ@�R�S���Q���ɒ�߂�u�s�����ɍ��z�ȕ����v������Ƃ��Ė@�l�ł̍X�����������s�������Ƃɑ��āA���̎����������߂鎖�Ăł���B �@���̑��_�́A�{���������^�̂����A�u�s�����ɍ��z�ȕ����v�i�@�l�Ŗ@�R�S���Q���j�̗L���y�т��̋��z�ł���B �@���̑��_���l�@���邤���ł́A�@�l�Ŗ@�R�S���Q���̎�|�A�ړI�͉����A�u�s�����ɍ��z�ȕ����v�Ƃ͉����A���̔��f��͉����A�Ȃǂ����ƂȂ�B���������@�l�Ŗ@�́A�Ȃɂ䂦�ɉߑ�Ȗ������^���K�����ׂ��������ƂȂ�B �@�@���_��́A�@�����P�W�N�̖������^�Ɋւ���@�l�Ŗ@�����̈Ӗ��A�A�����̈�Ƃ��āA�ގ��@�l�̒��o�A�I����@�A�K�����z�̔�����@�͂ǂ�����ׂ����A�Ȃǂ������ł��낤�B�]�O�̓����n�ٕ����Q�W�N�S���Q�Q�������i�A����Ў����A�c�g�����Ƃ������j���Q�l�ɂȂ�B �y���Ă̊T�v�z�iP62�j �@�{���́C�w�i�����j���C�w�̑�\������̈�l�ł���o�S�Ɏx���������^�̑S�z���̊z�ɎZ�����Đ\�������Ƃ���C�����s�����́C�������^�̊z�ɂ͖@�l�Ŗ@�R�S���Q���ɋK�肷��s�����ɍ��z�ȕ���������C�������̊z���̊z�ɎZ�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ȂǂƂ��āC�w�ɑ��C�@�l�ł̍X�����������������Ƃ���C���������̈ꕔ����������߂鎖�Ăł���B�����́C�����̎咣��F�߂Ȃ������B�@ �y�����v�|�z�iP79�j �@�{���������^�Ɂu�s�����ɍ��z�ȕ����v�����邱�Ƃ͖��炩�Ƃ����ׂ��ł���A�����āA���̕����̋��z�́A�����̔��グ�邽�߂ɖ{����\�҂��ʂ������E�Ӌy�ђB�������Ɛт��������������ɂ��������ƂɊӂ݁A���Y�����Ώێ��ƔN�x�ɂ�����{���e���o�@�l�̖������^�̍ō��z���镔��������ɓ�����ƔF�߂�̂������ł���B �W�@�߂̒�� �@�@�l�Ŗ@�R�S���Q���́C�����@�l�����̖����ɑ��Ďx�����鋋�^�i�ȉ��u�������^�v�Ƃ����B�j�̊z�̂����s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���z�́C���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��C�����̊z�ɎZ�����Ȃ��|�K�肷��B�����āC�����̈ϔC�����@�l�Ŗ@�{�s�߂V�O���P���́C��L�u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v�̔���ɂ��ē�̊��݂��Ă���B �i�P�j����� ���Y�����̐E���̓��e�C���Y�����@�l�̎��v�y�юg�p�l�ɑ��鋋�^�̎x���̏C���Y�����@�l�Ɠ���̎��Ƃ��c�ޖ@�l�ł��̎��ƋK�͂��ގ�������́i�ȉ��u���Ɨގ��@�l�v�Ƃ����B�j�̖������^�̎x�����ɏƂ炵�C���Y�����̐E���ɑ���Ή��Ƃ��đ����ł���ƔF�߂�����z���邩�ۂ��ɂ���Ĕ��� �i�Q�j�`��� �芼�̋K�薔�͊��呍��̌��c�ɂ���߂�ꂽ�������^�̌��x�z���邩�ۂ��ɂ���Ĕ��� �u������ɂ����đ����ȋ��z���镔���v�y�сu�`����ɂ����Č��x�z������z�v�̂��������ꂩ�������z���C�u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v�Ɋ܂܂�� �y�Q�l���z �@�l�Ŗ@�i����28�N�@��15���ɂ������O�j �i�������^�̑����s�Z���j ��34���@�i���j �Q�@�����@�l�����̖����ɑ��Ďx�����鋋�^�i�O�����͎����̋K��̓K�p��������̂������B�j�̊z�̂����s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���z�́A���̓����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��B �R�`�U�@�i���j �@�l�Ŗ@�{�s�߁i����29�N���ߑ�106���ɂ������O�j �i�ߑ�Ȗ������^�̊z�j ��70���@�@��34�l���2���i�������^�̑����s�Z���j�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂���z�́A���Ɍf������z�̍��v�z�Ƃ���B ��@���Ɍf������z�̂��������ꂩ�������z �C�@�����@�l���e���ƔN�x�ɂ����Ă��̖����ɑ��Ďx���������^�i�@��34�l���2���ɋK�肷�鋋�^�̂����A�ސE���^�ȊO�̂��̂������B�ȉ����̍��ɂ����ē����B�j�̊z�i��3���Ɍf������z�ɑ���������z�������B�j���A���Y�����̐E���̓��e�A���̓����@�l�̎��v�y�т��̎g�p�l�ɑ��鋋�^�̎x���̏A���̓����@�l�Ɠ���̎��Ƃ��c�ޖ@�l�ł��̎��ƋK�͂��ގ�������̖̂����ɑ��鋋�^�̎x���̏��ɏƂ炵�A���Y�����̐E���ɑ���Ή��Ƃ��đ����ł���ƔF�߂�����z����ꍇ�ɂ����邻�̒����镔���̋��z�i���̖����̐�����ȏ�ł���ꍇ�ɂ́A�����̖����ɌW�铖�Y�����镔���̋��z�̍��v�z�j ���@�芼�̋K�薔�͊��呍��A�Ј�����Ⴕ���͂����ɏ�������̂̌��c�ɂ������ɑ��鋋�^�Ƃ��Ďx�����邱�Ƃ��ł�����K�̊z�̌��x�z�Ⴕ���͎Z����@���͋��K�ȊO�̎��Y�i���ɂ����āu�x���Ώێ��Y�v�Ƃ����B�j�̓��e�i���ɂ����āu���x�z���v�Ƃ����B�j���߂Ă�������@�l���A�e���ƔN�x�ɂ����Ă��̖����i���Y���x�z������߂�ꂽ���^�̎x���̑ΏۂƂȂ���̂Ɍ���B���ɂ����ē����B�j�ɑ��Ďx���������^�̊z�i�@��34���5���ɋK�肷��g�p�l�Ƃ��Ă̐E����L��������i��3���ɂ����āu�g�p�l���������v�Ƃ����B�j�ɑ��Ďx�����鋋�^�̂������̎g�p�l�Ƃ��Ă̐E���ɑ�����̂��܂߂Ȃ��œ��Y���x�z�����߂Ă�������@�l�ɂ��ẮA���Y���ƔN�x�ɂ����ē��Y�E���ɑ��鋋�^�Ƃ��Ďx���������z�i�����Ɍf������z�ɑ���������z�������B�j�̂����A���̓����@�l�̑��̎g�p�l�ɑ��鋋�^�̎x���̏��ɏƂ炵�A���Y�E���ɑ��鋋�^�Ƃ��đ����ł���ƔF�߂�����z�������B�j�̍��v�z�����Y���ƔN�x�ɌW�铖�Y���x�z�y�ѓ��Y�Z����@�ɂ��Z�肳�ꂽ���z���тɓ��Y�x���Ώێ��Y�i���Y���ƔN�x�Ɏx�����ꂽ���̂Ɍ���B�j�̎x���̎��ɂ����鉿�z�ɑ���������z�̍��v�z����ꍇ�ɂ����邻�̒����镔���̋��z�i�����Ɍf������z������ꍇ�ɂ́A���Y�����镔���̋��z���瓯���Ɍf������z�ɑ���������z���T���������z�j ��@�����@�l���e���ƔN�x�ɂ����Ă��̑ސE���������ɑ��Ďx�������ސE���^�̊z���A���Y�����̂��̓����@�l�̋Ɩ��ɏ]���������ԁA���̑ސE�̎���A���̓����@�l�Ɠ���̎��Ƃ��c�ޖ@�l�ł��̎��ƋK�͂��ގ�������̖̂����ɑ���ސE���^�̎x���̏��ɏƂ炵�A���̑ސE���������ɑ���ސE���^�Ƃ��đ����ł���ƔF�߂�����z����ꍇ�ɂ����邻�̒����镔���̋��z �@�O�@�i���j ���@������V�@�@→�@�������^�@�����ސE���^�@(�K���z�����Z��) �����ܗ^�i�����s�Z���j �y���������z�^�y�����v�|�z (1) �������^�̂����u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v���s�Z���Ƃ�����|�B �@�l�Ŗ@�Q�Q���R���Q���́A�����@�l�̊e���ƔN�x�̏����̋��z�̌v�Z��A���Y���ƔN�x�̔̔���A��ʊǗ���̑��̔�p�i���p��ȊO�̔�p�œ��Y���ƔN�x�I���̓��܂łɍ��̊m�肵�Ȃ����̂������B�j�́A�ʒi�̒�߂�������̂������A���Y���ƔN�x�̑����̊z�ɎZ������|�K�肵�A�����āA���̕ʒi�̒�߂Ƃ��āA���@�R�S���P���́A�����@�l�����̖����ɑ��Ďx�����鋋�^�i�������^�j�̂����A����̗�O�Ƃ��Ē�߂鋋�^�ɊY�����Ȃ����̂̊z�́A�����̊z�ɎZ�����Ȃ��|�K�肵�A����ɁA��L��O�ɌW��������^�i�Ⴆ�A�����P���ɒ�߂������z���^�j�ɂ��Ă��A�����Q���́A�u�s�����ɍ��z�ȕ����̋��z�v�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���z�͑����̊z�ɎZ�����Ȃ��|�K�肵�A�������^�́A���@�Q�Q���R���Q���ɋK�肳�ꂽ��p�̈��ł͂�����̂́A�@�l�Ɩ����Ƃ̊W�Ɋӂ݂�ƁA�������^�̊z�����ɑ����̊z�ɎZ�����邱�ƂƂ���A�@�l�ɂ����Ė������^�̎x���z���ق����܂܂Ɍ��肵�A�@�l�̏����̋��z����X�ɏ��Ȃ����邱�Ƃɂ��A�@�l�ł̉ېł��������Ȃǂ̕��Q�������邨���ꂪ����A�����ŁA�@�l�Ŗ@�R�S���́A��L�ʒi�̒�߂�݂��A�����̊z�ɎZ�������������^����L�̂悤�ȕ��Q���Ȃ��ƍl��������̂Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��A�������^�̋��z����ɂ����霓�Ӑ��̔r����}��A�����ĉېł̌��������m�ۂ������̂Ɖ������B (2) ���㑍���v�������X���ɂ��钆�ł̖{���������^�̊z�̍����y�ё������͒������s���R�ł���ƕ]��������Ȃ��Ƃ�������B �{���������^�́A���̖����Ɏx�����ꂽ�������^�Ɣ�ׂĒ��������z�ł������łȂ��A�w�Ёi�����j�̎��v���A�{���e���ƔN�x��ʂ��Č����X���ɂ���A�g�p�l�ɑ��鋋�^�̎x���z�������Ȃ����ɂ₩�Ȍ����X���ɂ��钆�ŁA����ɋt�s����`�ŋ}�����Ă���A���̌��ʁA�w�Ђ̉���c�Ɨ��v�ip.91�c�Ɨ��v+�{���������^�j�̑啔�����߂邱�ƂƂȂ��āA�w�Ђ̉c�Ɨ��v��傫����������Ɏ����Ă���̂ł���A���̂��ƂɊӂ݂�ƁA�{����\�҂̐E�����e��w�Ђ̔��グ�邽�߂ɖ{����\�҂��ʂ������E�ӓ��ɏƂ炵�Ă��A�{���������^�̊z�̍����y�ё������͒������s���R�ł���ƕ]��������Ȃ��B (3) ���Ɨގ��@�l�̖������^�̎x������c�����邽�߂Ɍ����������̗p�������o��͍����I�ł���Ƃ�������B ���������́A�{�����o����Ɋ�Â��Ė{���e���o�@�l�𒊏o���Ă���Ƃ���A���̊T�v�́A�k�P�l��ʌ����̊e�Ŗ����̊NJ����i�t�����Ŗ����y�т���ɗאڂ���U�̐Ŗ����̊NJ����ł����P���Ώۋ��̂ق��A����ȊO�̍�ʌ����̂W�̐Ŗ����̊NJ����ł����Q���Ώۋ����܂ށB�j��ΏۂɁA�k�Q�l���{�W���Y�ƕ��ނɂ�����啪�ށu�q�P�r�|�����ƁA�����Ɓv�̒����ށu�T�S�|�@�B�����Ɓv�̏����ށu�T�S�Q�����ԉ����Ɓv����̎��ƂƂ��A�k�R�l������z�������̔�����z�̂Q���̂P����Q�{�܂ł͈̔͂ɂ���@�l�ŁA�k�S�l��\������ɑ��Ė������^�̎x��������A���A���ׂ̌W�����Ă��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ�v����Ƃ������̂ł���A�{�����o����́A�����̓��Ɨގ��@�l�𒊏o�����y�ђ��o�Ώۋ��Ƃ��č����I�Ȃ��̂ł���B(p.88-89) TKCBAST�@× (4) ���Ɨގ��@�l�̖������^�̎x������c�����邽�߂Ɍ������������o�ɗp�������o��͕s�����ł���Ƃ̌����̎咣��r�˂�������B �w�i�����j�́A�������������o�����{���e���o�@�l�́A�i���j�]�ƈ��������������啝�ɑ����A�i���j����c�Ɨ��v�ɂ��Č����̔��z�ȉ��ł���@�l���܂܂�Ă���A�i���j�]�ƈ��P�ʔ��㓙���w�����啝�ɏ��Ȃ��A�i���j�傽�鎖�Ƃ̓��e���w�ƈقȂ�@�l���܂܂�Ă���A�i���j�w�ƈقȂ葼�̊�Ƃ���̓Ɨ�����L���Ă��Ȃ��@�l���܂܂�Ă��铙�̗��R�ɂ��A�����Ƃ͎��Ƃ̋K�͂Ȃ����������قɂ��Ă��邩��A�{���e���o�@�l�͂w�̓��Ɨގ��@�l�ɓ����炸�A�܂��A���̒��o�ɗp����ꂽ�{�����o��̓��e���̂��s�����ł���Ǝ咣���邪�A���Ɨގ��@�l�̖����ɑ��鋋�^�̎x���́A�@�l�Ŗ@�{�s�߂V�O���P���C���K�肷��u���Y�����̐E���ɑ���Ή��Ƃ��đ����ł���ƔF�߂�����z�v���邩�ۂ����f���邽�߂̔�r�Ώۂ̈�ɂ����Ȃ����̂ł��邵�A���Ɨގ��@�l�̒��o�ɓ������āA���Ƃ̋K�͂Ȃ��������̌��i�ȓ��ꐫ��v������ꍇ�ɂ́A���Ƃ̓��e��K�͓��ɓ����I�ȗv�f������@�l�ɂ��āA��r�ɏ\���Ȑ��̓��Ɨގ��@�l�𒊏o���邱�Ƃ�����ɂȂ�A�@�l�Ŗ@�R�S���y�і@�l�Ŗ@�{�s�߂V�O���P���C���@�l�̖������^�̋��z����ɂ����霓�Ӑ��̔r����}��A�����ĉېł̌��������m�ۂ��悤�Ƃ�����|��v�p���邨���ꂪ����A��L�̋K�肪�u����̎��Ɓv�A�u���ƋK�͂��ގ��v�Ƃ̕�����p���Ă���̂��A��L�́u�����ł���ƔF�߂�����z�v�f���邽�߂̔�r�Ώۂɗp������@�l�̒��o�ɓ�����A���Ƃ̋K�͂Ȃ��������̌��i�ȓ��ꐫ�܂ł͗v������Ȃ����Ƃ�O��Ƃ������̂Ɖ�����A�����āA��L�i���j�`�i���j�ɂ����Ăw���咣����A�]�ƈ����A����c�Ɨ��v�y�я]�ƈ��P�ʔ��㓙�́A���ꂼ��A���ƋK�̗͂ގ����f�����v�f�ƂȂ蓾����̂ł��邪�A�����ŁA������z�����ƋK�͂�}��̂ɗL�p�Ŗ��m�Ȍo�ώw�W�ł���A����݂̂ł����ƋK�̗͂ގ����f����̂ɑ������̂ł����āA��L�̂Ƃ��蓯�Ɨގ��@�l�̒��o�ɓ������Ď��Ƃ̋K�͂Ȃ��������̌��i�ȓ��ꐫ�܂ŗv���������̂ł͂Ȃ��ȏ�A���ƋK�̗͂ގ����f���邽�߂ɏ�L�i���j�`�i���j�̎咣�ɌW��e�v�f�ɂ��ďd�˂čl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ͂������A����炪�l������Ă��Ȃ����Ƃ������āA�{�����o�������s�����ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B (5) ���Ɨގ��@�l�̒��o�Ώۋ�����ʌ����Ɍ���͍̂����I�łȂ��Ƃ̌����̎咣��r�˂�������B �w�i�����j�́A�C���^�[�l�b�g�o�R�Œ��Î����Ԃ𗎎D���ă}���[�V�A�ɗA�o�Ƃ����w�̋ƑԂɏƂ点�A���{�����ɂ�����n��I�ȉe���͖������邱�Ƃ��ł����A��ʌ����ɂ͂w�Ɠ��l�̒��Î����Ԃ̗A�o�Ƃ��c�ޖ@�l�͏��Ȃ��̂ł��邩��A���o�Ώۋ�����ʌ����Ɍ���͍̂����I�ł͂Ȃ��A�X�Ɋg�傷�ׂ��ł���|�咣���邪�A�w�́A��ʌ����ɖ{�Ў�������L���A�g�p�l�ɋ��^���x�����Ď��Ƃ��s���Ă���̂�����A�������̈ێ��Ǘ��ɌW���p��l����̓_�Œn��I�ȉe�����Ă��邱�Ƃ͔ے�ł����A�܂��A�����I�Ȗ{�����o��������āA��P���Ώۋ��y�ё�Q���Ώۋ��ɂ����钊�o���s�������ʁA��r�ɕK�v���\���Ȑ��̖@�l�����ɒ��o�ł��Ă���ȏ�A���o�Ώےn����g�債�Ȃ����Ƃ����������������̂Ƃ͂������A���������āA�w�̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B (6) �{���������^�̊z�́A�{����\�҂̐E�����e��E�ӓ��܂��Ă������I�͈͂���Ƃ�������B �{���������^�̎x���Ɩ{���e���o�@�l�̖������^�̎x���Ƃ��r����ƁA�����Q�R�N�V�����ɌW��{���������^�̊z�́A����ɑΉ����钲���Ώێ��ƔN�x�ɂ�����{���e���o�@�l�̍ō��z�Ɣ�r���Ă���S�{�A���z�ɂ��Ė�Q���~���z�ƂȂ��Ă���A�������A�{���������^�͖{���e���ƔN�x��ʂ��ĂQ�`�S�{�����������߁A���҂̊r���͔N�x���ƂɊg�債�A�����Q�V�N�V�����ɌW��{���������^�̊z�́A�{���e���o�@�l�̍ō��z�̖�P�O�{�A���z�ɂ��Ė�S���V�O�O�O���~���z�ƂȂ�Ɏ����Ă���A���̂悤�Ȗ������^�̎x���̊r���́A�{����\�҂̐E�����e�⌴���̔��グ�邽�߂ɖ{����\�҂��ʂ������E�ӓ��܂��Ă��A�����I�Ȕ͈͂�����̂Ƃ��킴��Ȃ��B �iY�P���ɔ{���A���ߋ��z�Ŕ��f�j (7) ���o�������Ɨގ��@�l�̖������^�x���z�Ƃ��ĔF�肷�ׂ��z�́A�����̊z�ɎZ�����ꂽ�������^�̊z�Ƃ���̂������Ƃ�������B �w�i�����j�́A�{�����o�@�l�P�̑�\������ɑ���������^�x���z�Ƃ��ĔF�肳�ꂽ�z�ɁA�����̊z�ɎZ������Ă��Ȃ��������^�̊z���܂܂�Ă��Ȃ����Ƃɂ��āA�s�����ł���|�咣���邪�A�w�̓��Ɨގ��@�l�𒊏o����ړI�́A��\������ł���{����\�҂̖������^�̂����ɑ����̊z�ɎZ�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��u�s�����ɍ��z�ȕ����v�����邩�ۂ��f����ۂ̔�r�Ώۂ�_�ɂ���̂�����A���Ɨގ��@�l�̖������^�x���z�Ƃ��ĔF�肷�ׂ��z�́A�����̊z�ɎZ�����ꂽ�������^�̊z�Ƃ���̂������ł���A���������āA�w�̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B (8) �{���������^�́u�s�����ɍ��z�ȕ����v�͖{���e���o�@�l�̖������^�̍ō��z���镔��������ɓ�����Ƃ�������B �{���������^�Ɂu�s�����ɍ��z�ȕ����v�����邱�Ƃ͖��炩�Ƃ����ׂ��ł���A�����āA���̕����̋��z�́A�����̔��グ�邽�߂ɖ{����\�҂��ʂ������E�Ӌy�ђB�������Ɛт��������������ɂ��������ƂɊӂ݁A���Y�����Ώێ��ƔN�x�ɂ�����{���e���o�@�l�̖������^�̍ō��z���镔��������ɓ�����ƔF�߂�̂������ł���B (9) �{���������^�̂����u�s�����ɍ��z�ȕ����v�ɓ�����̂́A�{���e���o�@�l�̖������^�̕��ϊz���镔���ł���Ƃ̌��������̎咣��r�˂�������B �x�i�퍐���������j�́A���̎�ʓI�咣�Ƃ��āA�{���������^�̂����u�s�����ɍ��z�ȕ����v�ɓ�����̂́A�{���e���o�@�l�̖������^�̕��ϊz���镔���ł���Ǝ咣���邪�A�{�����o����ɂ��w�i�����j�̓��Ɨގ��@�l�̒��o���K�����������Ȏ��Ƃ̋K�͂Ȃ��������̓��ꐫ�̗v���̉��ɂ��ꂽ���̂łȂ��Ƃ���A�w�̔��グ�邽�߂ɖ{����\�҂��ʂ������E�Ӌy�ђB�������Ɛѓ��̖{���ɂ����鎖��Ɋӂ݂�ƁA��L�̕��ϊz���镔����S�āu�s�����ɍ��z�ȕ����v�ɓ�������̂Ƃ����ꍇ�A�{����\�҂̐E���ɑ���Ή��Ƃ��ĕs�����ƔF�߂�ׂ��łȂ��������܂܂�邱�ƂɂȂ��Ă��܂������ꂪ����A��������ƁA��L�̂悤�Ȗ{���̎���̉��ł́A�{���e���o�@�l�̖������^�̍ō��z���镔���������āu�s�����ɍ��z�ȕ����v�ɓ�����ƔF�߂�̂������ł��邩��A�x�̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B (10)�{���������^�̊z�ɌW��u�s�����ɍ��z�ȕ����v�́A�X������������Ă��Ȃ����ߎ��ƔN�x�̕��ϊz���镔���̋��z�Ƃ��ׂ��Ƃ̌����̎咣��r�˂�������B �w�i�����j�́A���̗\���I�咣�Ƃ��āA�{���e���ƔN�x�ɂ����锄����z�����c�Ɨ��v���A�����Q�P�N�V�����y�ѕ����Q�Q�N�V�����̕��ϊz�Ƃ����ނ˓��������͓������ȏ�ł��邱�ƂɊӂ݂�A�������^�Ƃ��đ����ƔF�߂�����z�́A��L�e���ƔN�x�ɂ����Ė{����\�҂Ɏx�����ꂽ�������^�̕��ϊz�i�P���Q�W�O�O���~�j���������̂ł͂Ȃ�����A�u�s�����ɍ��z�ȕ����v�̋��z�́A��L���ϊz���镔���Ɍ�����Ǝ咣���邪�A�w���咣����P���Q�W�O�O���~�Ƃ������z�́A��L�e���ƔN�x�ɑΉ�����{���e���o�@�l�̖������^�̍ō��z��啝�ɏ�����̂ł��邱�Ƃ����F����A�w�̏�L�咣�́A��L�e���ƔN�x�ɂ����Ė{����\�҂Ɏx�����ꂽ�������^�̊z�Ɂu�s�����ɍ��z�ȕ����v���Ȃ����Ƃ�O��ɂ�����̂ł���Ƃ���A��L�e���ƔN�x�ɌW��@�l�łɂ��čX������������Ă��Ȃ����Ƃ������āA�����̔N�x�ɂ����Ė{����\�҂Ɏx�����ꂽ�������^�̊z�Ɂu�s�����ɍ��z�ȕ����v���Ȃ��ƔF�߂邱�Ƃ͂ł����A�����āA���̂ق��ɁA�����F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��̂ł��邩��A�w�̗\���I�咣�͂��̑O����������̂ł����āA�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B |
���{���P���~�ȉ��̉�Ђ̂W�̗��_

�ߘa2�N4��1�����ݖ@�ߓ��i�ŐV���͍��Œ��v�m�F�j
�� �|�C���g
���{����1���~�ȉ��̖@�l�ɂ��ẮA�Ŗ���u������Ɓv�ƈʒu�Â����A���̗D���[�u���K�p����܂��B �܂�A���{����1���~���邩�ǂ����Ŕ[�Ŋz�ɑ傫�ȍ����o�邱�ƂɂȂ�܂��B �����ł́A���{��1���~�ȉ��̉�Ђ�8�̃����b�g�ɂ��Ă��Љ�܂��B ���{���Ƃ����{���Ƃ́A��Аݗ��̍ۂ���̍ۂɁA�o���҂��略�����܂ꂽ�����̂��Ƃ������܂��B���{�������z���ꂽ�茸�z���ꂽ�肵�����ɂ́A���{���Ƃ�������Ȗڂŏ��������܂��B�Ȃ��A��Аݗ��̍ۂɕ������܂ꂽ�����̂����A�����͎��{���ł͂Ȃ����{�������Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B���{�������Ƃ́A��Ђ̋Ɛт������������ɔ����Đςݗ��ĂĂ��������̂��Ƃł��B �i�P�j���{���͂�����ɂ��ׂ��� ���{���̊z�͉�Ђ̋K�͂�̗͂�\���̂ŁA�u������Α����قǂ悢�v�Ǝv������������ł��傤�B�m���Ɏ��{���������ƁA�����̈�ۂ��ǂ��Ȃ�P�[�X�������͎̂����ł��B ���{���Ƃ́A��Аݗ��̍ۂ���̍ۂɁA�o���҂��������A���{����1,000���~�ȏ�ɂ���ƁA�ŏ��̔N�������ł̉ېŎ��Ǝ҂ƂȂ�܂����A1���~����ƈ�C�ɐŕ��S���d���Ȃ�܂��B �Ŗ���́A���{���̊z��1���~�ȉ��̉�Ђ́u������Ɓv�ƈʒu�Â�����̂ŁA�Ŗ��㑽���̂����ȋK�肪�K�p�����悤�ɂȂ邩��ł��B ���{���Ƃ́A��Аݗ��̍ۂ���̍ۂɁA�o���҂����������āA���{���̊z���߂�ꍇ�ɂ�1,000���~����ꍇ��1���~����ꍇ�Ń��C��������Ƃ������Ƃ܂��Č�������K�v������܂��B ���{��1���~�ȉ��̉�Ђ̃����b�g���{����1���~�ȉ��̉�Ђ́A�y���ŗ����K�p���ꂽ��A�N800���~�̌��۔�g����������A�J�z��������S�z�T���ł���ȂǁA���܂��܂Ȃ����ȋK�肪�K�p����܂��B�������A�e��Ђ̎��{���̊z��5���~�ȏ゠���āA���̐e��Ђ�������100���ۗL���銮�S�q��Ђ�ݗ������ꍇ�ɂ́A���̎q��Ђ͎����I�ɂ͒�����Ƃł͂Ȃ��Ƃ݂Ȃ���A�D���[�u���K�p����Ȃ��Ȃ�܂��B �i1�j�y���ŗ����K�p����� ���{��1���~���̖@�l�̏ꍇ�ɂ́A�@�l�ŗ���23.2%�ł��B ����A���{��1���~�ȉ��̉�Ђ͔N800���~�܂ł̏����ɂ��Ă�15%�ŔN800���~����ƁA23.2%�ƂȂ�܂��B �܂�A�N800���~�܂ł̐ŗ����y�������̂ŁA���̕��ߐł��邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯�ł��B �Q�ƁF���Œ��u�@�l�ł̐ŗ��v No.5759 �@�l�ł̐ŗ� [�ߘa3�N9��1�����ݖ@�ߓ�] �ΏېŖ� �@�l�� �T�v �@�l�ł̐ŗ��́A���\�̖@�l�̋敪�ɉ����A���ꂼ�ꎟ�\�̂Ƃ���Ƃ���Ă��܂��B �Ȃ��A���\�́y�@�z�́A�����g�����܂��͓���̈�Ö@�l���A���e�@�l�ł���ꍇ�̐ŗ��ł��B �ŗ�
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �i��1�j�@�ΏۂƂȂ�@�l�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B �i1�j�@�e���ƔN�x�I���̎��ɂ����Ď��{���̊z�������͏o�����̊z��1���~�ȉ��ł�����̂܂��͎��{�������͏o����L���Ȃ����́i�i��5�j�Ɍf�������̈�Ö@�l�������܂��B�j�B�������A�e���ƔN�x�I���̎��ɂ����Ď��̖@�l�ɊY��������̂ɂ��ẮA������܂��B �C�@���݉�Ђ���ъO�����݉�� ���@��@�l�i���Ɍf����@�l�������܂��B�ȉ������ł��B�j�Ƃ̊Ԃɂ��̑�@�l�ɂ�銮�S�x�z�W�����镁�ʖ@�l �i�C�j�@���{���̊z�܂��͏o�����̊z��5���~�ȏ�̖@�l �i���j�@���݉�Ђ���ъO�����݉�� �i�n�j�@����@�l �n�@100�p�[�Z���g�O���[�v���̕����̑�@�l�ɔ��s�ϊ����܂��͏o���̑S���ڂ܂��͊ԐڂɕۗL����Ă���@�l�i���Ɍf����@�l�������܂��B�j �j�@�����@�l �z�@����ړI��� �w�@����@�l �i2�j�@��c���^�@�l�ȊO�́A��ʎВc�@�l����ш�ʍ��c�@�l �i��2�j�@����31�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ����ēK�p���O���Ǝҁi���̎��ƔN�x�J�n�̓��O3�N�ȓ��ɏI�������e���ƔN�x�̏������z�̔N���ϊz��15���~����@�l���������܂��B�ȉ������ł��B�j�ɊY������@�l�̔N800���~�ȉ��̕����ɂ��ẮA19�p�[�Z���g�̐ŗ����K�p����܂��B �i��3�j�@�����g�����ŁA���̎��ƔN�x�ɂ����镨�i�������Ƃ̂����X�܂ɂ����čs������̂ɌW��������z�̔N���ϊz��1,000���~�ȏ�ł���Ȃǂ̈��̗v���������̂̔N10���~���̕����ɂ��ẮA22�p�[�Z���g�̐ŗ����K�p����܂��B �i��4�j�@���v�@�l���Ƃ݂Ȃ���Ă�����̂Ƃ́A�F�n���c�́A�Ǘ��g���@�l����ђc�n�Ǘ��g���@�l�A�@�l�ł��鐭�}���A�h�ЊX�搮�����Ƒg���A�����c�������@�l�Ȃ�тɃ}���V�������֑g������у}���V�����~�n���p�g���������܂��B �i��5�j�@����̈�Ö@�l�Ƃ́A�[�@��67����2��1���ɋK�肷�鍑�Œ������̔F��������̂������܂��B �i��6�j�@����31�N4��1���Ȍ�ɊJ�n���鎖�ƔN�x�ɂ����ēK�p���O���Ǝ҂ɊY������@�l�̔N800���~�ȉ��̕����ɂ��ẮA19�p�[�Z���g�i���̓���̈�Ö@�l���A���e�@�l�ł���ꍇ�ɂ́A20�p�[�Z���g�j�̐ŗ����K�p����܂��B �����@�ߓ� �@�@66�A81��12�A143�A�[�@42��3��2�A67��2�A68�A68��8�A68��100�A68��108�A��28�����@����21�A26�A27�A29 �i2�j�N800���~�ȉ��̌��۔�g������ ���{��1���~���̖@�l�̏ꍇ�ɂ́A�����Ƃ̈��H��Ȃǂ̌��۔��50���������Z������܂��B ����A���{��1���~�ȉ��̖@�l�̏ꍇ�ɂ́A�N800���~�ȉ��̌��۔�g������u�O���Ƃ̈��H���50���v�u�N��800���~�v�̂����A�����ꂩ�������z�ɂ��đ����ɎZ�����邱�Ƃ��ł��܂��B �܂�A�N��800���~�܂Ŗ������ɑ����ɎZ�����邱�Ƃ��ł���̂ŁA�ߐŌ��ʂ�����܂��B �Q�ƁF���Œ��u���۔�͈̔͂Ƒ����s�Z���z�̌v�Z�v �i3�j�J�z���������T������� ���{��1���~���̖@�l�̏ꍇ�A�ߋ�10�N�ȓ��ɔ��������J�z�������̂����A���̎��ƔN�x�̏������z��100����50�܂ł��̏������z����T�����邱�Ƃ��ł��܂��B ����ɑ��Ď��{����1���~�ȉ��̖@�l�̏ꍇ�ɂ́A�ߋ�10�N�ȓ��ɔ��������J�z�������̂������̎��ƔN�x�̏������z�܂ł��T�����邱�Ƃ��ł��܂��B �܂�A�����̏������z�Ɖߋ�10�N�ȓ��ɔ��������J�z���������r���āA�J�z�������̂ق��������ꍇ�ɂ́A�����̏������[���ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �Q�ƁF���Œ��u�F�\�������o�������ƔN�x�̌������̌J�z�T���v �i4�j�J�z���������J�ߊҕt����� �J�z�������̌J�ߊҕt�Ƃ́A�F�\�������o���鎖�ƔN�x�Ɍ������z���������ꍇ�ɁA���̌������z�����̎��ƔN�x�J�n�̓��O1�N�ȓ��ɊJ�n�������ƔN�x�ɌJ��߂��āA�@�l�Ŋz�̊ҕt�𐿋��ł���Ƃ������x�ł��B ���̌J�z�������̌J�ߊҕt�̐��x�́A���{��1���~���̖@�l�̏ꍇ�ɂ͓K�p���ꂸ�A���{����1���~�ȉ��̖@�l�݂̂ɓK�p�����D���[�u�ł��B ���Ƃ��A�O����1,000���~�̉ېŏ���������150���~�̖@�l�ł�[�߂��Ƃ��܂��B �Ƃ��낪����1,000���~�̌����ƂȂ������ɂ́A�O���x������150���~�̖@�l�ł̊ҕt�����邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�傫�ȐߐŌ��ʂ�����܂��B �Q�ƁF���Œ��u�������̌J�߂��ɂ��ҕt�v �i5�j���z�������p���Y�̑����Z�����Ⴊ�K�p����� �Œ莑�Y���擾�����ꍇ�ɂ́A�@��ϗp�N���ɉ����Č������p���s���̂������ł��B �������A���{��1���~�ȉ��̖@�l��30���~�����̌Œ莑�Y���擾�����ꍇ�ɂ́A�N��300���~�܂ł��̑S�z���ɎZ�����邱�Ƃ��ł��܂��i����18�N4��1������ߘa4�N3��31���܂Łj�B �Q�ƁF���Œ��u������Ǝғ��̏��z�������p���Y�̎擾���z�̑����Z���̓���v �i6�j���ʍT���A���ʏ��p���K�p����� ���ʍT���A���ʏ��p�̑����͑d�œ��ʑ[�u�@�ɂ���Ē�߂�����Ԍ���̓���ł��B ���ʍT���A���ʏ��p�Ƃ��ẮA���Ƃ��Έȉ��̂悤�Ȑ��x������܂��B
�����̓���́A�قƂ�ǂ����{��1���~�ȉ��̖@�l�݂̂��ΏۂƂȂ��Ă�����A��葽���̍T���z���F�߂�ꂽ�肷��Ȃǂ̋K��ƂȂ��Ă��܂��B �O�q�����Ƃ�����Ԍ���̂��̂������A�v�����ύX�����̂ŁA�����̐��x�𗘗p���鎞�ɂ͐T�d�Ɋm�F����悤�ɂ��܂��傤�B �Q�ƁF���Œ��u���ʏ��p�E���ʐŊz�T���v �i7�j������Ђ̗��ۋ��ېł��K�p����Ȃ� �u���ۋ��ېŐ��x�v�Ƃ́A����̓�����Ёi����1�O���[�v��50���ȏ�̊����ۗL���j���A���v��z�����Ȃ��œ������ۂ����ꍇ�ɂ́A�ېŗ��ۋ��z��10�`20�����悶�����z���A�ʏ�̖@�l�łƂ͕ʂɉېł���Ă��܂��Ƃ������x�ł��B ���̐��x�́A���{��1���~���̖@�l�̏ꍇ�ɂ͑ΏۂƂȂ�܂����A���{��1���~�ȉ��̖@�l�ɂ��Ă͓K�p����܂���B �Q�ƁF���Œ��u���ʐŗ���K�p����Ȃ����蓯����Ђ͈̔́v �@�@�@�Ŋz�v�Z�̉����i������Ђ̗��ۋ��ېŐ��x�j �i8�j�O�`�W���ېł��K�p����Ȃ� �u�O�`�W���ېŁv�Ƃ́A�n���ł��v�Z���鎞�ɐԎ��ł��ېłł���悤�ɂ��邽�߂ɁA���������łȂ���V���^�⎑�{���A���ؗ��Ȃǂɑ��Ă��ŋ����ۂ��Ƃ����ېŕ����̂��Ƃ������܂��B ���̊O�`�W���ېłɂ���āA���{��1���~���̖@�l�ɂ��Ă͏������̂ق��ɕt�����l������ю��{�����ۂ���邱�ƂɂȂ�܂��B �t�����l���́A��V���^�A���ؗ��A���x�����q�ƒP�N�x���v���ېŕW���Ƃ��A���{���͎��{�����̊z���ېŕW���Ƃ��ĉېł���܂��B ���̊O�`�W���ېł́A���{��1���~�ȉ��̖@�l�ɂ͓K�p����܂���B �Q�ƁF���Œ��u�y�����z�i���Ɛł̑����Z���̎����̓���j�v ���{��1,000���~�������Ƃ���ɂ�������܂ł��Љ���悤�ɁA���{����1���~�ȉ���1���~���ł́A1���~�ȉ��̕��������̃����b�g������܂����A���{��1,000���~�������ƐŐ��ʂł���ɂ����ɂ���܂��B�i1�j����ł�2�N�ԖƐł���� ���{��1,000���~�ȉ������̖@�l�́A�ŏ���2���̏���ł��Ɛł���܂��B ������1���ڂ̔����̔��㍂�܂��͋��^�̎x���z��1,000���~����ƁA2���ڂ͏���ł̉ېŎ��Ǝ҂ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪���{��1,000���~�����ł���A1���ڂ̏���ł͖Ɛł���܂��B �������A���{���̊z�Ɋւ�炸1�N�ڂɑ��z�̐ݔ��������s���ȂǁA�a����������ł��x����������ł̂ق��������ꍇ�ɂ́A���̎x�������������ҕt���Ă��炤���Ƃ��ł��܂��B �i�Q�j�@�l�Z���ł����� �@�l�Z���ł̋ϓ����Ƃ́A���Ƃ���Ђ��Ԏ��ł����N�[�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ŋ��ł��B ���̋ϓ����́A���{���̊z�ɂ���ĈقȂ�܂��B �]�ƈ���50�l�̏ꍇ�Ŏ��{����1,000���~�ȉ��Ȃ�7���~�ł����A1,000���~�����18���~�ɂȂ�܂��B �܂Ƃ��ȏ�A���{��1���~�ȉ��̉�Ђ̐Ő����8�̃����b�g�ɂ��Ă��Љ�܂����B���{���̊z�������ƐŖ���s���ɂȂ邱�Ƃ������A����1,000���~����ꍇ��1���~����ꍇ�Ŏ�舵���ɑ傫�ȍ�������܂��B �������A���{�����Ő���̃����b�g�����Œ�߂���̂ł͂���܂��A����1,000���~���郉�C����1���~���郉�C���ɂ��ď\���������������ł��A��Ђ̏i���F�̎擾�Ȃǁj�ɂ��������{���̊z�����肷��悤�ɂ��܂��傤�B �i���jhttps://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-04/cat-small-11/8049/�i�ꕔ���j |

�����]�˃^���[�i�����X�J�C�c���[�j |
|
��350-1314 ��ʌ� ���R�s �����u 167-2�@������� �����p�^�R���^�Η��ŗ��m�������@☎04(2946)7704
|